



2025.10.01
国内最大級の総合化学メーカーとして、『革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていく「KAITEKI(※1)」の実現をリードしていくこと』をパーパスとし、「グリーン・スペシャリティ企業」という目標に向けた経営ビジョン「KAITEKI Vision 35(※2)」を掲げる三菱ケミカル株式会社(以下、三菱ケミカル)さま。日立ソリューションズは、それらの実現に向けて、DX戦略パートナーとして協創を進めてきました。業界共通の課題とされていた「プラントの定期修理業務」では、デジタル技術を駆使して抜本的な現場の業務改革を後押し。生産性向上を図りながら、SXの実現に向けた取り組みがすでに始まっています。協創から生まれる新たな価値とは何か。あるべきパートナーシップの姿とは。両社の想いを伺いました。

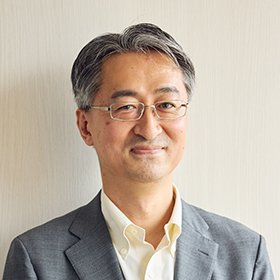
井深 浩
三菱ケミカル株式会社
デジタル統括本部 デジタルプランニング部 部長
研究所や製薬会社でのシステム企画、経営企画部門での資源配分管理、情報システム子会社でのシステム営業や大型統合PJなどのアライアンス対応を経験。2025年度から、デジタル部門の活動を横断的に管理/調整する部を率いて、活動方針策定やITスペンド管理、リスク管理、ベンダー管理、人材育成を指揮している。

森本 吏一
三菱ケミカル株式会社
広島事業所 設備技術部 部長
入社以来、事業所設備の設備管理業務に従事し、現職に至る。また、設備技術部業務のDXを推進し、進捗管理システム導入時は、ワーキングリーダーとして検討を行った。

田平 操子
三菱ケミカル株式会社
本社 技術本部 設備技術部 企画セクション マネージャー
九州事業所入社、事業所の設備管理部門にて企画及びDX推進に携わり、2023年度より本社に異動。全社設備技術部門の業務標準化を軸にしたDX推進に注力している。

小林 茂樹
株式会社日立ソリューションズ
営業統括本部
デジタルイノベーション営業本部
デジタルソリューション第2営業部 部長代理
入社以来、製造業のお客さまを中心に、インフラ、セキュリティ、クラウドなど多岐にわたる領域での提案・導入を経験。近年は、製造現場のDX推進に注力しており、お客さまとの協創活動を通じて、業界が抱える課題の解決に取り組んでいる。

小林 哲也
株式会社日立ソリューションズ
サステナブルシティビジネス事業部
スマート社会ソリューション本部
スマートメンテナンスソリューション部 グループマネージャ
入社後、携帯電話、スマートフォン向けソフトウェアの開発に従事した後、スマートビル事業の立ち上げを経験。現在は、製造業のお客さまに対して、設備保全業務のDXを実現するスマートメンテナンスソリューションの事業開発・推進を主導している。
井深:まず私たち三菱ケミカルグループのパーパスは、革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていく「KAITEKI」の実現をリードしていくことです。2020年には、2050年の社会のあるべき姿をイメージし、そこからバックキャステティングするかたちで中長期経営基本戦略「KAITEKI Vision 30」を策定しました。
しかし、それから4年が経ち、社会は想像以上に複雑化し、その変化のスピードはますます加速しています。顧客のニーズも多様化し、要求の水準も格段に高くなってきました。そうした中でも、私たちは素材の力で顧客を感動させる「グリーン・スペシャリティ企業」であり続けたいと考えています。そんな目標を、経営層と従業員がしっかりと共有するために策定したのが「KV35」です。

井深:グリーン・スペシャリティ企業として、社会が求める最適なソリューションを提供し続けていくためには、デジタル活用が不可欠であることは論を俟ちません。その上で今後は、「グリーン・ケミカルの安定供給基盤」「環境配慮型モビリティ」「データ処理と通信の高度化」といった領域を中心に、デジタルを活用した新たな価値の創造に取り組んでいきたいと考えています。
一方で、そのすべてを自社だけで遂行するのは合理的ではありません。そこで当社のデジタル部門では、私たちのめざすべき方向性を理解し、技術面・リソース面から強力な伴走支援を行っていただける企業を「戦略パートナー」として位置づけ、長期的な協創関係を築いてきました。日立ソリューションズも、その一社です。
井深:技術領域のカバー率が高いこと、なかでも工場やプラント、ビルなどの制御機器を管理・運用する「OT(Operational Technology)」の領域で、多くの実績と高い技術力を有していることが、最大の理由です。ITに関する技術への期待だけではなく、日立グループ全体として広義の「ものづくり」に携わるなかで培ってきた技術やノウハウに大きな信頼を寄せていた、と言い換えるとわかりやすいかもしれません。
小林(茂):おっしゃる通り、私たちはIT企業であると同時に、日立グループの一員として、ものづくり領域の課題解決にも深く関わってきました。その中で、既に確立されたプロダクトやソリューションも多数あります。それらを組み合わせたりカスタマイズしたりすることで、三菱ケミカルさまにもスピーディーに価値を提供できると考えていました。
井深:選定にあたっては、設備技術部をはじめとする「現場」に近いポジションから、日立ソリューションズを推す声が強く上がっていたことをよく覚えています。現場の課題に寄り添いながら、PoC(概念実証)からソリューションの実装まで、トータルで支援してもらえるのではないか、という期待がありました。
小林(哲):実際、「現場の声」に耳を傾けることは、私たちが課題解決に取り組む上で、何よりも大切にしていることのひとつです。そうしたスタンスを評価してくださる三菱ケミカルさまだからこそ、私たちも戦略パートナーとして、ともに新たな価値の協創に挑んでいけるのだと感じています。
田平:ご存じの通り、いま多くの企業は、少子高齢化による労働人口の減少という深刻な課題に直面しています。特に製造業の現場では、人手不足に加え、ベテラン技術者の退職による技術継承の難しさが顕著になってきました。
現場を支えるだけではなく、社会全体の持続可能性にどう貢献していくかも問われる時代となっています。こうした背景を踏まえ、私たち設備技術部門では、KV35に紐付く「技術ビジョン」を策定しました。具体的には設備管理の高度化を実現するために「設備管理プラットフォーム」を基盤とした業務の標準化と、PDCAサイクルの構築を進めています。日立ソリューションズとともに着手したプラントの定期修理業務のDXは、この取り組みの一環となります。

森本:プラントの定期修理は、大規模な事業所になると、数百から数千件にものぼる工事を、限られた期間のなかで実施しなければなりません。工事に関わる関係者は、数千人規模になるのですが、近年は働き方関連法案への対応や労働人口不足により、労働力の確保が大きな課題となっていました。
そこで作業員の稼働率向上をめざし、まず着目したのが進捗管理業務の効率化です。これまでは工事の進捗を確認するために担当者が現場まで足を運んだり、電話で都度確認する必要がありました。さらに進捗の共有は紙ベースで行われていたため、記入に遅れや漏れがあると、リアルタイムでの情報共有が難しくなってしまいます。結果として、次の工程の着工が遅れたり、再調整によって時間のロスが発生することも少なくありませんでした。
こうした課題を解決するために、日立ソリューションズとともに取り組んだのが、クラウド上で全工程の進捗を管理する「プラント向け予防保全 進捗管理サービス」の導入です。
森本:任意のタイミングで、どこからでも各現場の進捗状況を確認・更新できるようになったことは大きな変化です。作業が完了すると、次工程を担う施工会社に自動で通知が届くため、現地や電話での確認作業も不要になりました。情報連携のスピードと精度は、目に見えて向上したと感じています。さらに着工受付の手続きとシステムを連携させたことで、進捗管理項目の入力漏れも防止できるようになりました。また、事前に工事工程について協力会社と製造/設技で協議を重ねることでロスや無駄のない計画となり、実施時の稼働率が更に向上したと評価しています。
進捗管理システムの導入と並行して、その他の業務改革も進めた結果、作業員の稼働率は従来比で16%程度向上。これらにより、定期修理の期間短縮や作業要員の最適化、当社社員の単月あたりの時間外労働時間削減など、当初の想定を大きく上回る効果が得られています。

森本:システムの導入に向けて最初に取り組んだのが、岡山事業所でのPoCです。それにあたって、複数の会社からシステムのご提案をいただいたのですが、その中で最も「現場目線」で対話できたのが日立ソリューションズでした。
小林(哲):多くの協力会社さまが使用することを前提としたシステムだったので、まず意識したのはUI(ユーザーインターフェース)の使いやすさです。導入後の利用定着までを見据えると、これまで進捗管理表の作成に使われていたExcelと同じような感覚で操作できることが重要だと考えました。そうした観点から、当社のグループ会社である、株式会社日立ソリューションズ東日本が提供するプロジェクト管理統合プラットフォーム「SynViz S2」をベースに、新たなシステムの構築を提案させていただいたかたちです。
小林(茂):開発がスタートしてから現在に至るまで、何よりも心がけているのは「現場の課題」に真摯に応えていくことです。ただ本当は、提案段階からプラント(事業所)に伺い業務を理解し現場の課題を体感したかったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大と重なってしまい、残念ながら直接訪問することはかなわず......。代わりに、森本さまをはじめとするプロジェクトメンバーのみなさまとは、オンラインでほぼ毎週定時後(業務終了後)にオンラインミーティングの場を設けていただき、丁寧に議論を重ねていきました。

森本:「簡単に使えるものにしてほしい。できるだけシンプルで。」ということは、私たちとしても繰り返しお伝えさせていただきました。どんなに優れたシステムでも、現場ですぐに使えなければ意味がありません。なかなか難しい要望も多かったと思いますが、それにしっかりと応えてくださったことには、本当に感謝しています。導入後も、協力会社に向けた説明会にご同席いただくなど、現場への浸透にも力を尽くしていただきました。
森本:まずは「プラント向け予防保全 進捗管理サービス」を全社標準システムとして展開しています。全社ワーキンググループを立ち上げ、各事業所メンバーが参画し日立ソリューションズとも連携しながら、それぞれの事業所・工場の課題に応えるかたちでシステムの最適化を進めているところです。
田平:今回の取り組みの大きな意義は、現場の声を拾い上げ、ボトムアップによる業務改善を実現できたことだと感じています。今後もトップダウンとボトムアップのバランスをとりながら、組織全体で再現性と持続性のある高度な設備管理体制を築いていきたい。そのためにも、現場のニーズを熟知した日立ソリューションズのようなパートナーの存在は不可欠です。
小林(哲):私たち日立ソリューションズとしても、今回の取り組みを通じて、三菱ケミカルさまとの「共通言語」を築けたことは、大きな収穫でした。だからこそ、システムの導入をゴールではなく、新たなスタートにしていきたいと感じています。これをはじめの一歩として、デジタル技術やデータを活用した設備管理のさらなる高度化に、これからも伴走していければ幸いです。
小林(茂):「プラント向け予防保全 進捗管理サービス」については、業界内からも大きな反響があったと伺っています。この事例をきっかけに、工程管理のクラウド化が、定期修理業務のスタンダードになる可能性もある。業界を牽引する三菱ケミカルさまとともに、プラント分野全体の持続可能性に貢献していければと感じています。
井深:大きな期待を寄せているのが、当社の重点事業領域である「グリーンケミカル安定供給基盤DX」に関する協創です。たとえば、直近ではLCA(ライフ・サイクル・アセスメント)やGHG(温室効果ガス排出量)のデータ収集を、いかに省力化・デジタル化していくかが重要な課題となっています。この点については、当社の実状を深く理解し、データ分析にも豊富な知見を持つ日立ソリューションズの力を、ぜひお借りしたいですね。
また今後は、基幹システムの統合と並行して、周辺システムの集約化や標準化にも本格的に取り組んでいく予定です。ここでも、製造業向けに多彩なソリューションを提供する日立ソリューションズの力強い支援に、大いに期待しています。
小林(茂):私たちとしても、協創の裾野をさらに広げていければと考えています。繰り返しになりますが、三菱ケミカルさまが直面する課題の解決は、業界全体の変革にも直結しています。そしてそれは、人口減少や技術継承といった、より大きな社会課題の解決にも寄与するはずです。
小林(哲):同感です。戦略パートナーとして、これからも現場のみなさんの「リアルな声」に耳を傾けながら、私たちの知見とソリューションを有機的に組み合わせることで、三菱ケミカルさま全体のDXを着実に後押ししていければと思っています。

井深:そうおっしゃっていただけると、心強いです。これはあくまで個人的な見解ですが、やはりせっかくならば日本企業同士でタッグを組んでいきたい、という気持ちがあります。それが日本の産業全体のサステナビリティを高めることにもつながっていくと思うからです。そのためにも、まずは私たち自身が日立ソリューションズから「選ばれる会社」であり続けたいと感じています。お互いに切磋琢磨しながら、ともに新たな価値を生み出していける。そんな関係性を築いていけたらと思います。