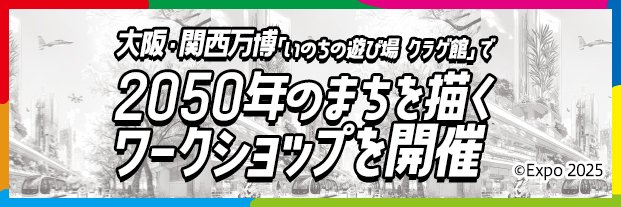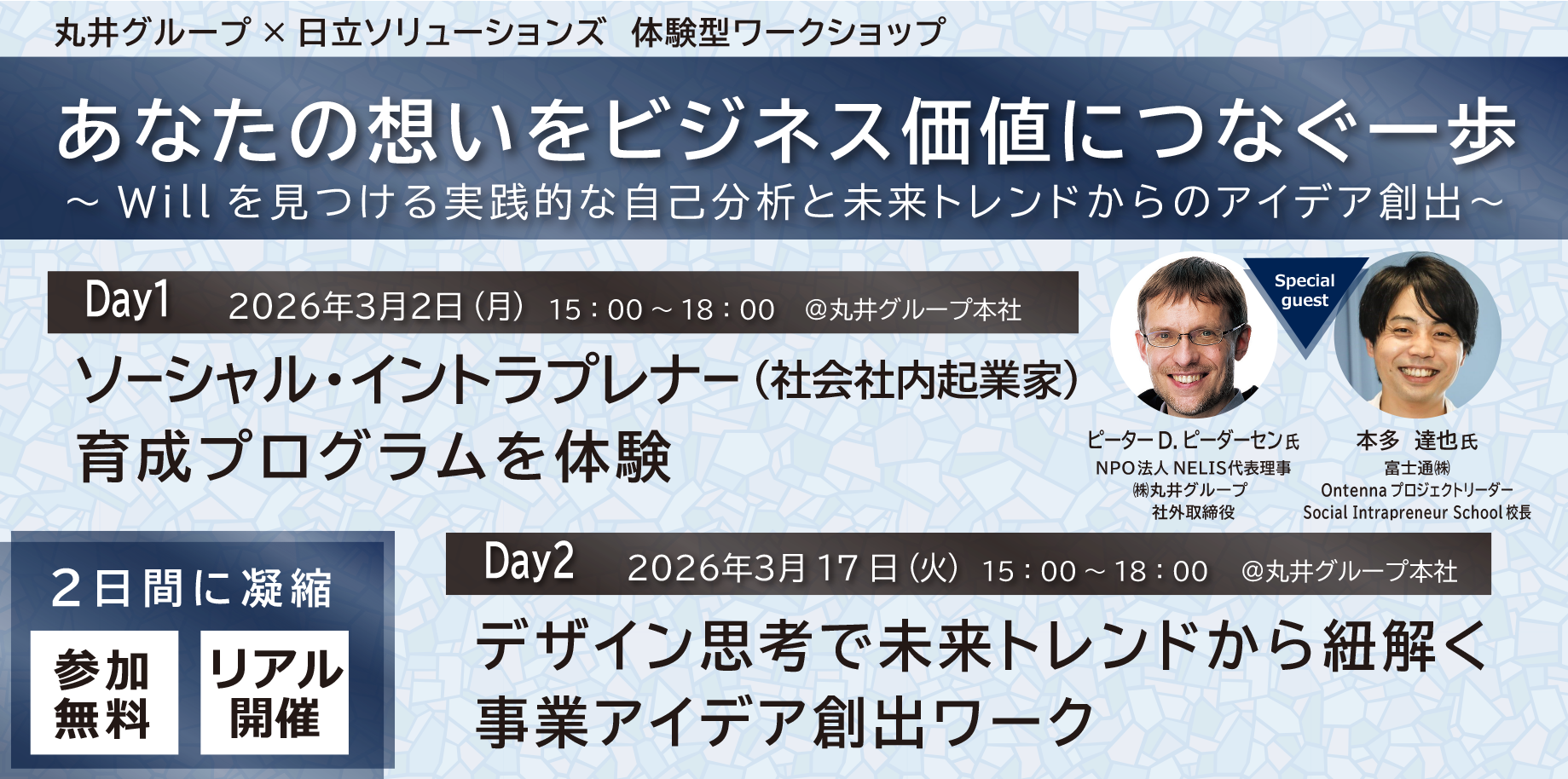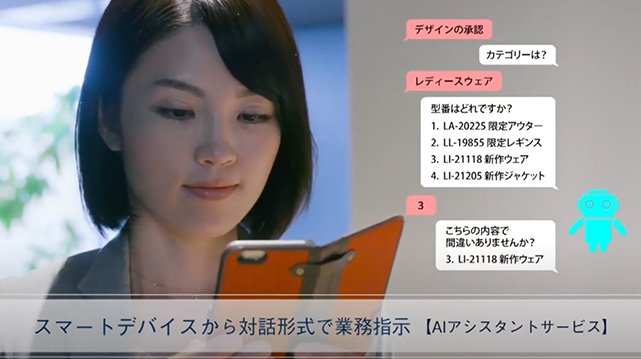※本記事は2023年2月に掲載されたものです
コンピューター内の空間で擬似的な体験をする
世界がコミュニケーションの場へ拡張
 1954年生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。東京大学大学院工学系研究科 教授、同 先端科学技術研究センター 教授、同 大学院情報理工学系研究科 教授などを歴任。2018~20年 東京大学連携研究機構バーチャルリアリティ教育研究センター機構長。20年から現職。専門はシステム工学、ヒューマンインタフェース、バーチャルリアリティ。 |
※黒字= 廣瀬通孝 氏
──メタバース(Metaverse)という言葉をよく聞くようになりました。メタバースは主に3次元の仮想空間サービスを指しますが、先生が研究してきたVR(仮想現実)とはどのような関係にあるのでしょうか。
VRが一般的に話題に上るようになったのは最近のことですが、実は昔からある技術です。私自身、大学の教員になって少し経った頃、人間と機械の境界としてのヒューマンインタフェースの研究をしていて、VRに出合いました。1980年代の終わり、日本で言えば平成が始まった頃です。
VRの出現により、コンピューターで作られた空間に入り込むことで擬似的な体験ができるようになりました。90年代の第1期VRのプレーヤーはコンピューター系の企業が中心で、そこで議論されたのはVRの体験のインタフェースになるゴーグルの性能に代表される技術面の課題でした。当時は「どうやって使うか」の議論が欠けていたのです。
 |
2016年、高額だったVRゴーグルの世界に、米国企業が10万円を切るヘッドマウントディスプレイで市場参入してきました。これはVRに大きな変化をもたらす1つの要因になりました。当時、興味を持った若い学生が「これは社会を変えます!」と力説したのを覚えています。製造業で技術開発や活用を考えていた第1期VRから、利用者サイドが興味を持つ第2期VRへの変化が起こったのです。
平成とともにやってきたVRは、時代が令和になり新しいVRとして広がりを見せ始めました。そこに新型コロナウイルスの感染拡大が発生。コロナ禍の影響はもちろんネガティブなものです。しかし、情報に関わる人間にとっては、ポジティブな一面もないわけではありませんでした。テレワークやリモートワークが一般に普及し、デジタルの世界が、対抗手段として有効だと社会が身にしみてわかったのです。
──そうした変遷を経て、いまメタバースの必要性が叫ばれるようになったのですね。
メタバースは、21年頃から話題に上るようになりました。これまでリアルワールドの中で自由に活動してきたのに、コロナ禍では行動に制約がかかります。アクティビティを上げるには、バーチャルという選択肢が不可欠です。米フェイスブックがメタに名称変更したのも、メタバースへの期待と決意があったからでしょう。
一方でメタバースは、30年の歴史を持つVRとそう違うものではありません。言葉自体は1992年の小説で出てきた仮想空間サービスの名称でした。
メタバースは、人々が生活する世界としての仮想空間であり、そこだけを見ればVRと同様です。ただしVRでは、目の前に見える3次元の対象を自由に動かしたりするような「人とモノ」の関係が重要でした。ところがVRが3次元空間としてネットワーク上で展開されていくと、「人と人」の関係が生まれます。VRワールドに多くの人が存在して、コミュニケーションの場になるわけです。こうなるとメタバースに近づきます。
|
VRとメタバースでは求められることが変化する  |
コミュニティを取り込みメタバースは
社会生活基盤になる
──メタバースの成立にはどのような条件があるとお考えでしょうか。
メタバースの定義や考え方は数多くあり、それぞれが間違いではないと思います。そうした中で、メタバースが今後の社会に定着するかどうかを判断する基準の1つに、基盤になれるかどうかという点があると思います。
VRは「あれば便利な技術」ですが、多くの人にとってはなくても困らないものでしょう。一方、メタバースはその中でコミュニティが成立すると「なくてはならない技術」として基盤化することが求められていきます。VRが成長してメタバースへと育っていく中で、その技術はインフラとしての意味合いが強くなります。
混沌として先が見通しづらいリアルの世界よりも、バーチャルの世界に良いことや楽しいことがあると考える人もいます。メタバースには、コロナ禍における救世主としてリアルに代わるコミュニティを実現する可能性もあります。リアル世界のオルタナティブ(代替)ワールドになるわけで、そこでお金が循環するようになればビジネスも立ち上がるでしょう。もちろんそうしてつくり出した世界が、急になくなってしまうと多くの人が困ることになる。メタバースは社会生活基盤としてきちんと運用されなければならないのです。
──コミュニティという側面がVRよりも強化されるメタバースでは、人間同士はどのように付き合うことになるのでしょうか。

廣瀬氏の研究室にある3Dスキャナーで制作した
アバター。まさにご本人そのものの姿を再現できる |
メタバースの上では、自分自身の分身として作ったキャラクターの「アバター」がコミュニケーションを担います。3Dスキャナーを使えば、今では本人そっくりのアバターを作れます。誰がどう見ても「廣瀬先生」というアバターです。でも、私としては、もっと格好良くなりたいかもしれません。より格好良いアバターを自分の分身として使うこともできるでしょう。
そう考えると、アバターを所有するということは、理想の自分を作り上げるという意味で、遺伝子組換えと同じような効果をもたらします。メタバース上の人たちにとって、アバターはすでに本人そのものかもしれません。
ちなみに、ソーシャルVRゲームでは、ゲームの合間もずっとVR空間に存在する「住民」がいます。興味深いのは、住民は圧倒的に男性が多いのに、アバターは女性のキャラクターが多いこと。メタバースでは性別も自由に選べます。さらに、メタバースでは1つのアバターを複数人で所有したり、1人がアバターを使い分けたりすることもできます。自分の本来の身体と、話す内容、ブランド、精神などがバラバラに分散される世界です。自分の価値を切り売りできる世界ともいえるでしょう。
もう1つ注目しているのが働き方との関係です。コロナ禍以前に、VRとHR(人材)について学内で議論したことがありました。まだテレワークが一般化する前でしたが、仮想化した空間で働くことができれば、新しい働き方が生まれるだろうという話になりました。
東京の仕事に地方から参加できれば、過疎化や高齢化の課題に答えが出せるかもしれません。外出するのが辛くなってきた高齢者でも、仮想空間ならば通勤や移動をせずにスキルを活かした仕事ができるでしょう。無理に自動運転などを実現しなくても、仮想空間で社会と高齢者がつながることができます。
また、外出せずに仕事ができれば、移動のためにエネルギーを使わなくて済みますからSDGsの達成にも一役買います。人間関係の変化から、新しい社会が生まれる可能性があるのです。
メタバースと社会が同時にイノベーション
するため技術に加えて社会科学の視点も
 |
──リアルとバーチャルの世界の間を融合させるには様々な課題がありそうです。課題とどうやって折り合いをつけばよいのでしょう。
メタバースが世の中に受け入れられるかどうかは、イノベーションへの受容性と関係していると感じます。メタバースに効果があるからといって、周辺の状況が育っていないところにいきなり新しいものを放り込むと混乱が生じます。
「高齢社会や地方創生に役立ちますよ」「環境負荷も減りますよ」といっても、社会の様々な側面が一緒になってメタバースを構築する必要があります。多方面で同時に一歩踏み出すような進化ができるかどうかが、近い将来のメタバースの成功に関わります。
違う視点も紹介しましょう。日本では「仮想」「虚像」などの意味で使われがちなバーチャルという言葉には、「実質の」「本質の」といった意味もあります。この世界では、物事の本質が見えてくるのです。
例えば、コロナ禍で私は国際会議にあまり行かなくなりました。知識を得るための国際会議は、バーチャルな開催でもあまり問題がないことがわかってきたからです。しかし、国際会議では懇親会での交流を重視していた先生方もいます。実は国際会議の本質は、知識を得ることではなく交流にあったのではないかと、バーチャルな時代になって改めて感じています。
バーチャルな空間のメタバースでは、より物事の本質が見えてきて、既存の職種や職業が何のために必要だったのかが議論されるようになるのではないでしょうか。
──メタバースの実現には、技術が大きく貢献します。社会科学的な学問の関わりは必要でしょうか。
東京大学にはバーチャルリアリティ教育研究センターという全学の横断組織があります。VRは理系の研究に近いため、工学部、理学部が中心となり、身体に関わる医学部やコンテンツ面に関わる文学部が交ざるような状況です。
ところがメタバースになると、法学部と経済学部が俄然関わるようになってきます。ルールメーキングは法学の役割ですし、情報が循環する中で価値をどのように移転するかを考えるのは経済学の役割です。
人々の常識やルールは、歴史を重ねて多くの人に納得されている部分があります。しかし、VRやメタバースの世界では、プログラマーが悪気なく書いたプログラムによって、一気にルールが規定されてしまうリスクがあります。工学系の私たちにはなじみのない部分です。こういったルールを議論することなくデジタル化するのは危険だという感覚を開発者が持つことは、今後のメタバースの広がりにとって重要なことだと感じています。
そうはいっても、メタバースによって人が集まって活動を繰り返せる仮想空間ができ上がってきたことは事実であり、メタバースには様々な可能性があります。企業にとっては、メタバースで自分たちが得意なものや提供しているものの本質が何かを見つめ直して活かす方法を見つけられたら、その中で生き残っていけるのではないでしょうか。
 |
「取材のための写真撮影も、もっと格好良く作ったアバターに任せたいところです」と笑うのは、メタバースの取材を受けてくださった東京大学の廣瀬通孝名誉教授。すてきで柔和な笑顔が印象的な廣瀬名誉教授だが、メタバース化した社会においては、御本人としてはアバターとなった姿を気に入っていらっしゃるご様子。しかしきっと、柔らかく相手を包んでくださる雰囲気は、アバターになっても変わらないと信じています。