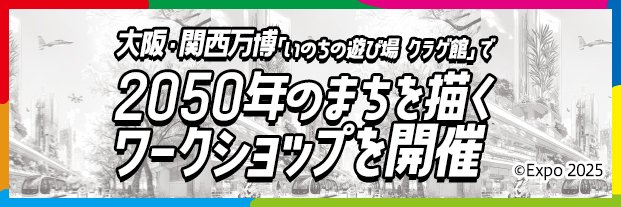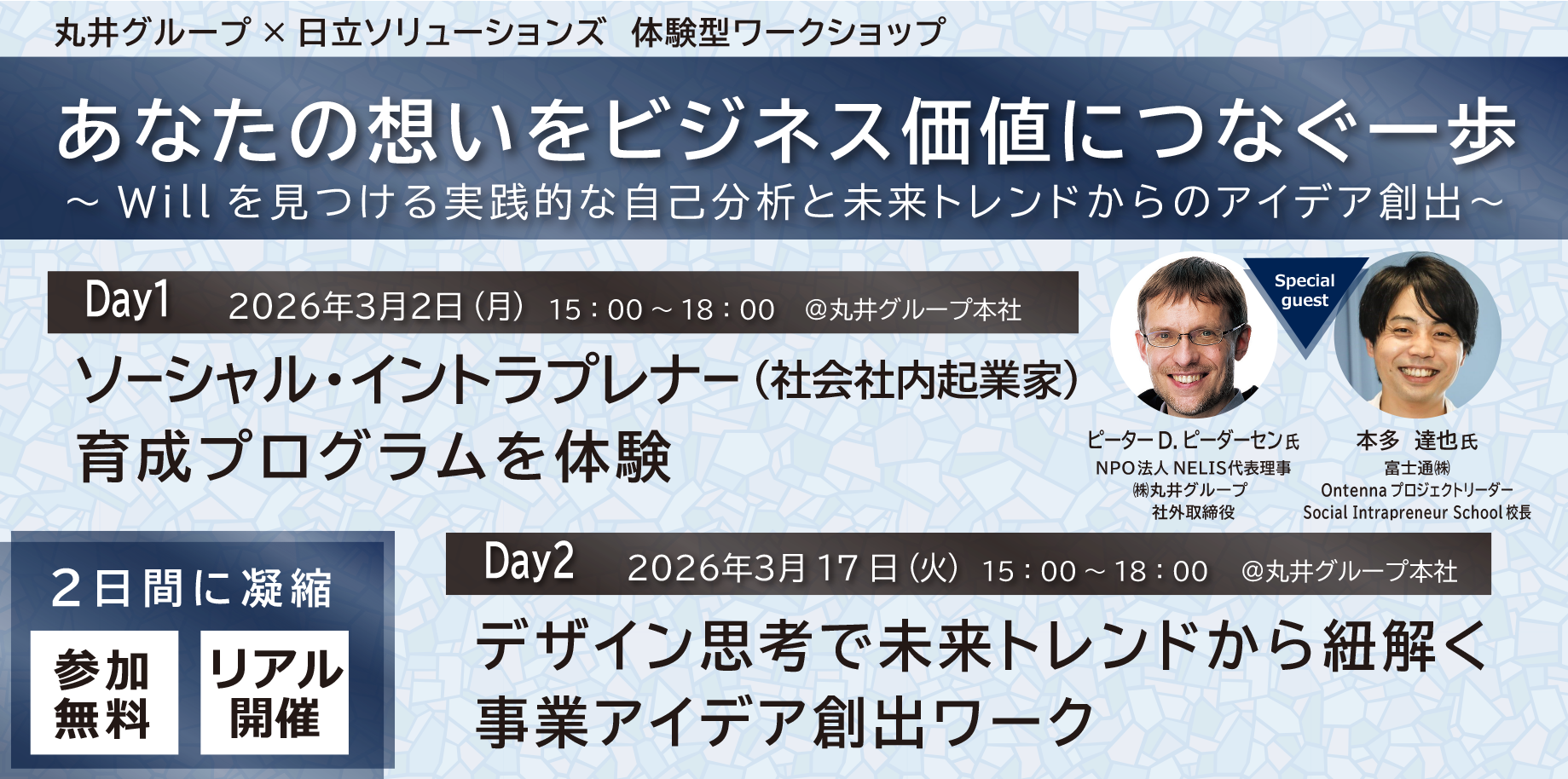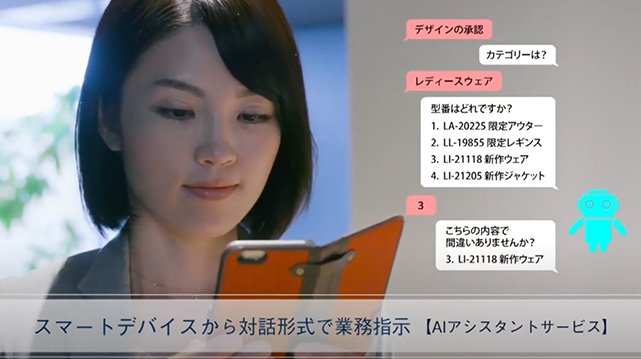※本記事は2022年10月に掲載されたものです
ビールの「鮮度」に勝負を懸ける
 1981年東京都板橋区生まれ。上智大学中退後、セールスプロモーションを手がける広告会社に入社。5年間の勤務後に退職し、麦酒企画を設立。高円寺に1号店を出店する。現在は、酒類卸売りの柴田屋酒店傘下のSAKE-YA JAPAN取締役として、全12店舗の人材育成や新規開店などを手がける。 |
ビール造りを一生の仕事としようと考えたのは、20代最後の年だった。大学を中退し、フリーターを経て就職した広告会社で5年間働いた。次の仕事は死ぬまで続けられるものをと考え、50年後、60年後にもあるに違いないのは「食」に関わる仕事だろうと見定めた。
ひと口に食の仕事といっても種類は限りなくある。決め手となったのは、旅の途中で出合った栃木のマイクロブルワリー(小規模ビール醸造所)だった。海外では、小さな施設や家庭で造るクラフトビールが根づいている。日本でも1994年の酒税法改正で手造りビールが解禁されて以来、個性ある商品が各地で造られてきた。「これだ!」と思った。

ビールの原料の麦芽。二条大麦、小麦、オーツ麦などを発芽させ焙煎(ばいせん)させたもの。焙煎の度合いで色や味が変わる
|
では、ビール造りをどのように生業(なりわい)にしていけばよいのか。その方向性は、岡山市でクラフトビール「吉備土手下麦酒」を造る永原敬氏との出会いによって決まった。ビール業界は競争の激しい世界だから、既存の市場に参入しようとせず、新しいチャネルを作った方がよい──。そんな永原氏のアドバイスから、ビール醸造所と飲食店を組み合わせた「ブルワリーパブ」という業態にチャレンジすることを決めた。
「流通させるのではなく、その場所で飲んでもらうビール。鮮度で勝負するビール。それに懸けてみようと思いました」
株式会社麦酒企画の創業者であり、東京都内を中心にブルワリーパブを運営するSAKE-YA JAPANの取締役である能村夏丘氏はそう話す。
手造りビール屋さんをあらゆる街に
 |
ビールは、デンプンが糖に変わる「糖化」と、糖がアルコールと炭酸ガスに分解する「発酵」という天然の現象を利用して造る一種の自然食品である。基本的な原料は、水を除けば、二条大麦や小麦を発芽させた麦芽、ホップ、そして発酵をつかさどる酵母だけだ。
麦芽を破砕し湯に漬けると、麦の中のデンプンに麦芽の酵素が作用して、糖化が進む。そうしてできた甘い麦汁にホップを加え、煮沸して不純物を揮発させる。そこに酵母を加えることで発酵が進み、糖がアルコールと炭酸ガスに分解される。1週間から10日くらいの発酵期間ののちに、あらためて炭酸ガスを加え、冷却が済めば、客にサーブできる状態になる。
以上がビール造りの基本工程だ。ビールによっては、ここから数カ月の熟成期間を経て提供される場合もある。

左/麦芽をお湯に入れ、糖化させたところでホップを入れる
右/攪拌(かくはん)した後、煮沸して不純物を揮発させる |
これらの工程の要所要所で醸造家の腕が試されることになる。麦芽の選び方、湯の温度、煮沸時間、ホップの量と投入のタイミング、酵母の選択──。そのどれか一つにでもミスがあれば、おいしいビールはできない。その作業を最小限の施設で行い、最大限のクオリティを生み出す。それがクラフトビールの極意だ。
「最初はなかなかイメージ通りの味を出せませんでしたが、トライアル&エラーを繰り返して、何とかお客様に喜んでいただける質を実現することができました」
東京の中央線沿線の高円寺に出店したのは、「街のビール屋さん」というコンセプトが当初からあったからだ。
「クラフトビールには観光地の名産というイメージがありますが、街の中に手造りビール屋さんがあってもよいわけですよね。その街の人に来てもらって、その街の人に喜んでもらえる。そんな店をめざしました」

店舗に併設されている醸造場。小さなスペースですべての作業を完結させる
|
18坪のスペースの1号店はまたたく間に評判を呼び、「行列のできる店」となった。この業態の可能性に気づいた能村氏は、2号店、3号店の可能性を模索し始めた。
「東京には、駅ごとに立ち食いそば屋さんがあって、文化として定着しています。同じように、あらゆる街に手造りのビール屋さんがあったら、クラフトビールは文化になるはずです。そのためには、とりあえず100店舗は必要だろう。そう考えて、都内100店舗出店を当面の目標としました」
目的はクラフトビール文化を根づかせることであり、店は必ずしも直営である必要はない。スタッフが独立して店を作ってもよいし、開店支援だけをするケースもありうるだろう。それが、能村氏が掲げたビジョンだ。2010年12月の1号店の開店からおよそ12年。店舗数は現在12を数える。
醸造家の腕と個性がビールの質を決める
 |
ビール造りは「人作り」でもある。基本工程がシンプルなぶん、細かな工夫や作業の緻密さ、独自のアイデアがビールの質にダイレクトに反映される。つまり、「誰が造るか」によってビールのうまさは変わるということだ。だからこそ人を育てることが大切なのだと能村氏は言う。
最初の店は妻と2人で始めたが、2号店からはスタッフを雇い、現場で醸造家を育てていくことにした。「街のビール屋さん」の魅力は、それぞれの店によって異なる味やタイプのビールが飲めることだ。だからめざすのは、「均質なビール」ではなく、「個性があって、質において下振れしないビール」である。
「各店舗の醸造家が、品質をしっかり守りながら、自分の五感をフルに活かし、オリジナリティを発揮する。そうしてクオリティがどんどん上振れしていく。それが理想だと思っています」
 |
店舗ごとに個性ある醸造家がいて、それぞれが高いレベルで切磋琢磨(せっさたくま)すれば、たくましい醸造家集団が形成されるだろう。そして、その技や想いが人から人に継承されていけば、100年後にも顧客に愛してもらえるブルワリーパブがいろいろな街に根づいていくだろう。クラフトビールを文化にしていくための道筋を、能村氏はそんなふうに描いている。
社内で独自の育成プログラムを開発し、ライセンスを取得しなければ醸造ができない仕組みも作った。将来的には醸造家の学校を作ることも視野に入っている。
「カリキュラムによって基本的なことを学びながら、OJTで技術を磨き、さらに感性を鍛えて、自分にしか造れないビールを造る。そんな人が増えていくといいですよね」
「日本のビール」をいかに生み出していくか
ビール造りは舶来の文化であり、原料のほぼすべてが外国産である。その中で、「日本のビール」というアイデンティティをどう生み出していくか。それが現在の能村氏の課題だ。着目しているのは、日本古来の発酵技術である。
「日本人は、昔から味噌や醤油、酒などの発酵食品を造ってきました。酵母にも日本土着のものがたくさんあります。例えば、日本酒に使われている酒酵母をビールに使うという方法は大いにありうると思います。同じく日本酒造りに使われる麹(こうじ)を使ってみてもよいかもしれません。もちろん、そのまま使ったのではおいしいビールになりません。そこに工夫する面白さがあると思っています」
ものづくりの一番の面白さは、造り手の喜びがお客様の喜びになっていくこと──。そう能村氏は言う。自分が本当においしいと思えるビールを造り、それをたくさんの人たちがおいしいと思ってくれる。それこそがビール造りの価値なのだと。その価値の蓄積を文化として育てていくことを目標に、能村氏は今日も一杯のビールに向き合っている。
 |
5500人以上のオフィスワーカーが働く東京・西新宿の新宿野村ビルディング。その地下2階にある「ビール工房新宿」でお話を伺いました。高円寺から始まった「街のビール屋さん」も現在は12店舗まで拡大。このビール工房新宿も、5500人からなる「街」とその近隣の人々から愛されている街のビール屋さんの一つです。一年に一店舗のペースで店を増やすことができたのは、何よりも能村さんのビール作りへの徹底的なこだわりがあったからだということが、お話を伺っていてわかりました。それでも、作りたいのは「能村ビール」ではなく、仲間の醸造家たちの個性が反映された、みんなに愛されるビールなのだと能村さんは言います。目標の100店舗出店はそう遠い未来ではないかもしれません。