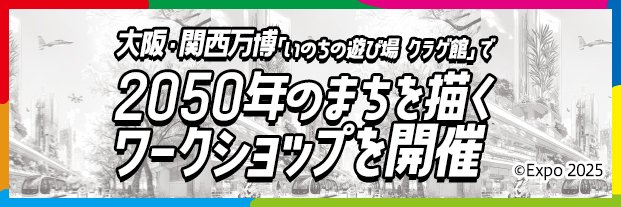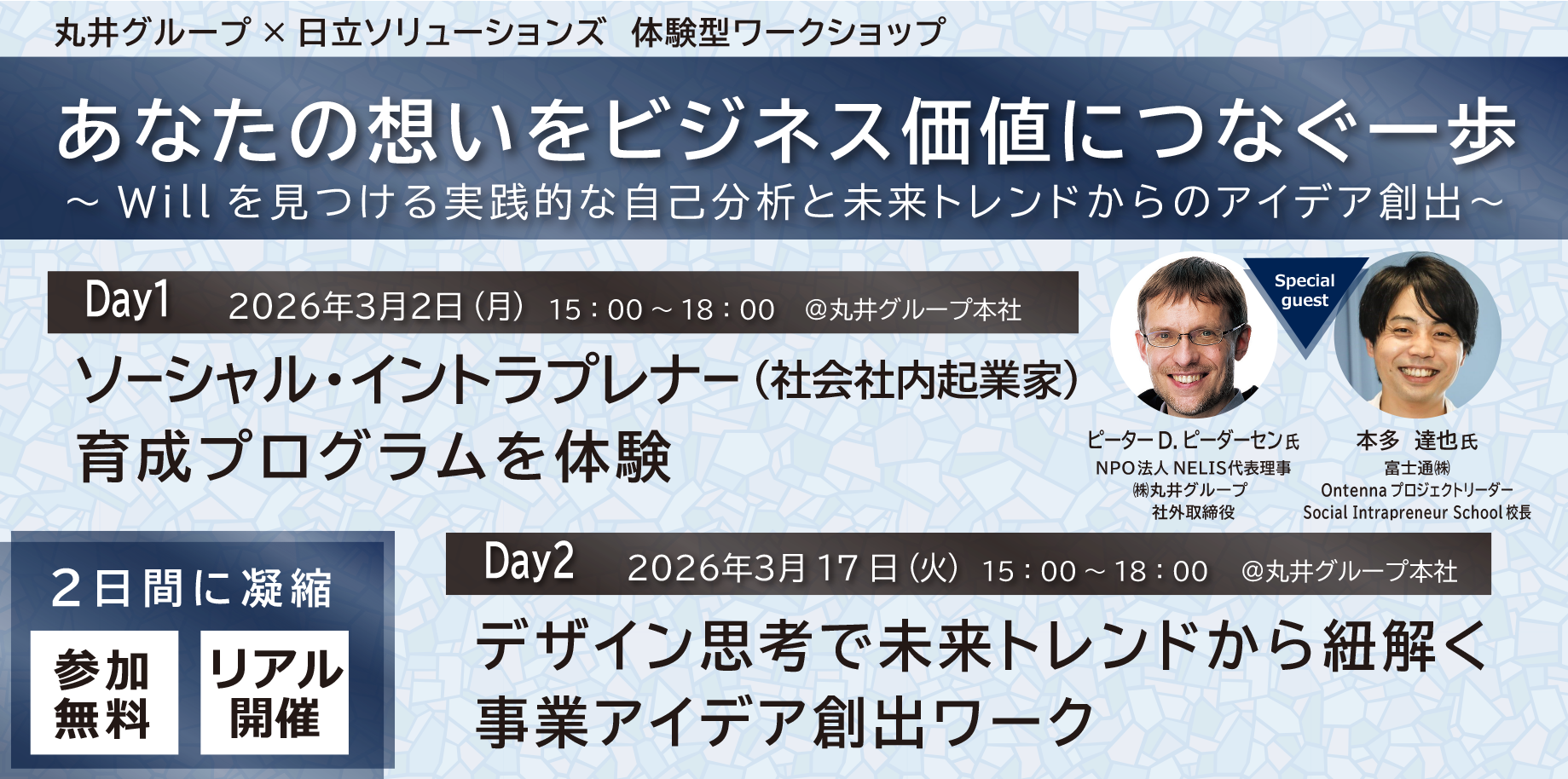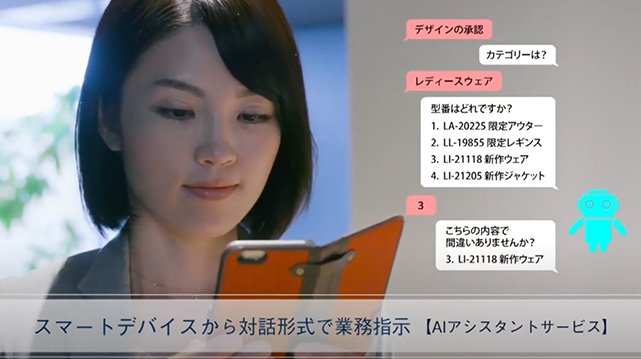※本記事は2020年6月に掲載されたものです
「目が見えない」ことはその人を構成する要素の1つにすぎない
 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授 |
2015年に発売された『目の見えない人は世界をどう見ているのか』は、視覚障がいについて全く新しい方向から掘り下げた画期的な本だった。社会学、福祉学、医学、哲学といった既存の知の枠組みに依拠するのではなく、年齢も職業も、視覚を失った時期も異なる4人の障がい者と対話し、共に行動する中から「目が見えない」ことの意味を根気強く考察した内容が大きな話題を呼び、今日まで読者の絶えないロングセラーとなった。
「視覚障がいに対する理解があらかじめあったわけではないので、話をするたびに大きな驚きがありました」と著者である伊藤亜紗氏は振り返る。特に印象に残っているのは、本の中でも紹介されている「大岡山」の逸話だという。
「私が勤務している大学に行くには、大岡山駅から坂を上らなければならないのですが、一緒に歩いていた目の見えない方が、"大岡山って、名前の通り山なんですね"って言うんです。そんなことを考えたこともなかったのでびっくりしました」
目が見える人にとって、駅からキャンパスまでの道は「坂」として認識される。しかし、目が見えないその人は、勾配を含めた地形をイメージの中で俯瞰して、その全体を「山」として捉えていた。
「目が見えると、目の前の坂道しか見ないから、むしろ視野は限定されるわけです。見えることによって何かが増えているわけじゃないんだ。むしろ、見えないことで豊かになる部分もあるんだ。そんなことに気づかせてもらえました」
「ままならなさ」から生まれる創造力
 |
子どもの頃から生き物が好きで、自分以外の存在の体に興味があった。自分の体は偶然与えられたもので、自分で選び取ったものではない。それを引き受けながら私たちは生きている。もし、自分の体が他の人の体になったらどうなるのだろう。もし、虫や動物の体になったら──。自身「妄想」と呼ぶその想像力が、彼女を生物学の世界に導いた。しかし、生き物や自然事象を細かに分類して捉える生物学の方法になじめず、大学2年で「文転」し、美学を専攻することにした。
「美学が面白いと思ったのは、言葉の限界を自覚した学問だからです。例えば哲学は、世の中の様々なことを概念によって、つまり言葉によって説明することをめざします。一方、美学はこの世には言葉にはできないことがあって、すべてを明確に説明することはできないと考えます。そのせめぎ合いのようなものに引かれたのだと思います」
自分の体は自分のものであるのにもかかわらず、いつも思い通りになるわけではない。同様に、言葉によってすべてのものを自在に説明できるわけではない。その「ままならなさ」が関心の中心にある点において、彼女のモチーフは幼少時から一貫している。障がいとはいわば「ままならなさ」の別称であり、ままならないが故に、そこに工夫や技術が生まれ、人や社会との新しい関わり合いが生まれる。そう考えれば、障がいの本質を追究することは、誰もが持つ「ままならなさ」の本質を追究することに他ならない。
「思い通りにならないことがあって、それを何とかしようとするところにクリエーティビティーが生まれる。私はそう思うんです」
伊藤氏が障がい者スポーツに強い関心を寄せているのも、工夫やクリエーティビティーが際立った世界だからだ。特にプロの障がい者アスリートの場合は、健常者のアスリートと同じように、「勝つためにいかに効率を上げるか」という発想で様々な工夫を行う。
「例えば陸上の三段跳びの場合、選手はコーチの声に合わせて跳ぶ訓練を繰り返します。効率を上げるために、タイミングの決定をアウトソーシングしているわけです。特定の役割を他の人に委託することで、競技者は"走る"ことと"跳躍する"ことに集中できるようになります」
 |
選手はサポートしてくれる人に依存しているわけだが、考えてみれば、これは障がい者スポーツに特有のことではない。障がいのないアスリートもまた、コーチに、トレーナーに、チームメンバーに、あるいは家族に依存している。障がいがある場合、単にその依存の仕方が変わり、依存先がいくぶん増えるにすぎない。その「依存の方法」に健常者スポーツとは異なる工夫や創造力が発揮されるのだと伊藤氏は言う。
伊藤氏はまた、ある競技が障がい者向けにアレンジされることによって、全く別の競技になることの面白さを指摘する。
「100m走は、見える人にとってはゴールまで最短の時間で走る競技ですが、見えない人にとっては、伴走者と2人でゴールに向かって真っすぐ走る競技になります。あらゆるスポーツは、ルールによってハードルを設定していますよね。手を使ってはいけないとか、ラインを越えてはいけないとか。障がいがあるということは、そのハードルが1つ増えるということです。その結果、障がい者向けの競技は、そうではない競技と"頑張るポイント"が変わります。そこを見ることが、障がい者スポーツを楽しむ方法だと思います」
「当たり前」を柔らかくほぐす
 |
1人で行う芸、いわゆるピン芸のコンテスト「R-1ぐらんぷり」で、視覚障がい者の濱田祐太郎氏が優勝したのは2018年のことだった。「目が見えないのに、思わず二度見してしまいました」というフレーズが彼の持ちネタの1つだ。しかし、このネタに笑いで応えることは必ずしも簡単ではない。もし彼が芸人ではなく、1対1の場面でこの言葉が発せられたとしたら、多くの人は笑っていいのかどうか逡巡するだろう。そんな経験は伊藤氏にもあった。
「目が見えない人が言う自虐ネタを聞いて、最初はどう反応していいのか分かりませんでした。どうして私は笑わないんだろう。そう考えて、どこかで私は障がい者をかわいそうな人だと思っている、距離を取らなければならないと思っていると気づきました」
重要なのは「気づいた」ということだ。コミュニケーションにおいて大事なのは「失敗」だというのが、伊藤氏の持論である。失敗の経験があるからこそ、人は学ぶことができるのだと。
「健常者は社会の中のマジョリティーなので、自分の感覚が正しいと思いがちです。その思い込みで障がい者と接すると、時に善意の押しつけになったり、同情になったりしてしまいます。そのような非対称的なコミュニケーションは、往々にして失敗することになります。でも、その失敗からより良いコミュニケーションの方法を学んでいけばいいと思うんです」
失敗も学びも接する相手の数だけあり得る。1人として同じ障がい者はいないからだ。1人として同じ健常者がいないのと同じように。
「目が見えない人にとって、"目が見えない"ということは、その人を構成する要素の1つにすぎません。その人の中にはそれ以外の様々な要素があって、それがいろいろな人につながる"リンク"になっているわけです。リンクを限定するような接し方をされるのは、誰にとっても苦しいことだと思います」
その人がどのようなリンクを持っているかは、すぐに分かることではない。どのようなリンクがあるかを知るために必要なのは、いわば「柔らかいコミュニケーション」である。伊藤氏は大学で美術史を教えている。アートの重要な役割は「ほぐすこと」なのだと彼女は言う。当たり前だとされているものの見方や考え方を、マッサージをするようにほぐして、その「こわばり」を柔らかくしてあげること。それはまた、人間同士のコミュニケーションの基本でもある。
「障がいってこういうことだよね。女性ってこういうものだよね。生き物ってこうだよね──。そういう固定された考え方がどこにでもあると思うんです。それを一つひとつほぐしていくような研究活動をこれからも続けていきたいと思っています」
 |
伊藤先生の勤務先である東京工業大学がある大岡山近くのスタジオでインタビューと撮影を行いました。先生は著書のイメージ通りのとても知的な女性で、こちらの質問の意図を即座に理解し、さらにこちらの意図を超えた内容にまで言及してくださるインテリジェンスに感銘を受けました。先生の研究は独自すぎて、日本のアカデミズムの世界に居場所を見つけるのはなかなか難しいとのことでしたが、だからこそ価値があると思います。これからも、他の人にはない視点で研究活動を続けていってください。