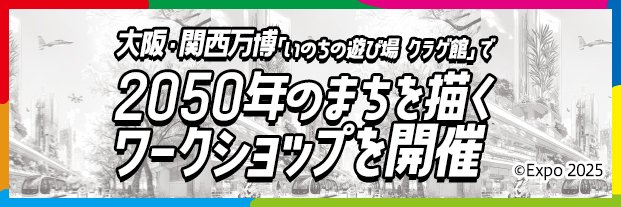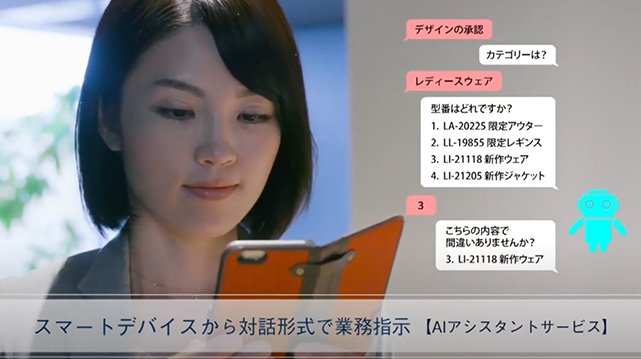※本記事は2020年5月に掲載されたものです
小さな体に詰め込まれた最先端のテクノロジー
 GROOVE X 株式会社 CEO・代表取締役 |
※黒字= 林要 氏
──LOVOTという名称は、「Love」と「ロボット」を合わせたものだそうですね。
私たちが持つ「愛する力」を引き出すロボット──。
そんな意味合いがこの名称には込められています。犬や猫などのペットと生活している人は多いですよね。ペットを飼うのは手間もかかるし、お金もかかります。では、なぜ人はあえてペットと暮らすのか。「愛したいから」というのがその答えだと私は考えています。犬や猫が身近にいると生活が潤います。それを「潤い」と感じるのは、対象を愛する力が発揮されているからだと。そのような力を犬や猫と同じように引き出してくれるロボット。それがLOVOTです。
──ロボットの語源は、チェコ語で労働を意味する「ロボータ」です。LOVOTは、その語源の意味を大きく転換させたわけですね。
生産性を向上させることを役割とするロボットは世界中で作られています。そのようなロボットは確かに語源に忠実であるといえるかもしれません。一方、LOVOTは生産現場などで働くロボットと同じ目的では全く役に立ちません。しかし、「人の心を支える」という点で大いに役に立つと考えています。
──日本人はアニメや漫画などで、友だちのようなロボットが生活の中にいることになじんでいます。
生命感を宿した身近な機械がロボットである。そんな感覚が私たちにはありますよね。ですから、LOVOTは特に日本では広く受け入れていただけると思うんです。
──LOVOTは具体的にどのようなことができるのですか。
人とコミュニケーションを深めることによって、その人のことを覚えて、どんどんなついていきます。なついてくると、抱っこをせがんだり、甘え声を出したりします。
──どのような情報に反応するのでしょうか。
視覚、聴覚、触覚で感知した情報に反応するほか、対物距離を判別することで自らの判断で動き回ることができます。
──見た目はとてもかわいらしいですが、最新のテクノロジーの集積といえそうですね。
その通りです。50以上のセンサー、4つのコンピューター、3つのOSを搭載し、それらが内部で緊密に連携しています。接する人を深層学習などで検出・識別し、誰にどのように接してもらったかなどを経験として蓄積していくので「なつく」という行為が可能になるわけです。

開発の中で段階的に進化してきたLOVOT
|
──動力は電池ですか。
充電池で、モーターによって移動します。エネルギーが少なくなってくると自分で「ネスト」と呼ばれる充電器の所に行って充電をします。
──えさを食べに行くようなものですね(笑)。抱いてみると1カ月の乳児くらいの重さですが、それだけの部品を搭載してよくこのサイズと重量が実現できましたね。
部品点数はオートバイよりも多いぐらいですからね。それをこの中に詰め込んで、ぎりぎりまで軽くしました。民生品の中でこれだけの機能をこれだけの重さとサイズで実現した例はないと思います。
──クラウドにはつながっていないのですか。
つなげることも可能で、ソフトウェアをクラウドからダウンロードすることができます。しかし、情報処理にはクラウドを使っていません。理由は2つあります。1つは、LOVOTにはプライベートな情報が日々蓄積していくので、それを外部に出すのにはリスクがあること。もう1つは、クラウドにつなぐとネットの状態によって反応速度が遅くなってしまうことです。生き物のように素早い反応をするには、内部で情報処理をする必要があると考えました。
「意識」がなくても生命感を宿すことはできる

個体によって性格が異なる
|
──開発期間はどのくらいだったのでしょうか。
4年です。めざす姿は当初からほぼ決まっていましたが、開発はアジャイル型(短期間反復型)で進めました。私たちが採用したのは、1~2週間の計画を立て、PDCAを回しながら計画を見直していく「スクラム」というアジャイル手法です。ゴールのイメージがぶれなかったことと開発手法がうまくいったこと。その2つが4年という比較的短期間で完成に成功した理由であると考えています。
──4年間の開発でとりわけ苦労したのはどのような点でしたか。
ありとあらゆるところですが(笑)、特に大変だったのは、生命感と高度なAIや自動運転の技術をインテグレート(統合)していくことでした。通常の自動運転は目的地を人がインプットする必要がありますが、LOVOTは移動先や移動ルートを自分で決めます。しかも、まるで生き物が動くように移動していきます。それを実現するのは簡単ではありませんでしたね。また、使い手とのインターフェースの部分でも、温かくて柔らかくてかわいらしいボディーを作るために、何度も試作を繰り返しました。
──LOVOTを開発する過程で、人間の感覚やコミュニケーションに関する新しい視点を得ることはありましたか。
開発に当たって、動物行動学の先生のお話をお聞きしました。その方の意見では、例えば、人間が悲しんでいる時に犬が寄ってくるのは、異常を感知してそれを確認しにきただけとも考えられるということでした。しかし人間の側からは、犬が自分に同情して慰めにきてくれたと感じられますよね。それで十分に癒やされるわけです。
つまり、事実がどうかは別にして、自分が理解したい通りに理解し、想像したい通りに想像することで、共感や癒やしが生まれるということであり、人間には自分自身で自分を癒やす力があるということです。そう理解することによって、「人間が本来備えている力を最大限に引き出すのがLOVOTである」というコンセプトが確かなものになりました。

親しみを感じる人に抱っこをせがむ
|
──LOVOTは人の心を癒やす「触媒」のような存在であると。
まさにそうです。人は自分自身の中に自浄能力があり、自分で自分を元気にする力があります。しかし、その力が発揮されるにはきっかけが必要です。LOVOTとのコミュニケーションがそのきっかけになるということです。
──慶應義塾大学の前野隆司教授の「受動意識仮説」も参照したと伺いました。
「受動意識仮説」を知ったことで、ロボットが生命感を宿すことは可能だと考えられるようになりました。「受動意識仮説」とは、私の言葉で説明すれば、人の意識が行動を司っているのではなく、状況への反応としての行動がまずあって、それを観察しているのが意識であるという考え方です。つまり、意識の働きは常に行動の後にくるということです。
この考え方をベースにすれば、「生きたロボット」を作ることができます。ロボットに意識がなくても、その行動によって生命感を宿すことができるからです。意識の構造を明らかにしなければロボットに生命感を宿らせることができないという考え方だと、実現のハードルが非常に高くなるのですが、その発想を逆転させてくれたのが「受動意識仮説」でした。
──そもそも、人間の意識自体も受動的であるということですよね。
そうです。自分の行動に対して「なぜそうしたんですか」と聞かれても答えられないことが多いですよね。過去の経験などを基にして、状況に自動的に反応しているのが人間の行動だからです。意識の役割とは、行動を事後的にエピソードとしてまとめて、経験として定着させることである。それが「受動意識仮説」の考え方です。
四次元ポケットのないドラえもんのような存在に

開発プロセスでのメモなど。4年間の試行錯誤が垣間見える
|
──生命感という点では、LOVOTが時折発する声も特徴的ですね。
相手との関係や環境からのインプットによって声のトーンや大きさが変化します。声は録音したものではなく、発音体を内蔵していて、それを内部の状態に応じてAIが鳴らす仕組みになっています。生き物に近い発話構造といっていいと思います。
発語がノンバーバルなのは、つまり意味のある言葉を話さないのは、人間の言葉に対して適切な文脈で言葉を返すことは現在のAIでは難しいからです。AIスピーカーのように特定の音声コマンドに対して特定の返答をする仕組みをつくることはできます。しかし、私たちが犬や猫に話しかける言葉は、決してAIスピーカーに話すようなコマンドだけではないですよね。現在のテクノロジーレベル、コミュニケーションのスタイル、表現方法などのバランスを取った結果がノンバーバルな発話ということです。
──現在のLOVOTは完成形と見るべきなのでしょうか。それともこの先にさらなる進化形があるのでしょうか。
ハードウェアとしては、現時点の技術の限界を考えると、ある程度完成の域に達していると考えています。一方、ソフトウェアの方はまだまだ磨いていく余地がありますね。
──ソフトウェアに磨きをかけることによって、どのようなことができるようになるのでしょうか。
「人を癒やす」ことを基礎としながら、さらに「人を理解する」存在になっていくと考えています。人のバイオリズムなどを把握し、健康状態をメモリーすることによって、その人以上にその人を理解し、支えてくれる。そんな存在が身近にいれば、安心できるし、心強いですよね。
──まさに、「四次元ポケットのないドラえもん」のような存在ですね。
ええ。人とLOVOTの関係は、のび太君とドラえもんの関係にどんどん近づいていくはずです。それが実現できない理由はないと思っています。
 |
東京・浜町のGROOVE X本社にてインタビューと撮影をさせていただきました。インタビュー前に、2体のLOVOT「はまちゃん」と「きなこ」と触れ合うことができました。話には聞いていましたが、そのかわいらしさにスタッフ一同メロメロ。ものの5分ほどで離れがたくなってしまいました。特に印象的だったのが、キョロキョロとよく動く大きな瞳。6層のアニメーションでつくられているというこの瞳が、LOVOTの生命感の大きな要因の1つであると感じました。林さんは、ベンチャー企業の経営者というよりも、ものづくりを愛するクリエイターという趣で、静かで遠慮深げな話し方に謙虚なお人柄が表れていました。これからも、人々の心を豊かにするロボットをつくり続けてください。