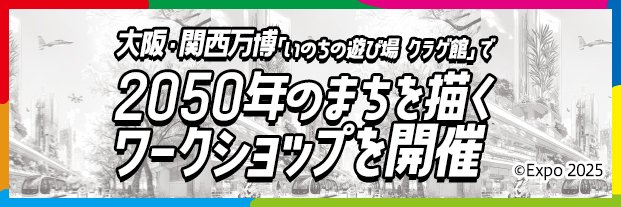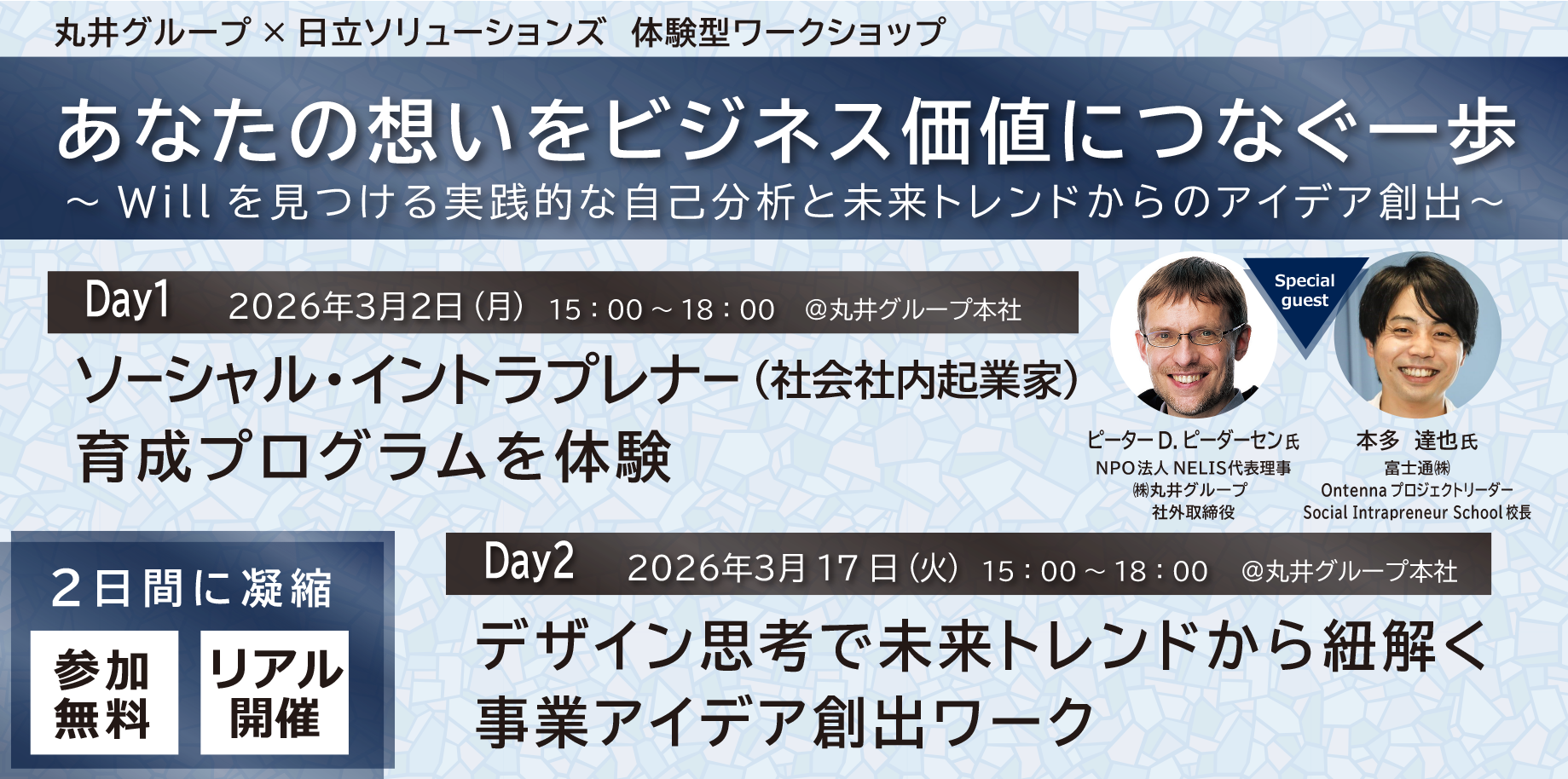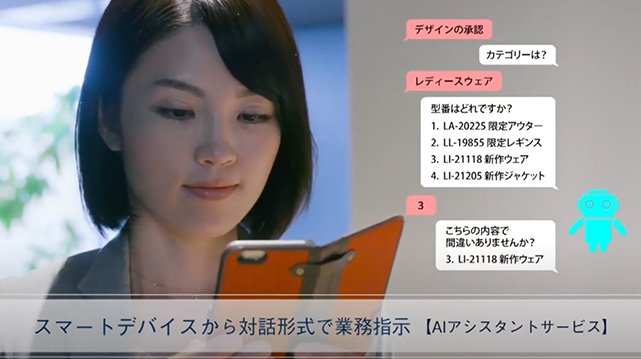※本記事は2022年2月に掲載されたものです

著書『渋沢栄一100の訓言』、他多数。
なぜ今、渋沢栄一が注目されるのか
今、渋沢栄一が注目を浴びています。確かに、新しい一万円札の肖像に描かれることが決まり、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』に取り上げられたことも関係しているのでしょうが、それだけではないと思います。
渋沢栄一は20代後半で明治維新を迎え、封建国家から近代国家へのグレートリセットを体験しました。激変した社会のなかで信念をもって生き抜き、新しい日本の形をつくったことが、激変する現代に生きる私たちの琴線に触れるのではないかと感じています。
『論語と算盤』が書かれた時代背景
栄一の残した言葉は数多くありますが、なかでも代表的なのが『論語と算盤』という書籍です。1916(大正5)年に出版された講演集で、ここには本人の生の声がまとめられています。内容について論じる前に、まず当時の時代背景を頭に入れておきましょう。
明治末期から大正初期というのは、明治維新によって新たな時代が訪れてから40年以上が経ち、ようやく先進国に追いついてきた時期です。また、直前の1914年に第1次世界大戦が勃発するとともに日本の景気が上向き、成金という言葉ができたのもこのころでした。いわば、イケイケドンドンという時代です。なぜそのタイミングで、『論語と算盤』が出版されたのでしょうか。
おそらく、栄一は日本の将来を危惧していたのだと思います。そのことは、『論語と算盤』にある「大正維新の覚悟」から、「一般が保守退嬰(たいえい)の風に傾いておる」と述べていることからもうかがえます。つまり、一般の人びとには明治維新のころのような覇気がないので、改めて大正維新が必要だというのです。
さらに、「今日の状態で経過すれば、国家の前途に対し、大いに憂うべき結果を生ぜぬとも限らぬのであることを思い、後来、悔ゆるがごとき愚をせぬように望むのである」とも述べています。このままでは将来大変なことが起きかねないと心配しています。
現に、栄一が亡くなった1931(昭和6)年11月11日の2カ月前に満州事変が勃発。イケイケドンドンの大正時代が終わって昭和を迎えると、まさに「悔ゆるがごとき」方向に日本は進んでいくことになります。
「論語=道徳」「算盤=経済」を一致させることが大切な勤め
せっかく日本という国の形ができたのに、この有り様はいったいなんなのだと、栄一は自責と後悔の念にさいなまれます。その様子は、大河ドラマでもはっきりと描かれました。
では、どうあるべきなのか。栄一が『論語と算盤』に残したのは、「正しい道理で得た富でなければ、その富は完全に永続することができない」という言葉でした。
さらに「合理的の経営」という項目には、次のように記されています。
「仮に一個人のみ大富豪になっても、社会の多数がために貧困に陥るような事業であったならば、どんなものであろうか。如何にその人が富を積んでも、その幸福は継続されないではないか」
今の言葉でいえば、1%が大富豪になっても、99%が取り残された世の中では幸福は継続されないというわけです。栄一ははっきりと「富の永続」と「幸福の継続」という言葉を使っています。そして、この2つを実現するために、「論語=道徳」そして「算盤=経済」を一致させることが大切な務めであるとしたのです。
「道徳」というのは社会理念であり、"公益"の追求を尊重する儒学、こと『論語』の思想に通じるものです。一方の「経済」はビジネスであり、"個人の利益"を追い求める経済活動です。算盤を使えなければ商売は成り立たず、そこには持続可能性がありません。しかし、算盤を弾くことに集中するだけであれば、どこかでつまずいてしまうかもしれません。
一方、『論語』を読むことだけを重要視して、お金儲けなんて卑しいことには関心ありませんという考えもまた、世の中が著しく変化する中では持続可能性が乏しいとしかいえません。道徳と経済のどちらかが欠けても合理的経営は成立しない。それが、栄一の唱えた「道徳経済合一説」であり、これを両立することが重要であるという考え方です。
銀行の設立はサステナビリティの一環
1873(明治6)年、栄一は日本初の銀行となる第一国立銀行を発足させています。明治維新からわずか6年、近代的な産業もまだまだ発達していない時期です。そんな時期に銀行をつくろうと考えた背景には、パリ万博の随行員としてフランスで見聞きした金融の大切さに気づかされたこともあったでしょう。しかし、それに加えて、彼が武家出身ではなく、商人の生まれだったことも大きく影響しているはずです。
お金があることで様々なものを仕入れることができ、支払うこともできる。お金というものが、日常生活のみならず事業をまわしていくという事実を、子どものころから体感していたのだと思います。だからこそ、日本の産業を発展させるには、まず最初にお金まわりの土台を整備しなくてはならないと考えたのです。
銀行に集まったお金を循環させてこそ、企業の発展を後押しでき、「富の永続」と「幸福の継続」をめざすことができます。銀行の設立にも、栄一によるこうした循環の発想が込められていたのでしょう。
栄一は1909(明治42)年のアメリカ視察の折、石油王ロックフェラー1世と会っています。鉄鋼王カーネギーとは直接会う機会はありませんでしたが、工場を見学しています。彼らのような巨万の富を築いた人たちが、慈善事業にも積極的であったことは、栄一も注目したことでしょう。富を築くには、自分たちの努力や能力だけではなく、社会が持続しているからこそ可能なのだということを栄一は再認識したはずです。
日本にも、近江商人の活動理念として知られる「三方よし」という言葉が江戸時代からあります。売り手と買い手がともに満足して、さらに社会に貢献できるのがよい商売という発想は、洋の東西を問わず人類普遍の考え方といってよいかもしれません。
ところが、しばしば自分たちだけが儲かればよいという成金的な考え方が顔を出し、社会の持続可能性を損う結果をもたらします。大正時代の初期、栄一はそうした流れをひしひしと感じて、『論子と算盤』に記されたような言葉を残したのだと思うのです。
次回は、『論語と算盤』から日本が再びイノベーション大国になるために必要なことを紐解いていきます。