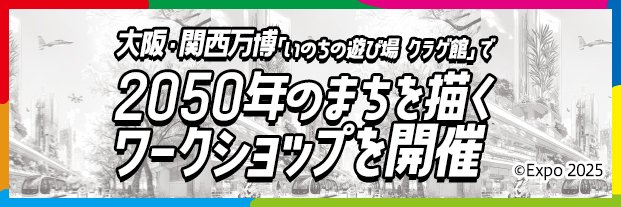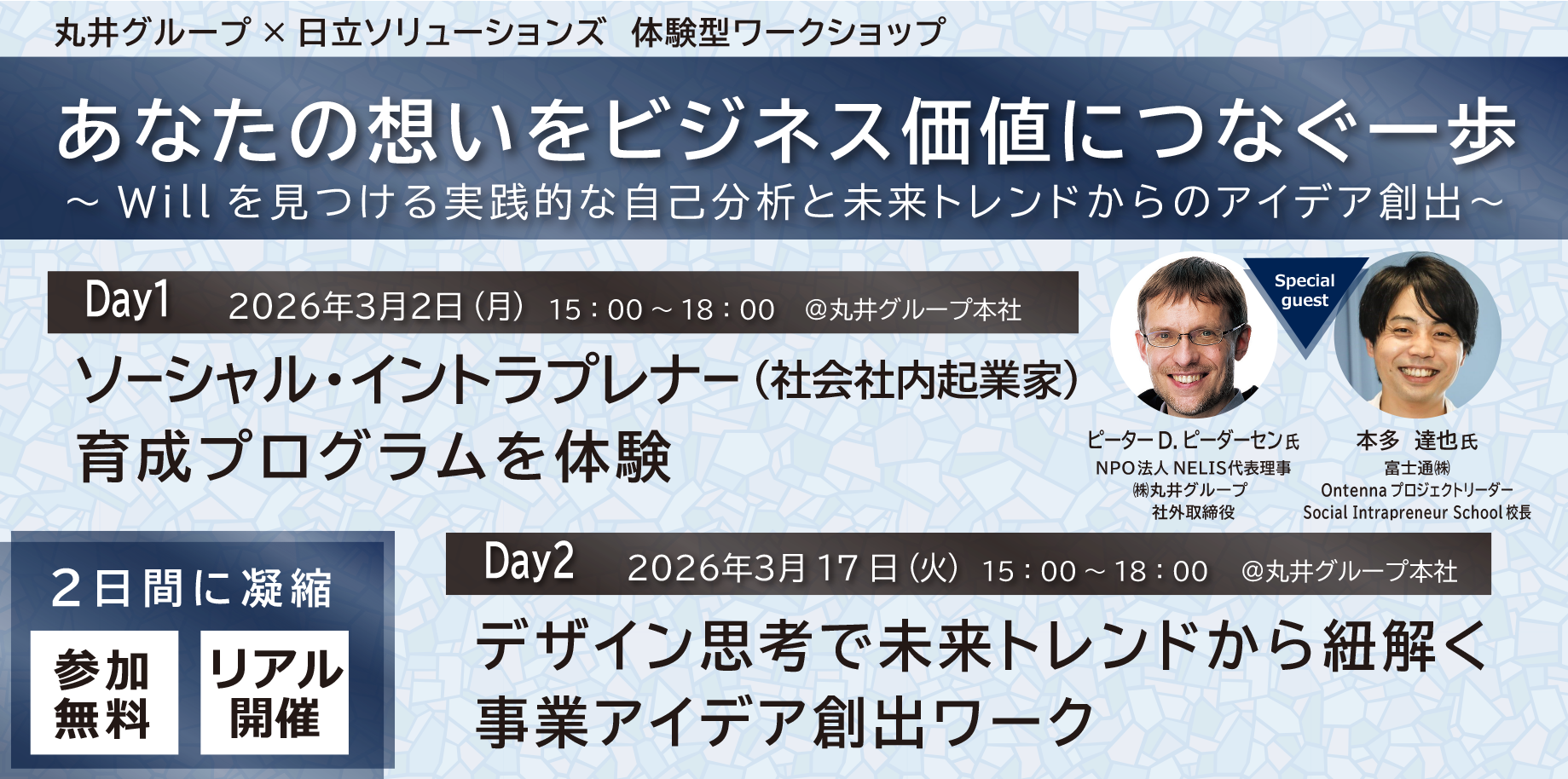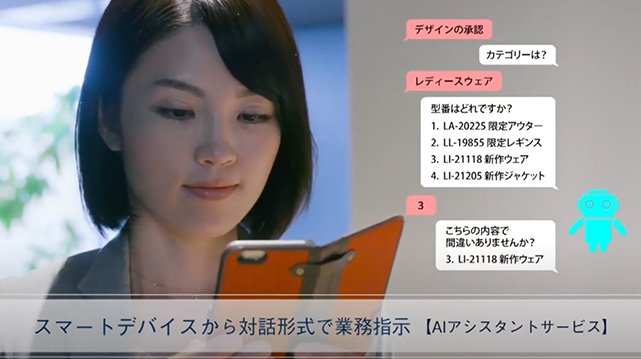蒲生氏郷が築いた豊臣政権の巨大シンボル

会津若松城
|
磐梯山を望む地にそびえる会津若松城。正式には鶴ヶ城、もしくは若松城と呼ばれる。明治の新政府軍と旧幕府軍が激しい攻防を繰り広げた会津戦争の舞台のイメージが強いが、その歴史は古い。時は南北朝時代、南奥州に一大勢力を誇っていた蘆名直盛(あしななおもり)がこの地に城を築いたという。元中元年/至徳元年(1384年)のことである。以来、黒川城と呼ばれ、蘆名氏が本拠地としてきた。
転機が訪れたのは、天正17年(1589年)。東北で勢力を拡張する伊達政宗がこの城を攻め、会津を自分の領地とした。天下統一に向けて動いていた豊臣秀吉は、この行動を諌め、政宗が小田原の北条攻めに非協力的だったこともあり、会津を没収する。かわりに領主となったのが、伊勢松坂を治めていた蒲生氏郷(がもううじさと)である。文禄元年(1592年)のことだった。
並外れた実力を備えながらも、経営トップの交代によって、本部のある中央から離れた部署に配属されることはビジネスではよくある。熾烈な権力争いが渦巻く戦国の世では、そうした人事政策が権力を強化する有効な手段となっていた。会津に「配置換え」となった蒲生氏郷は、そうしたパワーゲームに巻き込まれた典型ともいえる武将だ。織田信長の娘婿であり、重臣だった氏郷は、信長の後継者と目されていたほど才能に恵まれた逸材だった。だが、信長の死後に覇権を握った秀吉によって大きく運命が変わる。
蒲生氏郷は豊臣秀吉に信頼されていた反面、その才能を恐れるあまり、会津に遠ざけられたという説もある。真偽のほどは定かではないが、こんな逸話が残されている。秀吉が家臣たちに「100万の大軍の采配をさせたい武将は誰か」と問いかけたとき、家臣たちが徳川家康や前田利家の名を挙げるなか、秀吉だけが蒲生氏郷だと答えたという。また秀吉は会津への移封を決めるなかで「蒲生氏郷を上方に置いておくわけにはいかない」と側近にもらしたと伝えられる。

蒲生家紋 「立鶴紋」
|
鶴ヶ城という名の由来は、白亜の壁に赤瓦の姿が鶴を想起させるからと思われがちだがそうではない。「鶴」は蒲生氏の家紋「立鶴紋(たちづるもん)」によるものである。そもそも氏郷の築いた城は白ではなかった。それは漆黒に金箔をあしらった豊臣政権のシンボル「黒い城」であり、しかも七重の天守をもつ豪壮な城だった。氏郷の築いた城は天災で傾いてしまい、蒲生氏のあとに城主になった加藤嘉明と子の明成によって天守が改修されている。現在の会津若松城は、この加藤氏の築いた天守を復元したもので「秀吉の黒い城」の面影はない。
先端をいく技術と文化でイノベーション
豊臣秀吉が蒲生氏郷を会津に移封した狙いは大きく二つあった。一つは東北を拠点に勢いを増していた伊達政宗を封じるためである。もう一つは関東に移封された徳川家康を監視するためである。会津は地政学的に極めて重要な地であり、よほど能力の高い武将でない限り、ここを任せることはできないと秀吉は考えていた。それが氏郷だったのだ。自分の地位を脅かす存在になるかもしれない男ゆえに遠ざけたい。しかし、武将としての力量は捨てがたく、天下統一を推し進めるためにこの男は欠かせない。そんなアンビバレントな感情が秀吉にあったといわれている。
伊勢松阪12万石から会津42万石への大抜擢である。その後、さらに92万石に加増され、氏郷は前田利家の加賀百万石に匹敵する有力大名となったのである。
蒲生氏郷は近江の生まれで9歳にして織田信長の人質となり、信長の小姓として過ごした。信長にその器量を見込まれ、信長の次女をめとり娘婿となる。この信長のそばで仕えた経験が氏郷に大きな影響を与えた。海外に目を向けていた信長からグローバルな視野を学ぶ。ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスとも面識があり、西洋の情報を得たという。蒲生家の当主となってからはロルテスというイタリア人を家臣に加え、ローマと通商をしていたという記録も残されている。
本能寺の変のときは、安土城にいた濃姫をはじめとする織田家の一族を、自分の城である近江の日野城にかくまい、明智光秀との対決姿勢を明確に示した。信長の死後は豊臣秀吉に従い、多くの武功をあげ、伊勢松坂の領主となる。
若くして信長のもとで領国経営を学んできた氏郷は、武勇に優れているだけでなく、第一級の教養人であった。近江、伊勢という古くから優れた商人を輩出していた国を本拠地としていたため、商業や経済にも明るかった。また千利休の高弟として知られる茶人であり、レオンという洗礼名をもつクリスチャンでもあった。文武両道というだけでなく、最先端の洗練された都市文化をも身につけたパワーエリートだったといえる。
それだけに会津に移封になったときは「都落ち」のショックで落胆を隠さなかったという。だが氏郷は気持ちを切り替え、会津を発展させることが将来につながると考えた。

7層の黒塗りの天守閣「黒川城」想像模型
|
蒲生氏郷が会津に来たときの黒川城は、土塁と堀をめぐらした中世スタイルの城館であり、城下町の整備もなされていなかった。この地に近世城郭の会津若松城を築くとともに、町を新たにつくり、さまざまなイノベーションを起こしたのが氏郷だ。
氏郷の先進性は人材活用にも見られた。会津移封の条件として氏郷は、戦乱によって主君を失った家臣など、奉公先のない武将たちを採用したいと秀吉に願い出て認められる。ここから多くの優秀な家臣を得たという。また氏郷自らが風呂を焚いて家臣を労ったり、92万石に加増されたときは家臣の禄高を家臣自身に決めさせたという。こうしたふるまいは氏郷への信頼を深め、家臣の心をつかみ、家臣団の強化に結びついたという。現代のビジネスでは、従業員満足は重要な企業戦略とされるが、氏郷は戦国の世においてすでに実践していたのである。
氏郷のレガシーを受け継いだ会津松平家
氏郷は近世城郭の最高峰といわれた信長の安土城の築城にも関わった人である。現在の会津若松城は5層だが、蒲生氏郷の築いた城は7層で、姫路城に匹敵する壮麗さだったという。日本屈指の巨大な天守が、この会津の地にそびえていたのだ。現在も残る天守台は氏郷が築いたものである。氏郷の生地の近江は、穴太衆(あのうしゅう)と呼ばれる石垣施工のプロフェッショナル集団の本拠地であり、そのお家芸、自然の石を組み上げる「野面積(のづらづみ)」が用いられている。大規模な堀も壮観だ。西洋の事情に通じていた氏郷は、これからは銃ではなく砲弾の飛び交う戦闘が主流になると考え、幅40メートルという幅の広い堀もめぐらしている。
さらに城下は惣構え(そうがまえ)と呼ばれる堀と土塁による防御線を設け、郭内を家臣、郭外を町人の居住地とした。さらに商人と職人の居住地を分けることで、情報や技術の交換が活発になる協創の場をつくりだし、商工業の発展を促す土壌をつくった。
商人と職人は氏郷の生地である近江や前任地の松坂からもわざわざ呼び寄せている。会津の地に、会津塗などの工芸や酒造などの産業が盛んになったのは、氏郷の功績だといわれている。

茶室「麟閣」
|
また氏郷は千利休の高弟、利休七哲(しちてつ)の筆頭であったことから、秀吉の命で利休が切腹したあと、利休の娘婿である千少庵を会津にかくまっている。城内の茶室「麟閣(りんかく)」は、その少庵の作と伝えられる。氏郷の尽力もあり、少庵は京都に戻って茶道の宗家、千家を興すことができた。その歴史にちなみ、城内ではいまも定期的に大茶会が開かれている。
こうした遺産を受け継いだのが、会津松平家である。3代将軍・徳川家光の異母弟、保科正之(ほしなまさゆき)が会津藩主となって以来、御三家に次ぐ家門をもつ名門として幕末まで命脈を保つことになる。
とりわけ家光の信頼が厚く、4代将軍・徳川綱吉の後見役も務め、江戸初期を代表する名君の一人と謳われている。有名なエピソードとして次のような話がある。江戸に大きな火事があり、江戸城の天守も焼失する。
天守の再建が進められるなかで、街の復興を指揮していた正之は工事を中止させる。「城の天守は織田信長公の岐阜城がはじまりで、本来の城にどうしても必要なものではない。それよりも街の復興や町民の救済に財を投入すべきである」というのがその理由だ。以来、江戸城に天守が築かれることはなかった。
江戸で政権の中枢にいたため、正之は会津に滞在する期間は短かったが、困窮した農民に蔵米を貸し出す「社倉制」を導入するなど善政を行った。「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在」で始まる有名な「会津家訓十五箇条」を残したのも彼の功績である。
ビジネスでいえば、創業者語録のようなもので、会津藩士とは何かというアイデンティティの支柱となっている。
さらに会津藩士の子弟は「ならぬことはならぬものです」で締めくくられる「什(じゅう)の掟」を教え込まれる。のちに開設された会津藩の藩校である日新館では「日新館の心得」を学び、会津藩士の子弟としての心構えや誇りを身につける。これらも正之の「会津家訓十五箇条」にインスパイアされたものである。

会津家訓十五箇条(会津若松市役所 提供) 日新館
|
組織全体で幕府を支えるフィロソフィーを共有する会津は、幕府にもっとも忠実な雄藩として諸般からも一目置かれる存在だった。だが、この幕府への忠誠心の高さが幕末の戊辰戦争において、会津の悲劇を生む要因となった。
戊辰戦争で新政府軍の猛攻に耐えた防御力

松平容保
(国立国会図書館 提供) |
最後の藩主となった松平容保(かたもり)は会津の生まれではなく、美濃高須藩の松平家から養子にきた人でいわば「よそ者」だった。それだけに会津の伝統を守ろうという意識が強く働いたのかもしれない。京都の治安を守る京都守護職に任命されたものの、財政に余裕がなく頑なに断ってきた容保だったが、徳川慶喜や松平春嶽らに「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在」という保科正之の教えを引き合いに出され、受けざるを得なかったという。
京都守護職を引き受けた容保は、新撰組を配下に置いて、尊王攘夷派の志士たちを厳しく取り締まったことから新政府軍の宿敵となってしまう。孝明天皇から絶大な信頼を得ていたのにも関わらず、朝敵として追い詰められる。

白虎隊像
|
慶応4年(1868年)戊辰戦争の局地戦である会津戦争で、松平容保は約5,000名の会津藩士とその家族とともに会津若松城にこもり、新政府軍と戦う。
この戦争でよく知られているのが「白虎隊の悲劇」だ。16歳と17歳の少年たちで構成される白虎隊の「二番士中隊」に属する37名が、新政府軍の侵入を防ぐべく城外の野原で待ち伏せして戦うが敗走する。そのうち20名がはぐれ、近くの飯盛山に退避していたとき、会津若松城が燃えているのを見た。城が落ちてしまった以上、もはや生きていてもしかたがないと判断した彼らは自決してしまうのである。実際には城は燃えていたのではなく、煙に包まれていただけだった。自決した少年のうち一人だけ息があり、救出されたことから、この悲劇が広く伝えられるようになった。このほか中野竹子らが女性だけで新政府軍に立ち向かった「婦女隊」の奮戦も、会津戦争を語るうえで欠かせない悲劇といえるだろう。
新政府軍は50門の大砲を城に向け、各50発の砲弾を打ち込む日もあった。城は1日2,500発の砲弾を浴びたことになる。
1カ月の籠城の末、容保は降伏する。無数の犠牲者を出した凄惨な戦いだった。会津若松城の天守は、多くの砲弾を浴びたが落城はせず、なんとか生き残った。北出丸や西出丸など敵の侵攻を迎え撃つ城内の仕掛けは、本丸に突入しようとする新政府軍をよくしのいだという。蒲生氏郷が16世紀末に構想した城の防御力は、19世紀の近代戦においても機能し、「戦う城」としての実力を示したのである。
明治7年(1874年)に会津若松城を撮影した写真がある。戊辰戦争の砲弾によるダメージを受けているが、城そのものは崩れることなく存立している。この直後に会津若松城は取り壊され、廃城となった。
昭和の時代になって、この写真を見た多くの市民が、城の復興を強く願ったという。傷つきながらも生き残った城の姿が、戊辰戦争で朝敵とみなされ、苦難を味わった会津の人たちの心情に訴えるところが多かったと聞く。現在の天守はこの写真を参考に外観が復元されたものだ。復元された当初の瓦は黒だったが、発掘調査で実際には赤だったことがわかり、2011年に葺き替えられている。高温で焼いた赤瓦は水がしみこみにくく、凍害に強く割れにくいという。この東北の城ならではの個性が、会津若松城をさらに特別な城にしている。
イノベーションの旗手だった蒲生氏郷、そしてアンシャン・レジームというべき旧体制の守護役となった松平容保。時を超えて城主のキャラクターと役割が劇的に変わった会津若松城。歴史の舞台として、これほど振り幅の大きい城も珍しい。時代の変化にどう対応するべきかという経営課題について、会津若松城は重要な示唆を与えてくれる。人はどう生きるべきかという根源的な問いについても深く考えさせられる城である。