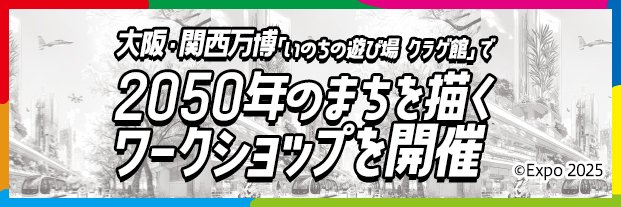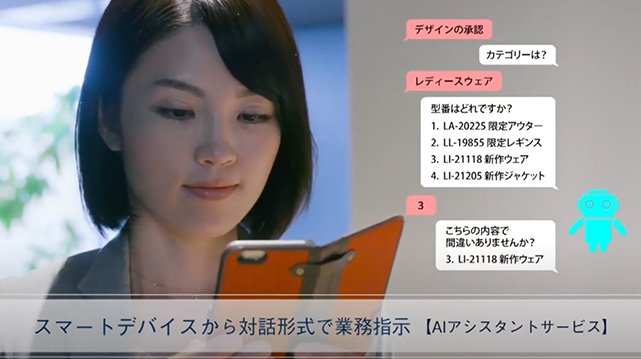小領主の大名、真田昌幸を支えた情報戦略

真田父子犬伏密談図(上田市立博物館蔵)右は真田昌幸、相向かいはその長男信之、その間で下を向いてじっと聞いているのが次男幸村。
|
真田家といえば、知略と武勇の一族という印象が強い。父の真田昌幸と長男の信幸(信之)、次男の信繁(幸村)の親子が率いる家臣団の物語は、さまざまな戦国武将のなかでもひときわ異彩を放っている。
真田家は大名として独立する前は、もともと武田家の家臣であった。昌幸の父の真田幸綱(幸隆)が武田信玄に重用され、昌幸の兄の信綱、昌輝も将来が嘱望される武将だった。しかしながら、兄の二人は武田と織田が戦った長篠の戦いで命を落としてしまう。1575年(天正3年)のことである。
三男の昌幸は武田家の名門、武藤家の養子として頭角をあらわしていたが、兄の死によって名を元に戻し、真田家の当主となったのである。武田の滅亡後は織田信長につくが、1582年(天正10年)の本能寺の変のあとは、上杉、徳川、北条といった有力大名たちと渡り合い、最終的には豊臣秀吉につき、独立した大名としての地位を確保するのである。
 |
真田昌幸が手にした領地は、現在の長野県上田市の周辺と群馬県の北部で、上杉、徳川、北条に比べると小国である。周辺の有力大名に滅ぼされないようにするには強力な武器がいる。ビジネス社会も同様で、中小の企業が大企業と同じ土俵のなかで戦うためには、技術力や開発力など突出したアドバンテージが必要だ。いわば競争力の源泉である。真田昌幸の場合、それは調略だった。
真田家の家臣団は、一門衆、普代衆のほか、信濃衆、吾妻(あがつま)衆、沼田衆、旧武田家臣で構成されていた。組織上は明らかにされていないが、そこには「透波(すっぱ)」といわれる忍びの者も潜んでいる。真田家はこの「透波」を活用した調略を得意とした。実際、難攻不落といわれる城を少ない手勢で陥落させるなど、武田の家臣時代の真田家は、正攻法ではありえない武功を数多く立ててきた。のちに息子の信繁が大坂の陣でめざましい活躍をしたこともあり、世の中では真田家は忍者の使い手という伝承が広まっていく。
そうしたイメージを決定づけたのが明治から大正にかけて流行した立川文庫(たつかわぶんこ)の『真田十勇士』だ。猿飛佐助、霧隠才蔵、筧十蔵、海野六郎、三好清海、三好伊三、穴山小助、由利鎌之助、根津甚八、望月六郎といった真田家の「透波」や武芸者が活躍する物語は、当時の人々の間で大変な人気を博した。彼らは実在の人物ではなく、物語も多くはフィクションだが、それぞれモデルとなった人がいたといわれる。現代でも池波正太郎氏の『真田太平記』では真田家と「透波」の深い関係が描かれている。
諸説はあるものの、真田家臣団と「透波」は切っても切れない関係にあるといえるだろう。
真田家が継承した特殊工作ネットワーク
現代のビジネスにおいて情報の重要さはいうまでもないが、戦国の世にもおいても、それは変わらない。通信インフラなどない当時においては、人的ネットワークが情報網となる。真田家に限らず、多くの有力大名が忍者集団を組織し、独自に情報を収集していた。
そもそも真田家が仕えていた武田信玄が「三ツ者」という隠密集団を組織し、敵を撹乱していた忍者の使い手であった。信玄が真田家の人間を重用した要因として、「透波」を使う能力の高さがあったかもしれない。

洛中洛外図屏風(舟木本)より
歩き巫女部分(東京国立博物館蔵) |
真田家がなぜ「透波」の起用に長けていたのか。それは真田家のルーツにあるといわれる。平安期の清和天皇の子を祖とする滋野氏という一族がある。信州に定着して、古くから「御牧(みまき)」と呼ばれる朝廷の軍馬用の牧場の管理をしていたという。この一族には「歩き巫女」と呼ばれる人たちを配下に置いていた歴史がある。
「歩き巫女」とは諸国を遍歴して祈祷や「口寄せ」といわれる降霊術を行う。こうした人たちのグループが、のちの情報ネットワークに発展したという説もある。滋野氏は、海野氏、根津氏、望月氏の三家に分かれた。真田家はその海野氏の流れをくむといわれ、昌幸の父の幸綱はその一族を統率するリーダーだった。海野氏は加持祈祷や呪術に通じていたとされ、幸綱は山伏と呼ばれる修験者を忍びとしてよく活用したという。根津氏は日本最大の鷹匠流派「根津・諏訪流鷹術」の祖であり、武田信玄にも重用された。望月氏は甲賀に支流をもち、甲賀の忍者を束ねる役割をもっていた。望月千代女(ちよめ/ちよじょ)という人物が女忍集団である「くのいち」を組織し、武田信玄の傘下で活動していたという。
真田家は長篠の戦いによる武田家の滅亡に伴い、無形の遺産を継承したともいわれている。その一つが「甲陽流」といわれる武術だ。武田四天王の一人、馬場信春が甲州流兵法から発展させたものといわれている。
真田の領土だった吾妻地方にはいまも甲陽流の武術が継承されている。そのなかには忍者の奥義と思われる技も少なくない。この地方を治めていたのが、真田家臣団の重鎮だった出浦昌相(いでうらまさすけ)である。彼は武田家に仕えたのち、森長可(もりながよし)を経て、真田昌幸、信幸に仕える。江戸時代後期に、真田家が治める松代藩の家老、河原綱徳が記した『本藩名士小伝』という書物がある。そのなかで昌相は、武田時代より「透波」の頭領であり、真田家でも「透波」を率いたと記されている。実際の昌相は真田家の家老で忍者ではないと考える人は多いが、真相は定かではない。他にも禰津信政、横谷幸重といった家臣が「透波」の頭領として有力視されている。
戦国の世にあって、他の国でも起用していた忍者集団であるが、真田家臣団の場合は真偽のほどはともかく、特に豊富なエピソードが残されている。
真田昌幸・信繁親子の配流期もサポート
ビジネスにおいては、プランAのほかに、プランBを用意することが求められる。もしも予定のプランを実行する際にトラブルが発生した場合、スピーディーに切り抜けるために、代替案をつねに持っておくべし、ということだ。これはそもそも戦争のために考えられた方法論だが、いまやあらゆるビジネスの局面で行われている。

関ケ原合戦図屏風(関ケ原町歴史民俗学習館)
|

左:石田三成肖像(長浜歴史博物館蔵)
右:徳川家康肖像(堺市博物館蔵) |
これを実践したのが真田家である。関ヶ原の戦いを前にして、真田家は2つのプランを用意する。昌幸と信繁の親子は石田三成の西軍に、信幸は徳川家康の東軍につく。信幸は家康の養子となった本多忠勝の娘、小松姫を正室に迎えていることもあり、徳川を裏切るわけにいかないという事情もある。東西に分かれることで、どちらかが勝ち組となり真田家の存続を計ることができると昌幸は考えた。
その結果、破れた西軍についた昌幸と信繁の親子は紀州の高野山、しばらくして九度山に配流される。いっぽう昌幸は家康の命により、上田藩の領主となった。これを境に真田家の家臣団のほとんどは信幸のもとに結集する。真田家の後継者は信幸となったのである。
家臣団のなかには昌幸と信繁の親子に付き添うものもあり、高梨内記など16名が昌幸に従った。しかし、昌幸の死後は13人の家臣が上田に戻り、残ったのは、高梨内記、青柳清庵、三井豊前の3人のみとなった。この3人は信繁が九度山を抜け出し、大坂の陣に参戦するときも同行している。
昌幸と信繁は徳川の監視下にあり、九度山を出ることは許されなかったが、家臣の行き来まで厳しく制限されることはなかった。このおかげで、信繁が考案したといわれる「真田紐」を販売するというビジネスも家臣を通じて展開できたのである。結局、信繁は関ヶ原の終戦後から大坂冬の陣が始まるまで、13年間にわたり、九度山に幽閉されるが、大坂の陣では長年のブランクを感じさせない働きを見せる。
信繁は大坂城の南側に出丸の「真田丸」を築き、知略を尽くした戦法で徳川軍に大打撃を与えた。さらに翌年の夏の陣でも徳川家康の本陣に迫り、圧巻の戦いぶりを見せる。
九度山時代の信繁は再起を計って家臣たちと実戦の訓練をしていたという言い伝えがあるが、その証拠となるような明確な記録は残されていない。ただ家臣団のサポートなくしては、合戦に参加できるような体力や気力を保ち続けることは困難だったに違いない。
少数でも大きな力を発揮するスキルの高さ

上田城
|
真田家臣団を特徴づけるケイパビリティは、なんといっても少数精鋭である。上田城の合戦では二度にわたり徳川の大軍を翻弄している。
1585年(天正13年)の第一次上田合戦は、真田軍2,000に対し、徳川軍7,000余。圧倒的な兵力差がありながら、徳川軍の戦死者は約1,300人、多くの負傷者を出し、徳川家康を撤退に追い込んだ。これに対して真田軍の戦死者は21人であった。
1600年(慶長5年)の第二次上田合戦では、上田城に籠城し、関ヶ原に向かう途中の徳川秀忠の3万8,000の軍を5日間も足止めさせ、関ヶ原の戦いに遅参させるという妨害を行った。このときも真田軍は2,000にすぎなかった。
1615年(慶長20年)の大坂冬の陣では、真田信繁がごくわずかな手勢を率い、家康の息の根を止める寸前まで追い詰めるなど、少ない人数で最大限の効果を上げている。それは優れた知略があってこそ成立するものだ。そのパフォーマンスの高さは、昌幸や信幸、信繁の知略やカリスマ性やリーダーシップに因るところが大きいが、家臣たちの優れたスキルが寄与している。
「透波」を巧みに活用するのが真田の戦法の特色でもある。「透波」は基本的に一人で行動する。すべて自分で考え、行動し、ミッションを遂行しなければならない。敵から襲われたときも自分で身を守らねばならない。そうしたスキルの高い者を多く抱えていたことが、真田の家臣団の強さを引き出していたと考えられる。
これは企業にとってもいえるだろう。指示待ちではなく、自らの意志でビジネスを推進できるようなプロ意識の高いチームは、企業価値を高める牽引力になりうる。
しかし、少数精鋭のチームが力を発揮するのは独立したユニットのときだけだ。これが他の集団と共同で作業を行う場合、能力のレベルを下げることになり、本来の持ち味である緻密さやスピードが失われ、破綻が生じてしまう。
大坂の陣で「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」と称賛され、信繁の軍は獅子奮迅の働きを見せたものの、豊臣軍の勝利に結びつけることはできなかった。
 |
グループ企業の経営では、ブランド価値を守るため、トラブルを起こした企業を切り離したり、解体させることはよくあることだ。しかし真田家はその手法をとらなかった。
信繁という反徳川勢力の火種を抱えながら、信幸は中心母体としての真田家を守り抜いた。しかも信幸は本多忠勝や本多正信といった徳川家の重臣に働きかけて何度も信繁の釈放を願い出ている。豊臣恩顧の大名を次々と弱体化させていた当時の家康の動きからすると極めて危険な行為であり、真田家が改易させられてもおかしくはない。しかも、大坂の陣では信繁に加勢しようという家臣が数多くあらわれる。
その数は50騎とも300騎とも伝えられ、信繁の義兄弟にあたる堀田作兵衛などの重臣も含まれている。そのうえ信繁の真田軍は徳川を大いに苦しませた。にも関わらず、終戦後も家康の信幸に対する信頼は失われることがなかった。信幸は93歳まで生き続け、真田家も10万石の大名として幕末まで命脈を保ち続ける。昌幸や信繁に注目が集まりがちな真田家だが、家臣団を守ることに心を砕いた信幸の手腕は、サステナブル経営のケーススタディとして参考に値する。