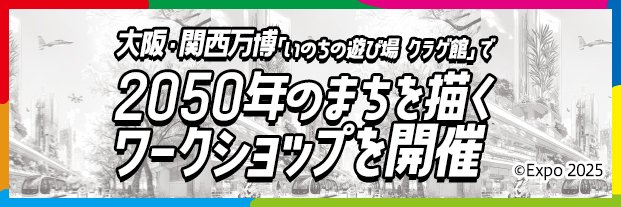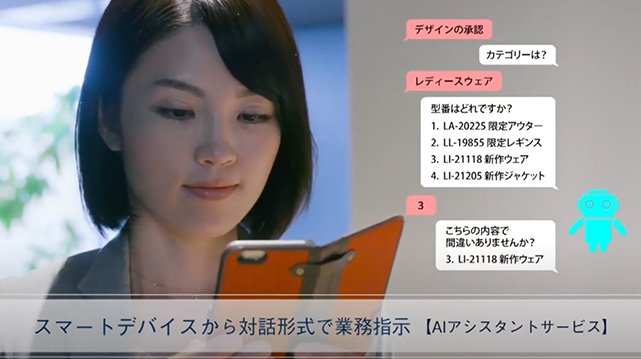豊臣秀吉の身内を中心にした
ファミリーが基盤

豊臣秀吉像(高台寺蔵)
|
豊臣秀吉ほど、家臣団の編成に労を費やした戦国武将はいないだろう。織田信長にしても、徳川家康にしても、親から受け継いだ家臣団があったが、農家に生まれた秀吉には家臣そのものが存在しない。しかも身内と呼べる親族が極めて少なかった。まさにゼロから家臣団を築き上げたといっていい。
信長のもとで頭角をあらわし、足軽大将となった頃の秀吉は、ビジネスに置き換えると、裸一貫で事業を立ち上げた起業家のようなものだ。みずからの才覚で道を拓き、独立を勝ち得たが、いざ会社を経営しようという時点で、信頼できる協力スタッフが数えるほどしかいない。これから大きく会社を成長させるためには、まだまだ優秀な人材が必要だった。しかし戦国の世において、いかに優れた才能があるとしても、縁もゆかりもない部下を側近としておくことは、いつ裏切られるかもわからず不安がつきまとう。側近には、最も信頼できる人物を配置したいと願うのは無理もないことだ。

上:豊臣秀長肖像(春岳院蔵)
下:高台院(ねね)肖像 (名古屋市秀吉清正記念館蔵) |
秀吉が最も頼りにしていたのは、三歳違いの異母弟(実弟という説もある)の秀長である。秀吉の影に隠れて目立たない存在だった秀長だが、最近の研究では秀吉に勝るとも劣らない豊かな才能をもった人物として評価されている。これが武家ともなると、優秀な弟は自分の主君の座を脅かす存在として排除されることもある。実際、織田信長は次弟の信勝(信行ともいわれる)と苛烈な後継者争いをしたのち、死に追いやっている。親族の少ない秀吉にとっては、血のつながった兄弟は数少ない味方だったのである。
さらに妻のねね(おね)の親族も重用した。武家の出であった彼女は、杉原家、木下家、浅野家といった親類があり、杉原家次や木下家定、浅野長政は秀吉をよく支えた。武家の一門衆をもたない秀吉にとって、初期の段階では彼らが側近の役割を果たしたのである。このほか頼りにしたのは秀吉の姉のともである。子どもに恵まれなかった秀吉とねねは、ともの子どもたちを養子に迎える。秀次や秀勝(小吉)である。その弟の秀保も秀長の養子になっている。また、ねねの兄の子である秀俊も養子にした。のちの小早川秀秋である。
さらに秀吉が行ったのは、いわゆる「子飼い」である。親類から子を預かり、ねねのもとで家族のように育てることで、忠誠心の高い一門衆を構成しようとした。加藤清正、福島正則、加藤嘉明らである。石田三成は親戚ではないが、秀吉が若い頃から目を付け、小姓から育てあげた子飼いの武将である。こうした「ファミリー」を増やすことで、秀吉は家臣団の充実と安定をはかった。人材不足というみずからの弱点を自覚し、初期の段階で積極的に身内の強化を行い、将来の家臣団編成に向けて周到な準備をしていたのである。
有能な人材は秀吉みずから
ヘッドハンティング

竹中半兵衛銅像
|
もともと家臣のいない秀吉は、つねに人材を求めていた。人材発掘の目利きでもあり、有能なヘッドハンターだったともいえるだろう。人材獲得におけるもっとも有名なエピソードのひとつが、竹中半兵衛にまつわるものだ。
軍略家としてすでに高い名声を得ていた半兵衛は、美濃の斎藤家の家臣だったが、織田信長の美濃攻めによって斎藤家が没落したのに伴い、隠棲生活を送っていた。信長は秀吉に半兵衛を織田の家臣としてスカウトすることを命じる。秀吉は半兵衛の元を何度も訪れ、勧誘を行うが、なかなか首を縦に振らない。繰り返し誠意と熱意をもって説得した結果、半兵衛は信長の直参の家臣になることは辞退するが、秀吉に仕えることを約束した。1567年(永禄10年)のことである。
後世の記録では、このときの様子を中国の『三国志』で、劉備玄徳が諸葛孔明を軍師として迎え入れるために行った「三顧の礼」になぞらえたものがある。彼を「今孔明」と形容する人もあった。半兵衛はのちに黒田官兵衛とともに「二兵衛」として秀吉の躍進を支える。秀吉はみずからも調略を得意とするだけに、半兵衛の才能を誰よりも理解していたともいえる。だからこそ半兵衛は信長ではなく、秀吉に仕えることを選んだとも考えられる。
もうひとつ代表的なものが、石田三成を見い出したときの「三献茶」といわれる逸話だ。
秀吉が鷹狩りの帰りに近くの寺に寄り、寺小姓に茶を頼んだときのことである。寺小姓は最初に大きめの茶碗にぬるめの茶をもってきた。秀吉は一気に飲み干し、もう一杯を所望した。二杯目に出てきたのは、少し熱くしたお茶を半分ほど注いだものだった。さらに三杯目を頼むと、小さめの茶碗に熱い茶が出てきた。最初はぬるめの茶で素早く乾きをいやしてもらい、二杯目からは徐々にお茶を熱くし、お茶の味を楽しんでもらおうという心づかいを高く評価した秀吉は、この寺小姓を召し抱える。これがのちの石田三成である。
1574年(天正2年)あるいは1577年(天正5年)のできごとだったと伝えられる。

石田三成(長浜歴史博物館)
|
この逸話は後世の創作という説もあるが、秀吉の人を見る目、三成の賢さをよくあらわしている。三成はその後、五奉行のひとりとして豊臣政権を支えることになる。武勇がもっとも尊重される戦国時代に、三成のような細やかな心づかいをもち、マネジメント能力に秀でた知恵者に目をつけるところに秀吉の非凡な才能をうかがい知ることができる。
家臣団の強さとは武力だけではない。そうした秀吉の認識が三成や大谷吉継のようなテクノクラート的な資質をもった者たちを引き寄せた。こうした「計数の才」をもつ家臣が、各国を攻略するうえでのロジスティクスや統治後の検地などのデータ集積で大きな力を発揮するのである。
巧みな人心掌握術で
家臣たちのやる気を引き出す

長浜城
|
1573年(天正元年)、織田信長が浅井長政(あざいながまさ)を下した小谷城(おだにじょう)の戦いで、秀吉はめざましい功績をあげる。その褒賞として浅井家の旧領だった北近江を与えられる。1574年(天正2年)、秀吉は長浜城を築き、念願の城持ち大名となるのである。この頃から秀吉は羽柴の姓を名乗り、家臣団は次第に厚みを増していく。ローカルなファミリー企業から、より大きな事業を手がける全国区のメジャー企業に変化を遂げようとしていた。
信長から貸与された与力でありながら、重臣の役割を果たしていた蜂須賀正勝(小六)、前野長康をはじめ、山内一豊(やまうちかずとよ)、堀尾吉晴といった同郷の尾張出身の武将も家臣となっている。加藤清正、福島正則、加藤嘉明といった子飼いの親族たちも育ちはじめ、石田三成、大谷吉継らも小姓として仕えはじめる。さらに若手の育成に力を注いでいる。織田信長は「黒母衣衆(くろほろしゅう)」「赤母衣衆(あかほろしゅう)」と呼ばれる将来有望な若者による精鋭軍を組織していたが、これを見習い秀吉も「黄母衣衆(きほろしゅう)」を編成した。
 |
苦労人だった秀吉だが、人の心をつかむことに長けていた。よい働きをした者にはねぎらい、相応の恩賞を与えるなど家臣がやる気になる「職場環境」や「待遇」を提供した。そうした秀吉の人事政策を支えたのが情報力と経済力である。その人が何を必要としているのかを情報ネットワークを駆使して綿密に調べ、相手の望むものを提供するのである。美濃を攻略する際は川並衆(かわなみしゅう)と呼ばれる木曽川流域を拠点とする土豪の人たちを使って、斎藤家の家臣を調略し、戦わずして従わせている。浅井家の近江を攻めるときも、竹中半兵衛に命じて浅井家の家臣を味方に引き入れている。もちろん、そこには単なる説得ではなく、経済的なメリットも織り込まれている。信長の楽市・楽座を継承し、長浜を大きく発展させた秀吉は経済の重要性を当時の武将の誰よりも熟知していた。理詰めの説得工作はもちろん重要だが、最後のひと押しには金がものをいうことを、足軽から叩き上げの秀吉は、身をもって体験していたのである。
半兵衛の亡きあと、秀吉の軍師・参謀として重要な働きをした黒田官兵衛も、秀吉のキャラクターに魅せられたひとりだ。中国攻めの軍団長となった秀吉のために、みずからの居城だった姫路城を提供している。お互いの信頼関係が強固であることは大前提だが、官兵衛としては秀吉の家臣になることで、播磨ローカルではなく全国区の武将として力を発揮できるというメリットがある。一方、秀吉は官兵衛を重用することで、より精度の高い計略を立案することができる。秀吉はそうした個人のモチベーションを読み取り、Win-Winの関係を築くことに長けた人物だった。
武力と知力を駆使した
天下統一プロジェクト
豊臣家臣団を特徴づけるケイパビリティは「交渉力」といえるだろう。家臣の役割は権謀術数に長けた秀吉の策略を実行に移すことであった。初期の頃から、秀吉の重臣として働いてきた蜂須賀正勝は武闘派に思われがちだが、戦わずして相手を説得するデリケートな交渉事を数多く成功させている。さらに竹中半兵衛、黒田官兵衛という稀代の軍師が、武力だけでは攻略できない相手も、緻密な策略をめぐらし、交渉を行うことで配下に収めた。もちろん、そうした交渉力の背景には、加藤清正、福島正則、加藤嘉明といった子飼いをはじめとする猛将たちの武力があり、確実に勝つためのロジスティクスを取り仕切る石田三成や大谷吉継らの知力がある。こうした人材の絶妙なバランスが豊臣家臣団の強みとなっていたといえる。
竹中半兵衛、黒田官兵衛の「二兵衛」に関する、こんなエピソードがある。信長に反旗を翻し、有岡城に籠城した荒木村重を説得するために、秀吉は官兵衛を交渉役として派遣する。しかし、官兵衛は村重に捉えられ、土牢に監禁されてしまう。官兵衛が帰ってこないのを知り、村重に寝返ったと判断した信長は激怒し、官兵衛の嫡男の松寿丸(のちの黒田長政)の首をはねる命令を下した。
官兵衛をよく知る竹中半兵衛は、これが何かのアクシデントであると判断し、松寿丸を寺にかくまい、別の首を差し出して難を逃れる。その後、官兵衛が解放され、誤解がとけたあと、はじめて松寿丸をかくまっていたことが明かされるが、虚偽の報告をしていた半兵衛に対して、信長が咎(とが)めることはなかったという。
自分の判断を正しいと信じ、ときには主君の命令にも背く。親族同士が命を奪い合うような殺伐とした戦国の世の中で、的確な判断力と温かな人間味を保ち、窮地に陥った仲間を救う。こんな家臣がいたことが、秀吉が天下人になった一因なのかもしれない。
 |
だが、後継者争いと、豊臣秀長という名補佐役の死、朝鮮出兵による家臣の疲弊などで、天下を手中にしたあとの豊臣家臣団は内部から崩れていく。特に朝鮮出兵は加藤清正らの武断派と、石田三成らの文治派の深刻な対立を招いてしまう。外国との戦いで領地の分け前がなく、充分な報酬が得られないことが、家臣たちの不満を蓄積させることになる。
そして秀吉の死後は、たちまちにして求心力を失い、豊臣家臣団は瓦解の一途を辿る。
天下統一というゴールまではうまく機能した組織も、目的を終えたあとは道を見失ってしまう。強い組織を維持するためには、多くの人を納得させる公明正大なリーダーシップと、多くの人が未来の指針として共有できるビジョンが大切なことを、豊臣家臣団はあらためて認識させてくれる。