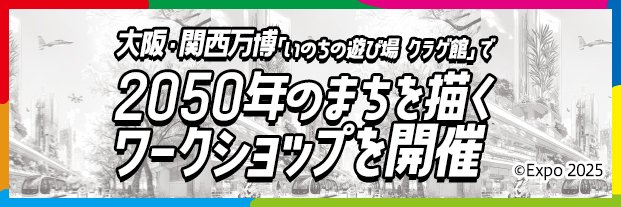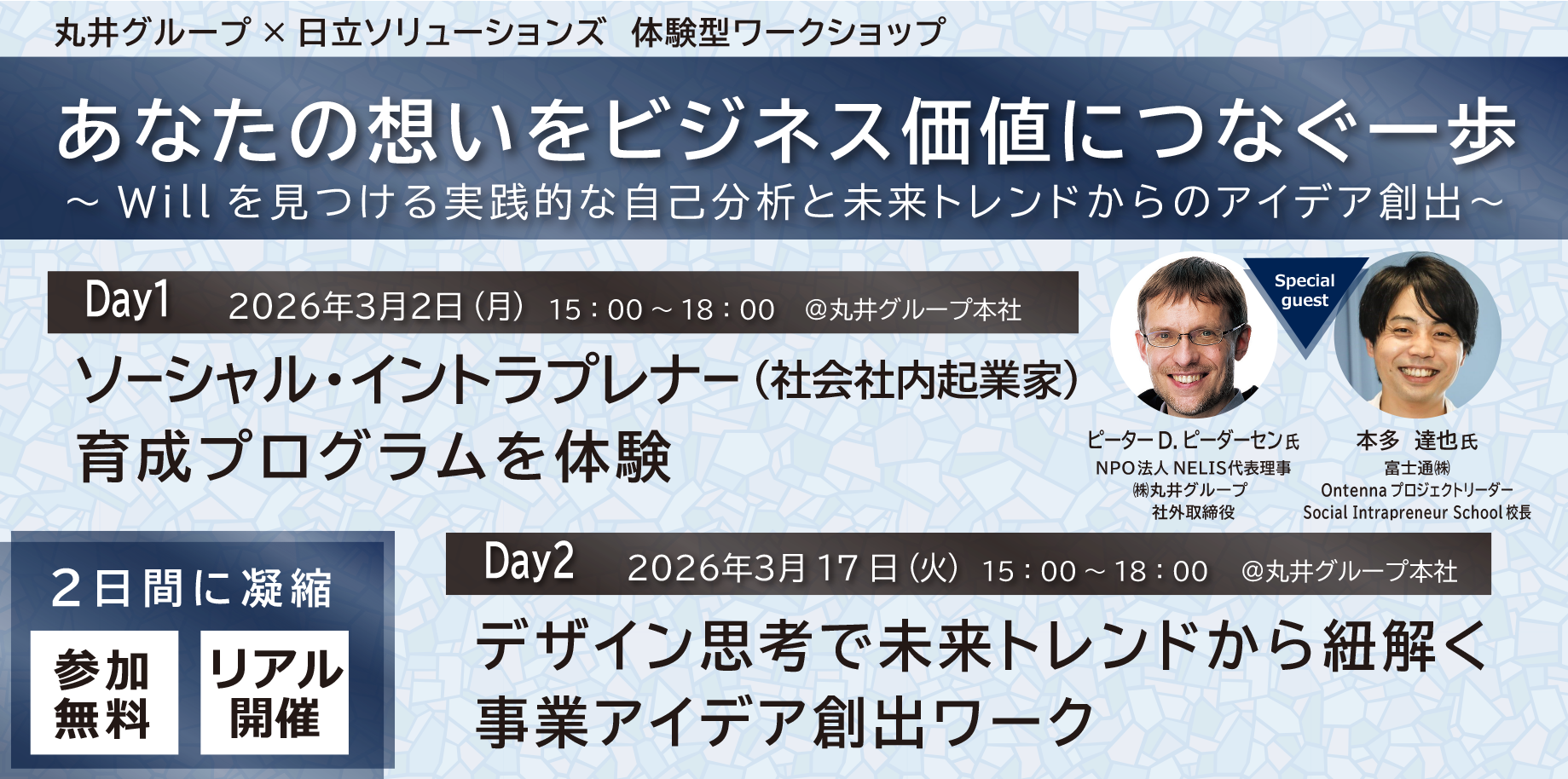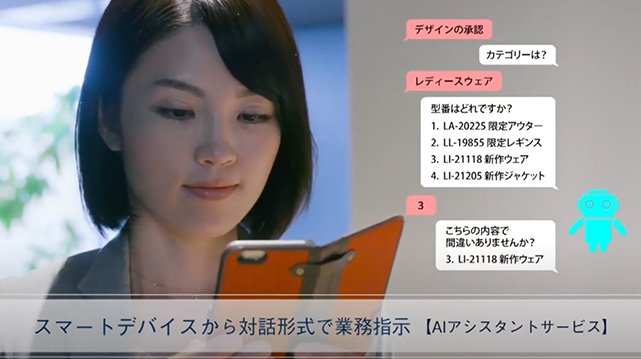徳川家康を支える古参スタッフ中心の編成

徳川家康肖像(堺市博物館蔵)
|
ここ最近で急成長を遂げた企業もあれば、かつて隆盛を誇りながら失速した企業もある。変化の激しい現代のビジネス社会においては、いかに経営者が優秀でも、ブランドに歴史があっても、組織が脆弱だと生き残ることがむずかしい。本当に強い組織づくりとは何か。戦国時代の家臣団をケーススタディとして考えていきたい。
最初にとりあげるのは徳川家臣団である。家康を主君とし、優秀な武将を数多く抱える家臣団であり、ビジネスの視点からみると圧倒的な力をもったメジャー企業のような印象を受ける。しかし、徳川に改名する前の松平家が治めていた三河の家臣団は、経営の安定しない中小企業のような存在にすぎなかった。強大な今川と武田、そして新興勢力の織田に挟まれ、どこかの有力大名と手を結ばないと単独では存続がむずかしい状態だった。家康はいかにして強固な組織づくりに成功したのか。そして徳川家臣団はなぜ覇者のチームに成長することができたのか。そこに組織づくりの重要なエッセンスがある。

岡崎城
|
徳川家臣団を語るうえで欠かせないのが三河武士団の存在だ。
家康の父、松平広忠はまだ幼い家康を今川に人質に出し、弱小だった三河の存続をはかる。だが広忠は家臣の謀略によって命を奪われ、本拠地の岡崎城は城主が不在となる。そのため今川から代官が派遣され、三河は今川の属国のような扱いになってしまう。
この家康の人質時代に岡崎城を預かっていたのは、本多、榊原、石川、鳥居といった長老たちだった。いわゆる三河武士団である。この長老たちは、のちに家康を支える本多忠勝や榊原康政といった重臣たちの親世代であり、家康の祖父にあたる松平清康の時代からの家臣である。若くして三河を統一する勢いだった祖父の清康は非凡な才能をもった英明な君主と期待されながら、政略によって家臣に殺されてしまった。この無念を晴らすべく家康に期待していたのである。窮乏生活に耐えながらも、いつかは家康を岡崎城の城主に迎え入れるという思いが、彼ら三河武士団の結束をいっそう固めたともいえる。
ゼロから人を集めるのは大変だが、すでに三河には松平家には優秀な人材が存在した。雪辱に燃える高いモチベーションをもった古参の家臣団が、松平家復興のために準備を怠らず、あとは領主の帰還を待つだけになっていた。
1560年(永禄3年)に桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れたのを機に、家康は岡崎城に戻り、ようやく今川から独立する。ここから本格的な組織づくりが始まるのである。
安心して仕事をまかせられる人材が集結
働き方改革で時短が叫ばれる昨今だが、若い組織にはハードワークはつきものだ。損得を度外視してチームのために働く献身的なスタッフがどうしても必要なときがある。家康はそうした家臣に恵まれていた。その代表が徳川四天王と呼ばれる、酒井忠次、榊原康政、本多忠勝、井伊直政である。

徳川十六将図(致道博物館蔵)
|
酒井忠次は徳川のナンバー2として家臣団を支えた重臣だ。家康の親の代からの家臣で、家康よりも15歳、榊原康政と本多忠勝よりも21歳、井伊直政にいたっては34歳も年上である。家康が今川義元の人質だった時代から仕え、苦楽をともにしてきた腹心である。
家康は三河を統一する過程で、忠次に東三河を任せ、その拠点である吉田城の城主に任命している。家康が家臣を城主にしたのは、この忠次の一件だけであり、いかに家康が信頼を寄せていたかがわかる。武将として優秀だっただけでなく、戦略家であり、交渉術にも長けていた。拙速な行動をとる若手を制するだけでなく、若手を育てるメンターとしての役割も果たしている。こうした豊富な経験と知見をもつキャリア人材は、強い組織づくりには欠かせない人物だ。
榊原康政と本多忠勝は武功派の重臣である。今川から独立し、岡崎城に戻った家康だが、決して基盤が安定していたわけではなかった。家康の統治を望まない者もいたのである。そうした対抗勢力との戦いが1563年(永禄6年)の三河一向一揆である。免税などの特権を得ていた三河の一向宗(浄土真宗)に対して、家康が課税しようとしたことが反乱の原因とされている。一揆の側には松平家の家臣も多く、三河武士団を二分する混乱を招いた。この事件は三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並び、家康の三大危機とされる。
この窮地を救ったのが、本多忠勝と榊原康政である。本多忠勝はわずか16歳で、一向宗の門徒でありながら、家康とともに戦うために浄土宗に改宗し、並外れた武芸の腕を発揮し、一揆の鎮圧に貢献する。榊原康政も忠勝と同じ16歳で、まだ元服していなかった。にもかかわらず、みずから志願して先陣を務め、相手を圧倒する働きをみせた。
この2人はのちに旗本先手役となって多くの武功をあげる。本多忠勝は57回の戦のなかで、一度も刀傷を負わなかったという逸話を残す。
井伊直政も武功派だが、譜代の家臣だった忠勝や康政と違い、もとは今川の家臣だった。若いうえに外部からの中途採用でありながら異例のスピード出世を遂げる。直政の能力が優れていたこともあるが、出自や年齢を問わず実力のある者を抜擢して厚遇することで、家康の人材活用に対するスタンスを世に示したともいえる。徳川家臣団に入れば、若い自分でも、あるいは主君を失った自分でも、活躍の場がある。そう思わせることで、多くの優秀な人材を引き寄せることが可能になる。
よき相談相手となるブレーンが充実

本多正信(加賀本多博物館蔵)
|
徳川家康のそばには、つねに信頼できる相談相手がいた。四天王に加えて、もう一人、欠かせない人物がいる。本多正信である。
本多正信は異色の存在である。もとは鷹匠であり、40代の半ばになって、参謀として家康に仕えるようになった。家康よりも4歳年長である。
正信は1563年(永禄6年)の三河一向一揆では家康に敵対する側にまわった。以後、約20年にわたって三河を離れたのち、家康のもとに帰ってきたのである。かつて敵対した人物を側近として迎える家康も寛容だが、それを認めざるを得ない能力が正信にはあったということだろう。

「絵本鷹かゞみ」河鍋暁斎 (洞郁) 著
(国立国会図書館蔵) |
鷹狩りは長時間にわたって野山を歩き回り、そのあいだに主君と家臣たちの間で、さまざまな会話が交わされる。レジャーでありながら仕事の要素も含んでいるという意味では、現代のゴルフと似たところがある。そうした鷹狩りを通して、正信は家康の相談相手として信頼を得るようになった。知略にすぐれ、卓越した政治力と交渉力を備えた正信は、家康の意向を読み取り、さまざまな政局で目覚ましい働きをする。
謀略に関わることが多く、冷徹な人物と思われがちだが、温情家であることを示す逸話も多い。徳川家のために、あえて汚れ役を引き受けるようなところもあった。本多忠勝や榊原康政のような武功派の武将とは相性が悪かったらしいが、そうした水と油のような人材が共存する多様性が、徳川家臣団という組織の強みになっているともいえる。
また家臣団ではないが、家康は外部スタッフをブレーンとしてうまく活用した。宗教面では以心崇伝(いしんすうでん)や天海僧正(てんかいそうじょう)、経済面では茶屋四郎次郎や角倉了以(すみのくらりょうい)、外交面ではオランダ人のヤン・ヨーステンやイギリス人のウィリアム・アダムズを顧問としている。自分や家臣団にはない能力を外部に求めることで、組織をさらに強いものにしていったのである。
1582年(天正10年)本能寺の変のあと、徳川は織田が治めていた甲斐や信濃も領土とし、さらに勢力を拡大する。1590年(天正18年)に北条氏が滅亡したあとは、家康の力を恐れた豊臣秀吉によって関東に移封される。こうなると拡大した領土をいかに統治するかが重要になってくる。また徳川を警戒する秀吉を出し抜き、天下取りを狙う野心も芽生えてくる。ビジネスに置き換えると、攻撃的な営業展開を重視した組織から、シェアを維持しつつ拡張するマネジメントを重視した組織へと生まれ変わる必要性が増してきた。こうした状況の変化に合わせて、徳川家臣団は武功派から文治派へ、イニシアティブを握る家臣が変わっていく。ともすると、武功派と文治派の対立から内紛が起こりそうなものだが、本多忠勝や榊原康政はみずからの役割をよく心得ていて、政局にからむことには、ほとんど口を出さなかったという。
高い結束力で徳川のガバナンスを強化
徳川家臣団を特徴づけるケイパビリティは「結束力」である。この結束力は家康に対する求心力ともいえる。経営トップとしての家康は、家臣からの信望が極めて厚かった。家康が家臣の意見をよく取り入れ、それぞれの家臣の働きに対して、誠意をもって報いたからともいえる。組織のなかにはさまざまなタイプの人間がいたが、主君への忠誠心においては、一枚岩ともいえる強さがあった。
たとえば、こんな逸話がある。新たに徳川の傘下に加わった武田氏の精強部隊、騎馬隊が井伊直政に与えられたとき、榊原康政は直政ばかりが優遇されるのが気に入らず、「直政を切り捨ててやる」と不満を酒井忠次にぶつけた。これに対して忠次は烈火のごとく怒り出す。家康は最初、忠次に騎馬隊を与えようとしたが、忠次はこれを断り、かわりに直政に与えることを進言したという。家臣団では若くて外様同然の直政の出世を妬む者が多く、直政に騎馬隊を与えて戦果をあげさせれば、文句を言うものはいなくなるだろうと忠次は考えたのだという。家臣団の不和を未然に防ぐ忠次らしい知恵である。
その後日談もある。関ヶ原の合戦のあと、家康は榊原康政に25万石を与えると提示した。しかし康政は、自分は上田城での真田との戦いで足止めを食い、合戦に遅れた秀忠の軍に属していたので戦功はなく、そこまでの俸禄を得る資格はない、と辞退したという。また、身の丈に合わない大禄を得ると慢心を生み、自分にとっても徳川にとってもよくない、と語ったともいわれている。若いころは自分に対する評価が低いと不平をもらしていた人物が、時を経て自己を律する人格者として熟成されていたのである。
 |
チームの輪を何よりも重んじる。そんな徳川家臣団のコーポレートカルチャーは、領主不在の窮乏生活に耐えた三河武士団の長老から、四天王を中心に継承され、家臣団のDNAとして浸透していった。これは家康が押し付けたものではなく、家康と家臣たちの付き合いを通して、自然と醸成されたものといえる。力による支配が主流だった戦国の世の中で、徳川家臣団は信頼をベースにした強固な組織を築き、頂点に立つことができた。人間関係のもつれから破綻を招いた織田や豊臣の家臣団の末路をみると、この徳川家臣団の存在がいかに特別なものだったかがわかる。
現代ビジネス社会の組織において、イノベーションや生産性が重要なことはいうまでもない。その前に組織としてもっとも大切なことは何かを、徳川家臣団は思い起こさせてくれる。