



社会を明るくする「稀人」を見出し、その半生やものづくりを紹介してきた稀人ハンター、川内イオ氏。独自の価値観で生きる稀人たちの取り組みを丹念に取材し、魅力的なストーリーとして世に送り出してきた。近年は稀人と企業をつなぐコラボレーション企画も手がけ、新たな価値創造の場を広げている。

川内 イオ
稀人ハンター
かわうち・いお
千葉県出身。広告代理店勤務を経て2003年よりフリーライター。06年にバルセロナに移住し、サッカーライターとして活動する傍ら、パリで日本人クリエーターなどを取材。10年に帰国しサッカー誌やビジネス誌の編集部で勤務した後、13年よりフリーランス。農、食、スポーツなどの分野で様々な活動を続けている。
―川内さんのいう「稀人(まれびと)」とは、どのような人でしょうか。
有名無名にかかわらず、社会に希望をもたらす活動をしている人たちです。「規格外の稀な人」ということもありますが、それだけでなく世の中を明るくすることも重要な要素と考えています。ごく普通の生き方をしていても、「稀」な部分を持っている人はいると思います。
―「稀人ハンター」になったきっかけを教えてください。
2006年から10年まで、バルセロナでサッカーライターをしていました。滞在中、現地のサッカー業界で働く日本人を取材してまとめた本がきっかけで、実際にスペインなどへ留学やサッカーの修業に向かう人が現れ、文章の影響力と責任を強く実感しました。また、当時パリで活躍する日本人クリエーターなども取材し、トータルで50人ほどの話を聞きました。知らなかっただけで、すごい人があちこちにいることに驚きました。帰国後、このような規格外の稀な人を見つけて世の中に広めたいと考えていた時に「稀人」という言葉がふと浮かび、稀人ハンターを名乗るようになりました。

―農業や食に関わる書籍、記事を多く手がけていますが、この分野に思い入れのようなものはありますか。また、サステナビリティを意識している稀人が多いですね。
食いしん坊だからでしょうか(笑)。例えば兵庫県のパン職人、塚本久美さんは冷凍パンを通販で売っています。台風で停電になり冷蔵庫が使えなくなった農家から野菜を仕入れたり、栽培過程で間引かれたブドウの実をパンに入れることもあります。
塚本さんはとても珍しい通販専門のパン屋さんなので、全国で大人気です。以前、有名なパン屋さんで修業していた頃、まだ食べられるパンを廃棄するたびに心が痛んだそうですが、そんなストレスからも解放されたようです。
―印象に残っている稀人との出会いについてお聞きします。
宇宙ベンチャーのアイスペースCEO、袴田武史さんとは11年ごろからの付き合いです。今年6月の月面着陸(ミッション2)は未達でしたが、すでにミッション3に向けて準備を進め、数百億円規模の資金調達にも成功しています。
袴田さんが副業で宇宙ビジネスを構想していた当時、オフィスとして東京・恵比寿の物件を紹介したことがあります。またチーム名を決める際にはアイデアも出しました。現在の「HAKUTO」という名称は僕の提案ではないですが、構想段階から関わらせていただいた思い出深い経験です。
猿田彦珈琲を創業した大塚朝之さんとの出会いもこの頃です。恵比寿に1号店を開店して間もない時期でしたが、現在では全国に数十店舗を展開する人気チェーンへと成長しています。
この2人に限りませんが、自分が「この人は」と見込んだ人たちが活躍しているのを見るのは楽しい。ドヤ顔で自慢したくなりますし(笑)、稀人ハンターの醍醐味でもあります。

―書籍では様々な分野でものづくりに挑む稀人たちも数多く紹介されています。稀人が活躍しやすい時代になったのでしょうか。
以前は、素晴らしいものをつくっても、伝える手段や販売する機会が限られていました。今ではSNSを使って購入者が感想を広めたり、つくり手自身もこだわりを発信できる。ECという販売ルートもできました。資金をクラウドファンディングで募ることもできます。
例えば廃棄野菜を使って「おやさいクレヨン」をつくっている木村尚子さん、1000万円以上の腕時計を製作する独立時計師の菊野昌宏さん、コーヒーグラインダーのメーカーを立ち上げたダグラス・ウェバーさんは、食べ物や道具など商品は様々ですがそれぞれの方法で発信し、ネットワークや資金を集めることで成功しました。一世代前と比べると、稀人が自分の生き方を貫きやすい、やりたいことをやりやすい環境が整ってきたように感じます。
―独自の道を切り開く稀人たちに、とがった商品に引かれる消費者だけでなく、多くの企業も注目し始めていますね。
典型的な例はおやさいクレヨンです。規格外品や加工時に廃棄される野菜を原料にしたクレヨンは、発売直後から注目を集め、多くのメディアで取り上げられました。SDGsへの関心の高まりを背景に、大手企業からも協業の提案が寄せられています。例えば、自社ワイナリーの廃棄農作物を活用したクレヨンづくりの相談などです。
―企業とのコラボイベントなど、「稀人×企業」の活動にも積極的に取り組んでいますね。
14年、アパレルブランドが東京・原宿に開設した書店併設型ショップで、イベントを僕が企画運営しました。地下フロアにある書店の認知度向上が課題だったため、旅行や健康、スポーツをテーマに著者を招いたトークイベントを開催。月2回のペースで約4年間継続し、これが稀人と企業を結ぶ活動の第一歩となりました。以降、様々な形で企業とのコラボを展開しています。
例えば、建設関係のコンサルティング会社から、社員エンゲージメント向上のための施策を行いたいとの話があり、稀人をゲストに迎えて彼らの活動を紹介する「朝活」というイベントを始めました。最初に招いた稀人は、スウェーデン人の日本茶インストラクター、ブレケル・オスカルさんです。東京で開催した朝活には希望する社員が直接参加し、他の地域で勤める社員はオンラインで参加できるようにしました。会場に来た参加者にはお茶の飲み比べの体験をしてもらいました。オスカルさんへの取材を基に僕がお茶の話をしても面白くないですよね。稀人本人だから強い説得力がありますし、専門家だから本当においしいお茶を提供することができる。イベント終了後には、オスカルさんが持参したお茶を購入しようと多くの社員が殺到しました。
その後、スペインのプロサッカークラブで働いた経験のあるスポーツトレーナーや著書多数の有名鍼灸師を招いて体を動かす朝活を開催し、とても好評でした。デジタル時代だからこそ、リアルな体験の持つ価値は高まっていると感じます。
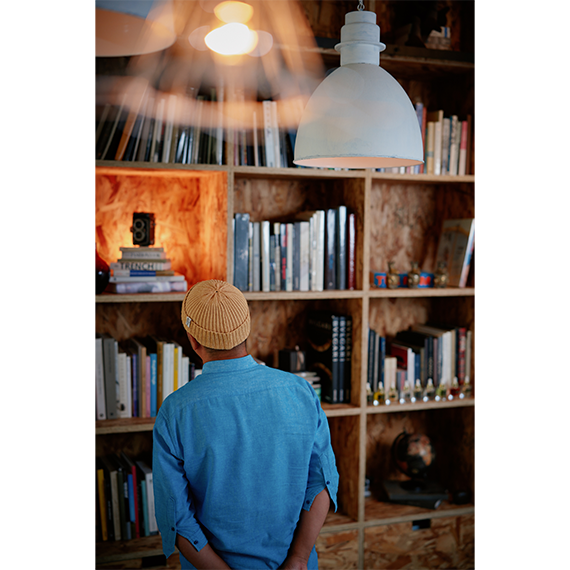
―企業とのコラボレーションには、他のパターンもありますか。
19年に始めた「稀人マルシェ」という活動があります。僕は食べ物について書くことが多いので、読者から「実際に味わってみたい」という声がよく届きます。そこで、皆さんも食べられる機会を設けようと考え、スタートしました。パンやチーズ、ジャム、お茶など僕が取材した稀人の商品を自費で買い取り、販売するイベントです。
当初は自主企画としてスタートしましたが、この取り組みを知ったある百貨店から「一緒にやりませんか」と声がかかりました。有楽町にある館内でのマルシェ開催の提案で、快諾しました。24年秋に実施したマルシェが好評で、25年6月には、富裕層の顧客向けのイベントでもコラボが実現。この回には著名な醸造家の斎藤まゆさん、イタリアで受賞経験のあるジェラート職人の磯部浩昭さんを招き、会場でワインとジェラートをふるまいました。
その館はファッションがメインなので、食に関心の高い顧客を新たに呼び込む上で、稀人の貢献は大きかったと思います。稀人たちにとっても、百貨店とのつながりや今回のイベントを通して生まれた出会いは今後に活かせるものと考えています。来場いただいたお客様にとっても有意義な時間になったと思います。もちろん、僕自身も楽しかった。そんなわけで稀人×企業の活動は、企業と稀人双方とお客様、そして僕にとっても価値がある取り組みという意味で「四方よし」と呼んでいます。
―今後、どのような活動をしていきたいですか。
これまで稀人の素晴らしい取り組みを多くの方々に知ってもらいたいという思いで取り組んできました。僕は稀人の活動を応援したい。その根本はこの先も変わりません。僕は取材をして原稿を書くことに加えて、朝活やマルシェなどのアイデアを考えたり、イベントを企画するのが好きなんです。これからも稀人たちと一緒に「四方よし」の活動を続けていきたいですね。

常識はずれで型破りな探求心で未知の扉を開く稀人たちに出会ったとき、川内さんは「脳みそが沸騰するような喜び」を感じ、心を奪われるそうです。
誰も歩んだことのない孤独な荒野にいながら、自身の情熱に突き動かされるままに一歩を踏み出し、他にはない独創的な提案をする稀人のキラリと光る魅力。それは多くの出会いと経験を通じてアンテナと感性を磨いてきた川内さんだからこそ見出せるのかもしれません。稀人を見つけるだけでなく、その独創性や情熱の価値を理解し、広める架け橋になっている川内さんの発信を、これからも楽しみにしています。
