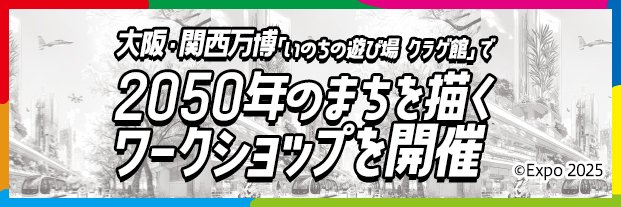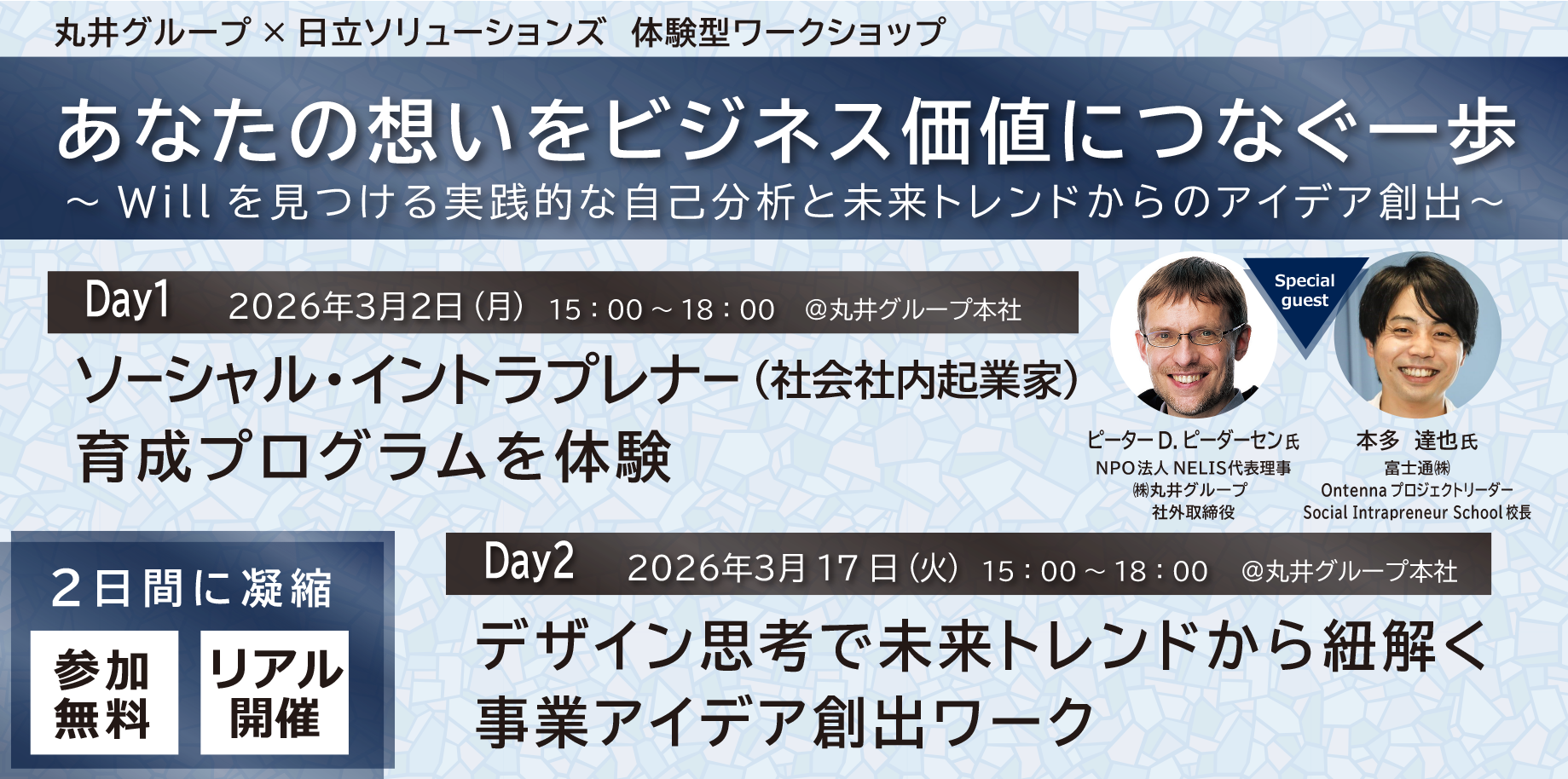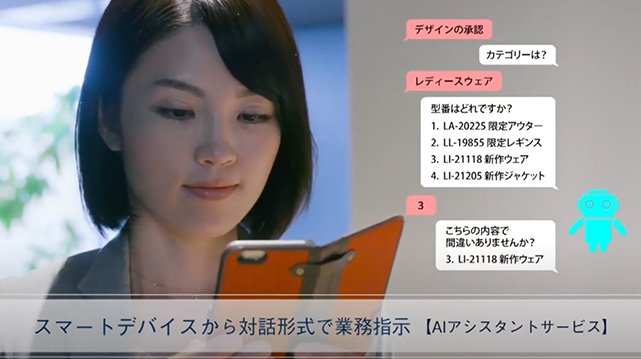※本記事は2022年7月に掲載されたものです
壊れたものを再生させて未来に引き継ぐ
 1968年千葉県生まれ。多摩美術大学でガラス工芸と陶芸を学ぶ。卒業後、いけばな草月流の陶芸教室の助手として花器やオブジェ製作の指導に当たる。2011年の東日本大震災をきっかけにワレモノ修理プロジェクト「モノ継ぎ」を開始。著書に『繕うワザを磨く 金継ぎ上達レッスン』(メイツ出版)がある。 |
ジョージア(旧グルジア)が舞台の映画『金の糸』が日本で公開されたのは2022年2月である。91歳の女性映画監督ラナ・ゴゴベリゼ氏は、日本の金継ぎの技術に着想を得てこの作品をつくった。陶器や磁器の割れ、欠け、ひびを、漆を用いて修繕し、そこに金粉をまぶして美しく仕上げる──。日本独自のこの技術は、海外でも「Kintsugi」として広く知られている。
「西洋にも器を修繕する技術はありますが、修繕後に日常使いに戻すことは基本的にありません。金継ぎで漆を使うのは、直した後に再び使えるようにするためです。自然素材である漆なら、人体への影響はありませんから」
年間300近い器を金継ぎによって再生させている持永かおり氏はそう話す。金継ぎが独特なのは、割れやひびの跡をあえて顕在化させ、一種の意匠とする点である。破損というアクシデントによって生まれる偶然の美。それが金継ぎの魅力だと持永氏は言う。
「壊れたこと、傷ついたことをなかったことにせず、生まれ変わらせて、生活の中で使い続けるところに美意識を感じます。人は挫折したり、失敗したりすることで魅力的になっていきますよね。それと同じだと思うのです」
2つの伝統の技で器の命をよみがえらせる

左/細い筆で「絵漆」を継ぎ目に塗っていく。全工程中、最も緊張する作業だ
右/漆を硬化させる「漆風呂」。湿度を一定に保ち、漆を安定的に硬化させる |
漆は、樹齢10年超の樹木から1年だけ採取することができる貴重な素材だ。1本の木から採れる量はおよそ200ml。牛乳瓶1本程度である。その天然の漆から夾雑物(きょうざつぶつ)を取り除いた「生漆(きうるし)」に小麦粉や米粉を混ぜて粘性を加え、接着力を高めるところから金継ぎの作業は始まる。小麦粉を混ぜた漆を「麦漆」、米粉を混ぜた漆を「糊漆」という。
その漆で割れた器の破片を接着させ、時間をかけて硬化させる。その後、表面を研磨し、漆で隙間を埋める作業を何度も繰り返す。漆は周囲の空気中の水分を吸収しながら硬化する性質を持つ。湿度を70%以上に保ちながら、およそ1カ月の時間をかけて硬化させる。硬化には「漆風呂」もしくは「むろ」と呼ばれる木箱が用いられる。

絵漆を塗った継ぎ目に、粉筒で金粉を蒔(ま)く。粒度の異なる金粉を2回に分けて蒔くことで、金の密度を上げていく
|
器の修繕自体はこの作業で完了するが、金継ぎの工程が佳境に入るのはここからだ。継ぎ目に金の「化粧」を施していく作業である。
酸化第二鉄から作る顔料である弁柄を漆に混ぜ合わせた「絵漆」を細い筆につけ、継ぎ目のラインを丁寧になぞっていく。弁柄を加えるのは金の発色を良くするためだ。「全工程の中で一番緊張する作業」と持永氏は話す。
続いて、筆で塗った漆の上に、粉筒を使って金粉を蒔(ま)き、さらにより細かな金粉を蒔いて微細な隙間を埋める。その後、刷毛(はけ)で余分な金粉を払い、2~3日硬化させる。生漆で金粉をコーティングし、それが乾き切ったら、車の塗装などの際に使うフィルム研磨剤と「鯛牙(たいき)」と呼ばれる鯛の歯で表面を磨く。最後に、焼いた鹿の角を粉末状にした「艶の粉」で磨き上げる。これで金継ぎの作業は完了する。
縄文時代に始まったといわれる漆を使った修繕の技術と、平安時代に始まったといわれる金粉をあしらう技術。その2つの伝統の技を緻密に組み合わせて、器の命をよみがえらせる。器は新たな装いを得て、再び使い手の日常生活の一部となる──。まさしく日本人の美意識が結晶した匠(たくみ)の技というべきであろう。
一つひとつの器にかけがえのない物語がある

左/はみ出した漆は、ナイフで丁寧に削り取っていく
右/金粉をコーティングした漆が硬化したのちに、鯛の歯で表面を磨く |
美術大学でガラス工芸や陶芸を学び、卒業後は華道の師範を対象とした陶芸教室の講師をしていた持永氏が金継ぎを始めたのは、ささやかな出来事からだった。
「自宅で使っていたご飯茶わんを割ってしまったんです。陶芸教室でも割れた花器などを修繕することはよくあったのですが、人の口に触れるものではないので、合成接着剤を使うことができました。でも、食器の修繕に合成接着剤を使うことはできません。それで着目したのが金継ぎでした。その頃は金継ぎに関する書籍や教室はほとんどなかったので、たまたまラジオで知った金継ぎキットを購入して、試行錯誤しながら食器を修繕しました」
そのDIYの作業を通じて金継ぎの面白さを知り、友人の食器も直すようになった頃に起きたのが、2011年3月11日の東日本大震災だった。
「地震が起きてすぐ、北海道に住んでいた友人がアートレスキューの活動を始めました。アート作品を販売して、その売り上げを被災地に寄付する取り組みです。私も声をかけられたのですが、出展できるような作品はありませんでした。でも、"直す"ことならできると考えたのです。被災地では多くのものが壊され、たくさんの人が傷ついていました。だからこそ、"直す"ことに意味がある。そう思ったのです」
 |
器の修繕をし、その修繕費を寄付する。そんな活動を始めるにあたって掲げたのが、現在も使っている「モノ継ぎ」という屋号だった。壊れてしまった大切なものを丁寧に直し、未来に引き継いでいく──。そんな思いを込めた屋号だ。その時には修繕の依頼はなく、寄付金を集めることはかなわなかったが、それがプロの金継ぎ師としての活動のきっかけとなった。
セレクトショップで修繕を受けつけたり、ウェブサイトを開設したりする一方で、漆を使った芸術である蒔絵(まきえ)の技法を学び、金継ぎのスキルを磨きながら修繕の依頼を募っていった。本格的に金継ぎに取り組んでみて、「ニーズが多いことに驚いた」と持永氏は話す。
「100円ショップで買った器、夫婦の思い出のペアカップ、子どもからのプレゼント、祖父母から受け継いだ食器と、とにかくいろいろなご依頼がありました。壊れても捨てられないもの、ずっと大切にしたいものが誰にでもあるんですよね。一つひとつの器にかけがえのない物語があることを知りました」
割れの修繕には数万円の費用がかかる場合もある。依頼が多いため、申し込みから納品まで半年から1年は待たなければならない。しかし、どれだけお金と時間がかかっても大切な器を直したい。そんな思いを持った人が全国にいる。

器の形状や割れ方は一つひとつ異なる。特徴や必要な作業を付箋に書き込んで貼り付けておくこともある。1つの器の修繕に2カ月はかかるという
|
「襟を正さなければならないと感じます。1人でやっている仕事ですから、手を抜ける余地がないわけではありません。でも、絶対に手は抜かないと決めています。材料にこだわり、今の私にできる最高の水準で仕上げることで、お客様の思いに応えたい。そう考えています」
金継ぎによって再生した器は、決して完全に元に戻ったわけではない。レンジで加熱したり、粗雑に扱ったりすれば、再び壊れてしまう可能性がある。
「疵を負っているからこそ、優しく、丁寧に扱うようになるわけですよね。それも金継ぎで修繕することの一つの意味だと思うのです。直しながら使い続けることで、ものを大切にする気持ちが生まれ、それが人を大切にする気持ちにもつながるのではないかって」
日本人が数世紀も前に壊れた器を金でつなぎ合わせるように、金の糸で過去をつなぎ合わせるならば、過去は、その最も痛ましいものでさえ、財産になるでしょう──。『金の糸』のラナ・ゴゴベリゼ監督は、作品のウェブサイトにそんな言葉を寄せている。大震災という「痛ましい過去」から始まった持永氏の金継ぎの営みによって、数多くの器がよみがえり、ものの命がつながれていく。縄文時代から受け継がれてきた伝統の技術は、未来を創る技術でもある。

金継ぎで仕上げた様々な器。金粉ではなく、銀粉を使う場合もあり、それは「銀継ぎ」と呼ばれる。
銀の発色を良くするために、金継ぎとは異なる調合の漆を用いる |
東京・世田谷のご自宅兼仕事場でインタビューと撮影をさせていただきました。素材や工程の話、金継ぎにかける持永さんの思いをお聞きしながら、ものを直して長く使い続けることの大切さを深く実感しました。現在の夢は、壊れた器を買い取りアート作品として販売するプロジェクトを立ち上げることだと持永さんは言います。ゆくゆくは器だけでなく、家具や洋服を再生させる活動に各ジャンルのプロと一緒に取り組んでみたいとも。金継ぎのような「修繕の文化」は、サステナビリティやSDGsが人類共通の目標となっているこの時代にこそ求められていると感じました。