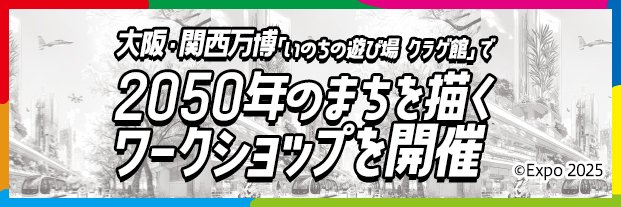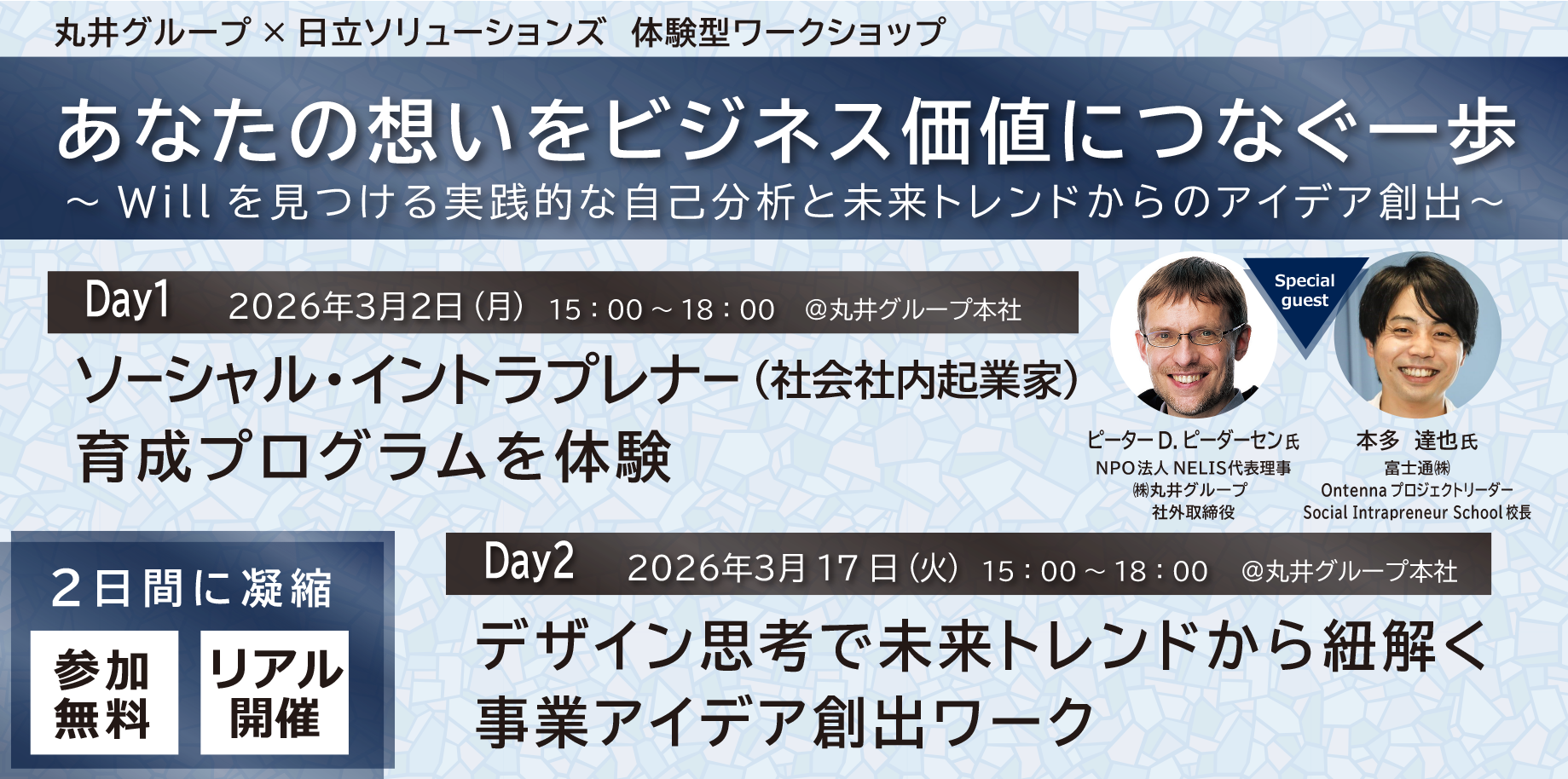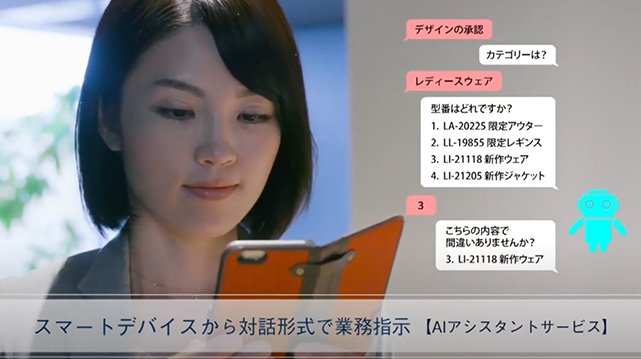※本記事は2021年8月に掲載されたものです
家康の命で本格的に始まった七宝焼づくり
 1953年東京生まれ。大学卒業後に七宝焼職人の父のもとで本格的な修業を始める。2005年、東京都伝統工芸士に認定。11年に「東京の伝統工芸品チャレンジ大賞」優秀賞を、13年にはグッドデザイン賞を受賞している。 |
金、銀、銅などの金属の光沢と、200色に及ぶガラスの鮮やかな彩り。その二様の輝きを融合させた伝統工芸が七宝焼である。大小の金属器にガラス質の釉薬(ゆうやく)を溶着させる技術の発祥は、千数百年前まで遡るといわれる。「七宝」とは、仏典にある7つの宝、すなわち金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、硨磲(しゃこ)、珊瑚(さんご)、瑪瑙(めのう)を意味する。それほどの多彩な輝きを持つ工芸品ということだ。
これまでに出土している最古の七宝焼は、キプロス島のミケーネ人の墓からでた笏(しゃく)で、紀元前13世紀のものとみられている。七宝焼の技術はその後、中近東からシルクロードを通って朝鮮半島や日本にまで伝わった。はるか距離を隔てても、金属にガラスを盛って焼成するという七宝焼のつくり方自体に大きな変化はなかった。

「絵具」とも呼ばれる釉薬。ガラスの原料である珪石が主成分で、種類は200色に及ぶ
|
我が国における最古の七宝焼は、奈良県の7世紀の古墳から見つかった金具だが、これが国内でつくられたものか、海外からもたらされたものかは判明していない。日本国内で七宝焼が最初につくられたのは安土桃山時代で、その技術は江戸時代初期に本格的に花開いた。
京都で金工師をしていた平田道仁(通称:彦四郎)が江戸に呼ばれ、徳川家康の命で七宝の技術を学んだのは江戸初期の慶長年間のことである。彦四郎に技術を教えたのは、朝鮮半島からの渡来人だった。
「それ以前の七宝焼は、"泥もの"といって、透明感のない釉薬を使ったものがほとんどでした。しかし、彦四郎がつくる七宝の刀の鍔(つば)や馬具は、ガラスの透き通った美しさを活かした、それまでにない七宝焼でした」
東京・南千住で40年以上にわたって七宝焼をつくり続けている畠山弘氏はそう解説する。その彦四郎がつくった七宝焼から、現在に至る東京七宝の歴史が始まった。
色彩の美しいコントラストと光沢

左/釉薬を盛る前の酢洗い。これによって表面の油分を取り除き、釉薬を定着しやすくする
右/多少の水分を加えながら釉薬の粗い粒子をすり潰してペースト状にしていく |
新潟から上京して七宝焼職人となった父と同じように、自分も七宝焼のプロになりたい。そう畠山氏が考えるようになったのは高校時代だった。
「小さい時から父の仕事を傍らで見ていました。七宝焼の素晴らしさは、色彩の美しいコントラストや、色ごとの光り方の違いにあります。父がつくる七宝焼を見て、こういう作品を自分もつくってみたいと思いました」
大学卒業後に父に弟子入りし、20代後半で父に代わって家業を主に担うようになった。
「本来は、1人で七宝焼をつくれるようになるまで10年はかかります。私は6年くらいで一本立ちすることになったので、腕を上げるために夜遅くまで必死に働いたものです」
七宝焼づくりは、ベースとなる金属器をデザインするところから始まる。そのデザインを基に金属の器体をつくるのは彫金師の仕事だ。器体の素材で最も多いのは、銅に亜鉛を配合した丹銅で、まずはその表面の油を落とすために空焼きをし、塩酸水などで洗う。この作業を「酢洗い」と呼ぶ。
 |
そこに様々な色彩の釉薬を盛り付けていく作業からが七宝焼職人の腕の見せどころだ。七宝焼に使う釉薬は、ガラスの原料である珪石(けいせき)に金属を混ぜて色を調合したもので、配合する金属の種類や量によって色が変わる。色が200種類に及ぶことは先に記した通りだ。釉薬はまた透明度によって、透明、半透明、不透明の3種類に分けられる。
釉薬は、仕入れた時の状態は粗い粉末である。これをすり鉢で擦って粒子を細かくし、少量の水を入れてペースト状にしていく。この作業を「こなし」という。そうしてペースト状になった釉薬を、細いへらを使って金属の凹みに盛り付けていく。
その後、釉薬を定着させるために800℃くらいの温度で焼き、酢洗いをする。一色を盛るたびに、この作業が何度も繰り返される。

銀製の器体にへらを使って様々な色の釉薬を盛っていく。指輪づくりのワンシーン
|
すべての色の盛りと焼成、酢洗いが終わったら、七宝焼づくりで一番難しいという研磨の作業に入る。研磨の目的は、はみ出している釉薬を取ることと、張力によって盛り上がっている釉薬の表面を平らにすることだ。目が細かく柔らかい砥石を回転させ、微かなはみ出しや盛り上がりを、慎重に力を調整しながら磨いていく。まさに熟練の技である。
「一人前の七宝焼職人になるためには、すべての工程においてベストな"加減"を感覚でつかめるようにならなければなりません。釉薬の盛り加減、焼き加減、磨き加減。それが分かるようになるまで、数多くの仕事をこなす必要があります」
革新に向けて舵を切っていく

釉薬を盛った後に、電気炉で800℃以上の温度で焼成し、釉薬を溶着させる
|
1代目の時代は、ほぼ全量が受注生産だった。記念品、プレゼント、社章、家電のエンブレム──。高度成長時代はそのような注文が引きも切らず、商売は繁盛した。1964年の東京五輪の五輪マークを七宝焼でつくったこともあったという。
注文が徐々に減ってきたのは、金属に樹脂で色づけした商品がつくられるようになってからだ。樹脂を使ったアクセサリーやエンブレムは質感や重厚感において七宝焼に及ぶべくもないが、安価で大量につくれるというメリットがある。
「父が亡くなってから、これまでと同じやり方でいいのかとずいぶん悩みました。注文が来るのを待つだけでなく、自分の作品をつくって販売していく道もあるのではないか。そう考えて、父がやっていなかったオリジナルアイテムの製作を始めるようになったんです」

葛飾北斎の天井絵「睨み鳳凰」をモチーフとしたブローチ。このような「和物」のアイテムも数多く手がける
|
父は仕事が速く、一つひとつの作業も的確だった。2代目である自分は、仕事は決して速くはないが、粘り強さや根気強さがある。そう畠山氏は自己分析をする。また、「物事を簡単に考える」のも自分の強みだという。
「難しく物事を考えると、尻込みしてしまいますよね。どんなものでも、まずは"できる"と考えて、チャレンジしてみることが大事だと思っています」
そんな前向きな姿勢によって身に付けたのが、プリカジュールの技術だ。プリカジュールとは、19世紀末から20世紀初頭のアールヌーボーの時代に主に欧州で流行した技法で、スケルトンになった金属の枠の中に釉薬を定着させたものだ。土台に釉薬を盛る一般的な七宝と異なり、表面、裏面ともガラスが露出するので、ステンドグラスのように透き通って見えるのがプリカジュールの大きな特徴である。東京の七宝焼職人の中でこれをつくれるのは畠山氏だけだという。
「日本のものづくりの伝統をこの先につないでいくには、今までの技術にとらわれず、新しい視点でものをつくっていくことが必要だと思っています。伝統の中だけにとどまるのではなく、革新に向けて舵を切るということです」

注文でつくったエンブレムの数々。左端は、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」をあしらったもの。畠山氏の自信作の一つだ
|
その革新の試みの一つがプリカジュールだった。近年取り組んでいる雛人形とのコラボレーションなど、他の伝統工芸との組み合わせもまた革新の方法の一つだと畠山氏は言う。
現在のアイテムの売上数は、ピンバッジ、ネックレス、指輪がトップ3で、他に男性向けのカフスやネクタイピン、イヤリング、根付けや帯留めなどの和物アイテムも販売している。そのようなオリジナルアイテムづくりと、父の代から続く注文製作が現在の商売の2本柱だ。
近年のオリジナルアイテムの中では、妖怪のイラストをベースにした「妖怪七宝」や、東京都美術館の企画に出展してグッドデザイン賞をとった指輪のシリーズなどが人気を集めている。自分で考案するデザインのインスピレーションのもととなっているのは、シュールレアリスムの代表的な画家であるサルバドール・ダリの作品や、フランスのアクセサリー、そして自分が見た夢などだという。
「私がめざしているのは、"楽しめる七宝焼"をつくることです。伝統工芸はこれまで、きれいさ、美しさ、精巧さなどで評価されてきました。それらももちろん大切な価値ですが、私がつくりたいのは、身に付けると楽しくなったり、ウキウキしたりする。そんな七宝焼です」

すべての釉薬を盛った指輪を砥石で慎重に磨いていく。最も熟練の技を必要とする工程だ
|
東京七宝の組合には最盛期には70人ほどの組合員がいたが、現在は6人まで減っている。売り上げが落ちて廃業を余儀なくされた人もいるし、高齢を理由に引退していった人もいる。その中で今も仕事を続けられているのは、自分がつくったものを喜んでくれる人がいて、評価してくれる人がいるから。そう畠山氏は言う。
現在は、職人が1人、弟子が2人いるほか、娘も職人修業を続けている。カラーコーディネーターの資格を持つ娘が、七宝焼に新風を吹き込んでくれるのを期待していると話す。
「"畠山ブランド"が確立していくのはこれからです。喜んでいただけるものをつくって、七宝焼の素晴らしさをもっと多くの人に伝えていきたい。そう思っています」
 |
年が明けてから東京都心で本格的な雪が初めて降った1月末の寒い日に、ご自宅兼仕事場にお邪魔してインタビューと撮影をさせていただきました。七宝焼の工程を手取り足取り教えてくださっただけでなく、こちらの質問に当意即妙に答えてくださる様を見て、本当に頭の回転の速い方だと感じました。現在67歳とのことですが、「畠山ブランドが確立するのはこれから」と、20代の若者のようなビジョンを語る姿が本当にすがすがしく、このようなフレッシュな感覚によって伝統工芸は継承されていくのだなと思いました。これからも、新感覚の七宝焼をつくり続けていただきたいと思います。