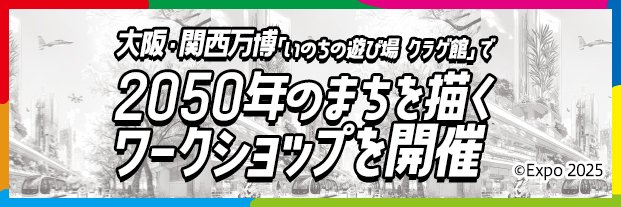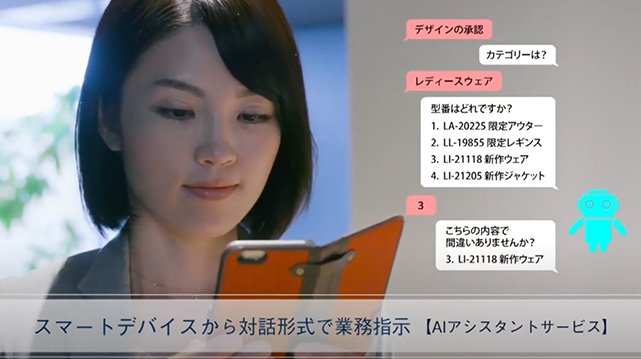※本記事は2020年7月に掲載されたものです
水草が揺らめき魚が泳ぐ小川の如く
 刀鍛冶師 |
「武家政権が誕生してこのかた、つまり源平の時代から幕末に至る長い間、刀剣は権力のシンボルであり至上の宝物であり、政治的駆け引きを含んだ贈答品、または恩賞品、献上品として欠くべからざる存在だったのです」(「小鍛冶」浅田次郎※1)
武器でありながら、シンボルや宝物「武にふさわしい美しさを持ち、恩賞品や献上品にふさわしい品格を持つ─。それが日本刀の唯一無二の魅力だ。鋭利な刃は触れれば切れる。その緊張感ゆえに美しく、その美しさゆえに見る人は襟を正さずにはいられない。そんな力が日本刀にはある。とりわけ、名刀と呼ばれる刀には。
「名刀とはどう使っても折れず曲がらず実用的であるばかりか、気品高く破邪降魔(※2)の威徳を感じさせる刀のこと」と歴史小説家の中村彰彦は書く(「名刀足るとは何か」※1)。
川﨑晶平氏を刀鍛冶の道にいざなったのも、そんな名刀の力だった。

上/川﨑氏の刀づくりは、鉄づくりから始まる。これは、原料となる銑(ずく)を卸鉄(おろしがね)の技法で、刀の材料となる鋼にしたもの
下/刀づくりの作業は「叩く」ことの繰り返しだ。金槌は最も重要な道具の一つである |
川﨑氏が日本刀づくりを志したのは、学生時代に上野の国立博物館で「城和泉正宗」を見てからだという。鎌倉時代につくられた国宝指定の刀である。九州・臼杵の古い武家であった父親の実家に刀や甲冑が残されていたこともあって、子どもの頃から刀に親しんできた。しかし、上野で見た正宗は、それまで見てきた刀とは別次元だったと川﨑氏は振り返る。
上からのぞく小川のように、底には小石があって、水草が揺らめき、魚が泳いでいるのが見える。それほどの透明感と奥行きが優れた刀にはある─。そう川﨑氏は表現する。そんな刀を自分でつくるべく刀匠をめざしたのだ、と。
千年の歴史を持つ日本刀づくりは、作風の違いによって大きく5つの流れに分けられる。大和伝、備前伝、山城伝、相州伝、美濃伝である。正宗から始まり川﨑氏がその流れに属する相州伝の特徴は、刃に沿って浮かぶ刃文にあらわれる「錵にえ」と呼ばれる粒子の輝きや、「地景」と呼ばれる黒い地金の色の華やかさなどにある。
「相州伝が生まれたのは鎌倉末期、武士に勢いがあった時代です。実用を追い求めた姿の無駄のない格好よさ。それが相州伝の刀の魅力です」
師匠からも故郷からも遠く離れて

川﨑氏の作業場。作業のほとんどは円座に座ったままで行われる
|
大学を卒業して就職した会社を1年で辞め、刀鍛冶への道を模索し始めたのは24歳の頃だった。どうすれば刀鍛冶になれるのかが分かっていたわけではない。アルバイトをしながら、弟子となれる機会を探した。道が開けたのは、長野の東急百貨店で開催されていた現代刀の展覧会に足を運んだ時だった。
「展示されていた中で一番いいと思った刀の作者が、ちょうどその日会場当番をしていた宮入小左衛門行平でした。弟子にしてほしいと頼み込んだのですが、その時は断られました。それでも諦めずに半年くらい手紙を送ったり仕事場を訪ねたりして、ようやく弟子入りを認められました」
1994年のことだ。修業はゼロからならぬマイナスからのスタートだったと振り返る。
「刀鍛冶の家に生まれた人なら分かるような基礎的なことも分からないし、弟子としての振る舞い方も分かりませんでした。内弟子ですから、師匠の家の雑用もしなければなりません。昼夜も土日も関係なく働き詰めで、もちろん給金もありません。特につらかったのは、自由が全くなかったことでした。そんなストレスがたまっていたんですね。師匠に反抗的な態度を取って、逆鱗に触れてしまいました」
弟子入りしてから3カ月での破門。故郷の大分に帰り、自分の気持ちが落ち着くのを待って、師匠に手紙を何度も書いて再度の弟子入りを請うた。
「それを何とか受け入れてもらってからは、心を入れ替えました。本物のプロになろう。一流になろう。その一念で修業に打ち込みました」

沸かした鉄を鉄床(かなとこ)の上で叩く。小さな水蒸気爆発が起こり、激しい音と共に火花が飛び散る。このような作業が何度も繰り返される
|
刀鍛冶は最低5年の修業の後、文化庁が主催する「美術刀剣刀匠技術保存研修会」を修了し、美術刀剣の製作承認を受けて初めてプロとして認められる。川﨑氏は、5年で刀づくりの基礎を身につけて、日本刀の作品コンクール「新作刀展覧会」で上位の賞を取ることを目標に定めた。もっとも、師匠は刀づくりのノウハウを手取り足取り教えてくれたわけではない。作業をはたから見て自ら学び取っていかなければならなかった。
「作業工程の一部は見せてすらもらえません。作業の後のゴミや、作業場の様子を見て、師匠がどのようにしていたかを想像するしかありませんでした。どんな道具を使ったのか。どういう姿勢で座っていたのか。どんな呼吸をしていたのか─。そんなことまで考えましたね」
そうして5年間の厳しい修業生活を終え、初出品した新作刀展覧会で志通りに優秀賞・新人賞を受賞した。師匠も独立を認めてくれたが、独立するには資金がなければならない。その後も4年間の御礼奉公をし、弟弟子の面倒を見ながら、自分の作品づくりに勤しんで資金をためた。
独立したのは2003年。師匠の家があった長野からも、故郷の大分からも離れた埼玉県の美里町に「晶平鍛刀道場」を開設した。それから17年がたつ。
最新作こそがいつも最高傑作

柄の中に入る部分を茎(なかご)という。そこに刀匠の銘が刻まれる
|
刀づくりは鉄づくりから始まる。鉄づくりにも様々な流儀があるが、川﨑氏は江戸時代中期以前の古鉄を集めて、それをリサイクルする卸おろしがね鉄という方法で主に原料の鋼をつくっている。それを火(ほ)床(ど)(炉のこと)で熱しながら(「沸かす」と表現される)炭素量を調整して、刀にふさわしい鋼に仕立てていく。1kgの刀をつくるのに必要なのは7㎏から8㎏の鉄だという。それを最も高温の時で1350℃~1400℃で沸かしながら、夾きょうざつぶつ雑物を落としていく。
そこから先は、鉄を繰り返し何度も何度も叩いていく。たばこの箱くらいの大きさに整えた鉄の塊を重ね、叩き、伸ばし、折り返し、さらに叩く。折り返しは6回から8回繰り返される。それによって、鉄の層ができ、「折れず、曲がらず、よく切れる」、すなわち柔軟性と丈夫さと鋭さを兼ね備えた刀となる。
刀身がある程度形となったら、焼刃土(やきばつち)を塗り、焼き入れという最も重要な工程に入っていく。焼き入れとは、刀を高温で熱してから急冷する作業のことだ。
これによって組織が変化し、硬度が増す。焼刃土は粘土や炭粉などを混合してつくった土で、これを薄く塗れば焼きが入りやすくなり、厚く塗れば入りにくくなる。その塗り分けによって一つの刀身の中に硬い部分と比較的柔らかい部分ができる。これもまた「折れず、曲がらず、よく切れる」刀を実現するための方法だ。
古代日本の刀は反りのない「直刀」だったが、鎌倉時代に入ると反りのある「太刀」や「打刀」が主流となった。その反りは、熱した刀身を水を張った桶に入れることによって生じる。そうして反りの入った刀身に粗研ぎを施し、彫りを入れるところまでが刀鍛冶の仕事だ。
「完成品としての刀は、鍛冶屋だけでつくれるわけではありません。研ぎ、彫金、木工、漆塗り、組紐づくりなど、8人ほどの職人が関わることによって、ようやく拵こしらえ(鞘、柄、鍔などの外装)のある刀が完成します」
独立してから17年、弟子入りから数えれば25年以上刀づくりに携わってきた。目標は千年先の未来にも残る刀をつくることだ。
「千年前につくられた古刀には何ともいえない生命力があります。歴史の中で数多くつくられてきた刀の中で、今日まで残っているものはごく一部です。生き残った刀には生き残っただけの理由があり、力があるのです。そのような力がある刀を私もつくりたい。そう思っています」
そのために必要なものとは何だろうか。素材か。技か。

上/鉄を沸かす際に使われる炭。これを均等な大きさに切るのも刀鍛冶の腕だ
下/水を張った桶に熱した刀身を入れることで「反り」が生まれる。水の温度は門外不出だという |
「最も大切なのは"自分がどうあるか"だと思っています。ものづくりが怖いのは、作品に自分自身のすべてが反映されることです。体が弱っていれば、刀も弱ります。気持ちが萎えていれば、刀からも覇気が失われます。だから自分を律し、常に自分自身を保つことが必要なんです」
もう一つの目標は、日本刀ファンの裾野を広げていくことだ。他の職人たちと共にアニメ『ヱヴァンゲリヲン』に登場する剣を再現した展覧会を行ったのも、柔軟な感性を持った若者や女性に日本刀の魅力を知ってほしかったからだ。毀誉(きよ)褒貶(ほうへん)の激しい試みではあったが、その挑戦によって確実に日本刀のファンが増えた実感があると話す。
現代において、日本刀はもとより必需品でもなければ実用品でもない。世の中に必ずしも必要のないものをつくっているからこそ、刀鍛冶には作家性が必要であると川﨑氏は言う。仕事がうまいだけの職人ではなく、過去の名刀をめざし、過去の名刀を超えるものをつくる。そんな作家でありたいのだと。
「最新作がいつも最高傑作─。そう胸を張って言える作家であり続けることが一番の目標ですね」
※1『名刀伝』(細谷正充編/ハルキ文庫より)から引用
※2邪道を打ち破り、悪魔を降伏(こうぶく)すること
 |
埼玉県北西部、群馬県との県境に近い美里町にある川﨑さんの自宅場兼作業場にお邪魔してお話を伺い、撮影させていただきました。最近では外国人観光客が訪れることも多いとのこと。作業を見学した後で、鉄を熱した炭を使って庭でバーベキューをするのが定番のコースになっているそうです。写真で見る川﨑さんは眼光鋭く、寄らば斬らなん、といった迫力がありますが、実際にお会いした川﨑さんは、物腰柔らかなジェントルマンで、いい意味でとても意外でした。しかし、ひとたび仕事場に入れば、まさしく勝負師の面構えとなって、鉄や火と向かい合うのでした。日頃ほとんど接することのない日本刀の奥深い魅力を知ることができた本当に意義深い取材でした。