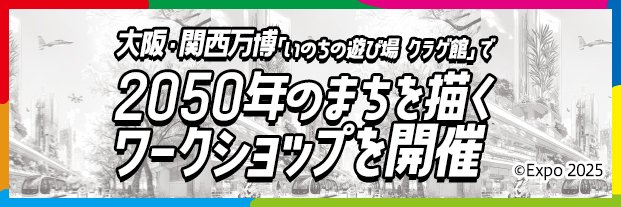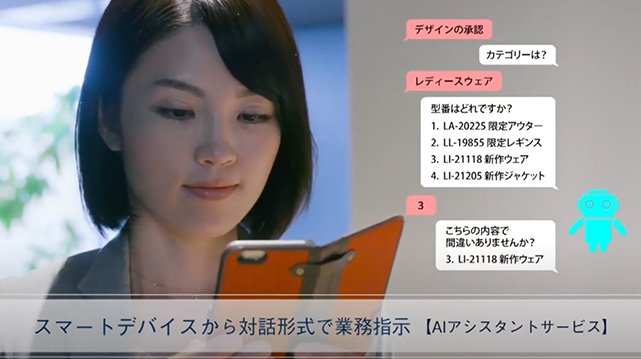※本記事は2020年5月に掲載されたものです
武家と町人の合作として生まれた文化
 江戸手描き鯉のぼり職人 |
鯉のぼりを掲げる風習は、江戸期の武家と町人のいわば合作として生まれたものであった。湿気が多くなる五月に、菖蒲の葉や根を酒に浸した菖蒲酒を飲んで毒気を払うという風習は奈良時代に中国から伝わったもので、江戸時代になって、菖蒲が「尚武(武を尚ぶ)」や「勝負」に通じることから男子の節句となり、武家では家紋を入れた旗指物や吹き流しを掲げるようになった。
それをまねたのが、富裕な町人層だった。彼らは和紙で鯉をかたどった幟を吹き流しとともに高く掲げた。当時は鯉のぼりづくりの職人がいたわけではなく、絵の達者な町人が鯉のぼりづくりを担ったようだ。紙製だから長持ちはしない。毎年の鯉のぼりの新調もまた恒例の行事だったのだろう。鯉のぼりは後に、家の跡継ぎとなる男子が生まれたことを地域に示す意味も持つようになった。

鱗模様を丁寧に描きこんでいく。彩色は淡い色から濃い色に進んでいくのが基本だ。金の彩色は最後になる
|
幟に鯉をあしらったのは、中国の故事にちなんだものだ。黄河中流にある竜門と呼ばれる滝を鯉が力強く登って、登り切ると龍に変じたというのがその故事で、功成り名を遂げ成功するための関門を「登竜門」と呼ぶのはこの物語による。町人たちは鯉に男子の立身出世の願いを込めたのだった。
百瀬(ももせ)の滝を登りなば
忽ち龍になりぬべき
わが身に似よや男子(おのこご)と
空に躍るや鯉のぼり
大正初期に当時の尋常小学校の唱歌となった「鯉のぼり」には、こんな歌詞も見える。

縫製を丹念に行うのも秀光人形工房の鯉のぼりづくりの流儀だ。手縫いとミシン縫いを組み合わせながら強度を出す。「縫製はどこにも負けない」と三代目は話す
|
その登竜門の故事を吹き流しに最初に描いたのが、江戸手描き鯉のぼり職人の初代川尻金龍だったという。呉服職人であった初代金龍は、元来の絵画の才能を活かして、力強く跳ね泳ぐ鯉とうねるように舞う龍をあしらった吹き流しと、鮮やかな彩色の鯉のぼりをつくった。その作品は昭和の世にあって大ヒット商品となり、男子を持つ家庭の多くが買い求めた。五月に鯉のぼりを掲げる風習がしっかりと残っていた時代の話である。
初代金龍の作品は手描きによるものだったが、当時から「捺染(型染め)」による大量生産の鯉のぼりづくりもあって、二代目金龍の時代になってからはすべてが捺染によってつくられるようになった。ナイロン布にパターン模様が描かれた私たちがよく知る鯉のぼりである。
そうして江戸手描き鯉のぼりはいっとき途絶えることとなった。それを復活させたのが三代目金龍氏である。実に35年ぶりのことであった。
手描きの手本は初代の「失敗作」

吹き流しの制作風景。墨色で線を描き、十分に乾いてから彩色を施していく。絵は初代のタッチを参考にしている
|
「初代金龍が描いた鯉のぼりや吹き流しは抜群にかっこよかったんです。他のものとは全然違いました」
二代目金龍の長女であり、まだ20代の三代目はそう話す。初代との間に血のつながりはなく、浅草で工房を構えていた初代のもとに二代目が弟子入りして後に名を継いだのだという。
幼い頃から父の仕事を傍らで見て、12歳から仕事の手伝いを始めた三代目が本格的に鯉のぼりづくりの修業を始めたのは、美大の学生になった18歳の時だった。父が属する秀光人形工房で、初めは布の縫製を学び、並行して鯉の絵を描く練習を続けた。
しかし、父がつくる鯉のぼりは捺染のみであり、周囲にも手描きで鯉のぼりをつくる職人は皆無であった。手本となるのは初代が残した「失敗作」だけだった。
「うまくいったものはすべて販売してしまっていますから、残っていたのは商品にならなかったものだけでした。図面もありません。残された失敗作を見ながら、線のタッチや色のニュアンスなどを学んでいきました」

完成品に記された「三代目」の銘。ひと目で三代目が手がけたことが分かる作品を作ることがこれからの目標だ
|
その練習が実を結んだのが25歳の時だった。「多満自慢」の銘で知られる東京・福生の老舗酒蔵の石川酒造から手描きの鯉のぼりのオーダーがあった。
「このチャンスを活かさない手はないと思って、ぜひ私にやらせてほしいと父に言いました。それが私の江戸手描き鯉のぼり職人としてのデビュー作になりました」
以後、三代目金龍として手描きの鯉のぼりづくりを続けて3年ほどになる。
鯉のぼりのサイズは、80㎝から10mまで。作業台に綿布をつけるところから手描き鯉のぼりづくりは始まる。布は目が細かく、漂白し過ぎていないものが好ましいという。布の張り方は難しく、引っ張り過ぎると、絵が完成した時にゆがんでしまう。
さらに難しいのは染料の調合だ。自身で糊とインクを混ぜて調合を行うが、天候によって最適な調合の仕方が変わる。発色が良くにじみの出ない染料にするのにいつも苦労すると三代目は話す。

線の微妙なかすれは手描きでしか出せない味わいだ
|
筆は、市販のものの毛先を切るなど独自のアレンジを加えたものを使う。100円ショップで購入したものなどもあるという。かつては黒と赤くらいの色しかなかった鯉のぼりを多色化し、緑、青、黄、紫といった色鮮やかな鯉のぼりをつくったのは初代金龍だった。三代目もそれに忠実に、12色のインクを駆使して鯉のぼりと吹き流しを描く。色がくすむので、インクを混ぜ合わせることはない。
軽く下書きし、縫製のガイドとなる線を入れた布に、墨色で線を描き、さらに色が薄い順に彩色していく。線の強弱、染料の微妙な擦れ、グラデーション──。そのいずれも捺染では生み出すことのできないニュアンスである。そこから鯉の生命力が発し、龍の躍動感が生じる。
「父のアドバイスで、鯉が泳いでいるところを観察しながら、絵を描く練習もしました。実際の鯉の生命力を再現したいといつも考えています」
時代に合った描き方や色の選び方が必要

染料はその日の天候などに応じて調合を変える。現在使用しているインクは12色
|
高度成長期の頃と比べれば、鯉のぼりの市場は30分の1程度に縮小しているとみられている。その最大の理由は住宅事情だ。集合住宅で大きな鯉のぼりを掲げることは難しく、戸建てでも大きな庭を備えた家は都会には多くない。二代目金龍の時代にすべて捺染の鯉のぼりとなったのは、市場が縮小する中で手間のかかる手描きでは採算が合わなくなったからだった。
しかし、最近になって手描きの鯉のぼりの良さを見直す動きが出てきていると三代目は話す。秀光人形工房で販売する鯉のぼりの9割は依然捺染によるものだが、25万円から75万円もする手描き鯉のぼりへの引き合いも毎年確実にあるという。
「子どもの時に初代金龍が描いた鯉のぼりを見た記憶があって、自分の孫にも手描きの鯉のぼりを贈りたい。そう考えるお客様も少なくないようです」
三代目自身も、初代が描いた鯉のぼりが大空を雄大に舞う様子を仰ぎ見たことが原体験となっている。
「鯉のぼりを朝夕に上げ下げするのは面倒な作業です。でも、鯉のぼりが風に舞う姿を見るのは、本当に気持ちがいいものです。昔からの日本の風物詩が廃れてしまうのはとても寂しいと思います。この伝統を何とか守っていきたいですね」
伝統を守るためには、「選べること」が大事であると三代目は言う。比較的安価で買える捺染の鯉のぼりがあり、値段は高めだが一つひとつオーダーメードでつくられる手描きの鯉のぼりがある。そこから、住宅事情や子や孫への思いに応じて選んでもらえればいい。鯉のぼり文化の層を厚くするためにも、手描きの鯉のぼりは必要であるということだ。
鯉のぼりは商品であって芸術作品ではない。だから、「お客様にいかに喜んでもらえるか」という意識を忘れてはならない。初代の鯉のぼりの再現が現在の目標ではあっても、時代に合った描き方や色の選び方も必要になるはず──。そう三代目は話す。

筆は部位によって使い分ける。大胆な筆遣いで鯉の生命力を表現する
|
「そこから私の個性のようなものも表れてくると思うんです。三代目が描いた鯉のぼりだとひと目見て分かっていただけるような個性が自然に出てくればいい。そう考えています。そのためには、もっともっと腕を上げていかなければなりません」
伝統のものづくりは、市場が拡大していく世界ではない。現状を維持すること自体が難しく、努力を怠っては文化が絶えてしまう。そんな世界である。日本で唯一となった江戸手描き鯉のぼり職人の三代目金龍氏の最大の目標は、手描きの作品づくりを続けることによって、鯉のぼりの文化を継続させていくことだ。
「新しい鯉のぼりを描くたびに、初代が生きていたらなあと思います。自分で自分の作品を評価するのはとても難しくて、いつも何が正解なのかが分からなくなってしまいます」
すでにいない人を師匠にしなければならない。そんな厳しさに立ち向かいながら、三代目は今日も技を磨き続ける。
 |
千葉県市川市の秀光人形工房にてインタビューと撮影を行いました。ひな人形がずらりと並ぶ店舗の向かいにある倉庫が三代目金龍さんの作業場で、そこで実際に鯉のぼりと吹き流しに彩色をしていただきながら撮影をしました。子どもの頃から鯉のぼりづくりの職人になりたいと思っていたという金龍さんですが、独力単身で手描きの作品をつくり続けなければならないのは本当に大変だと思います。現在27歳。これからも素敵な鯉のぼりをたくさんつくって、それを目にする人たちを元気づけてください。