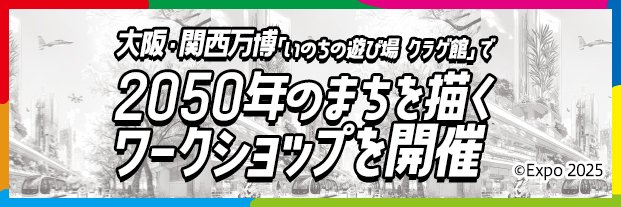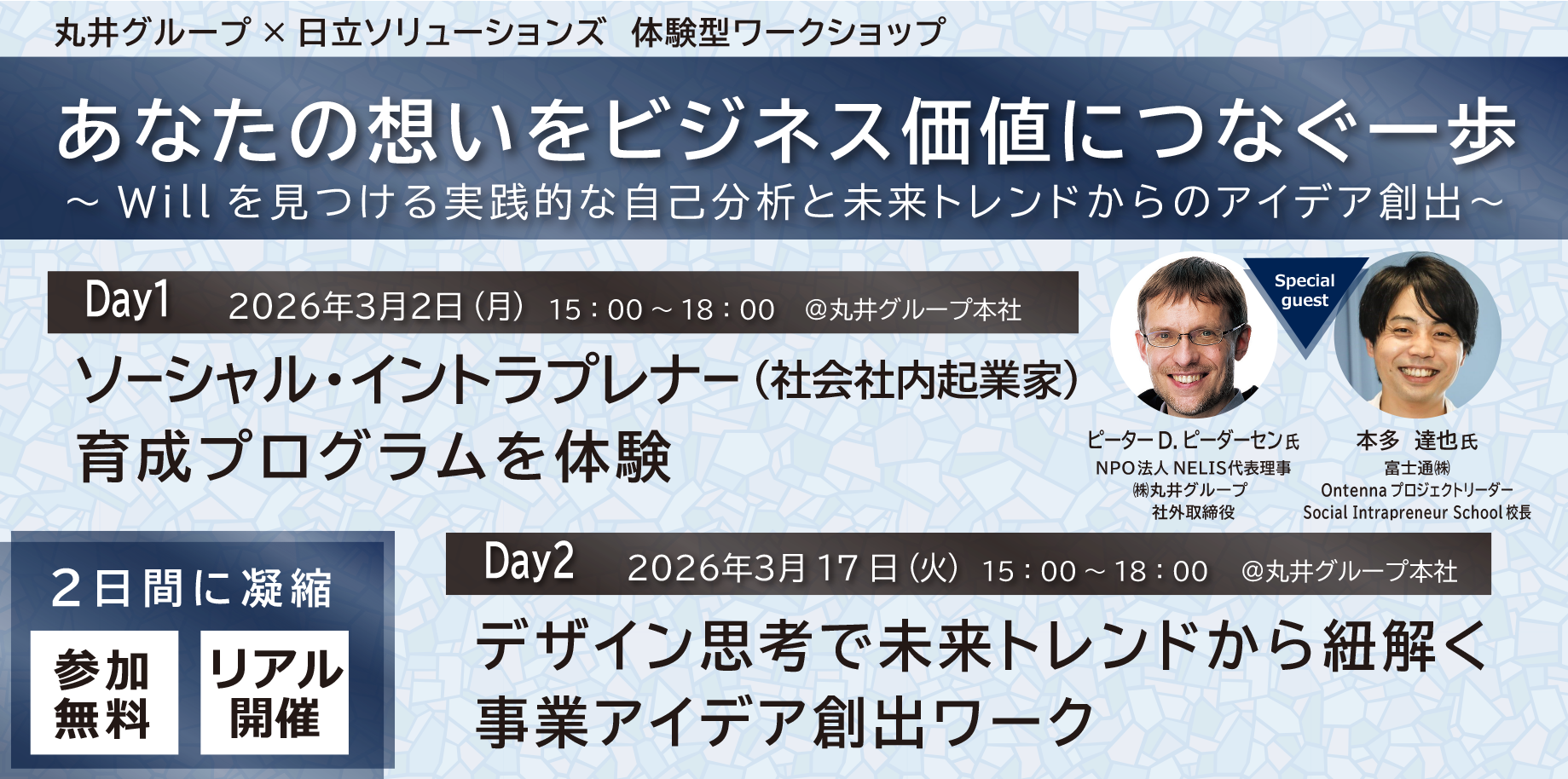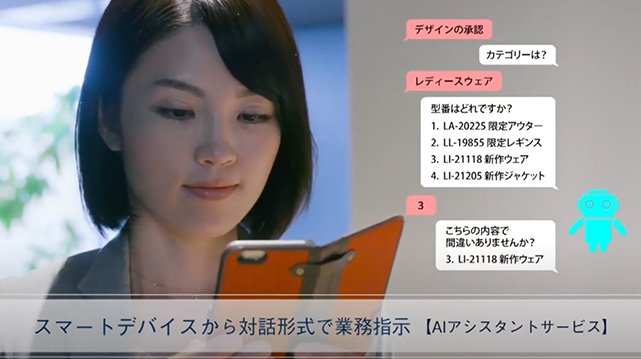※本記事は2019年9月に掲載されたものです
すべての部品の調和が生み出す独自の音
 亀屋邦楽器・前社長。東京都大田区(大森)生まれ。16歳で三味線づくりの修業を始め、28歳で独立する。以来、半世紀以上にわたって三味線づくりに取り組んできた。2010年、優れた技能者を表彰する「東京マイスター(東京都優秀技能者)」に選出。三味線の仕上げ工程の技術力と後継者育成の取り組みが評価された。現在の亀屋邦楽器の社長は息子の勇生氏。店舗は東京都世田谷区の経堂にある。 |
ただ一音を鳴らすだけで、周囲の空気の色を一瞬にして変えてしまう。三味線は、そんな魔力にも似た独特の音色を持つ楽器である。例えば、シタールの音がインドの風土や人々の感性と切り離すことができないように、時に繊細で時に激しい三味線の音は、日本人の美的感性の一部となっていると言っていいのではないだろうか。
中国の三弦が琉球に伝わり三線(さんしん)となり、それがさらに日本に伝わって独自に改良されたのが三味線であるといわれている。伝来地は大阪・堺、伝来時期は室町・永禄年間(1558~70年)というのがほぼ定説となっている。それ以前から日本にあった琵琶と同じ弦楽器だったこともあってか、琵琶法師が奏でることで三味線は徐々に日本各地に広まっていったようだ。現在でも、多く、語りや歌の伴奏に使われるところに琵琶法師の影響を見ることもできる。
長唄、小唄、端唄(はうた)、清元、常磐津、浪曲、新内(しんない)、義太夫、民謡、津軽など、三味線が使われるジャンルは現在に残るだけでも10種類以上あり、それぞれに求められる音色や音量が異なる。三味線をつくる職人も以前はジャンルごとに分かれていたが、需要が少なくなった現代では、一職人があらゆるジャンルに対応するのが一般的になっている。東京・世田谷で三味線づくりを続ける亀屋邦楽器の芝﨑勇二氏も、そんな職人の一人だ。

上/濡れた手ぬぐいに皮を包んで湿らせる。皮を張る作業に入る前に、湿気で柔らかくしておく
下/胴に糊をつける。糊の主原料はもち米。最近は化学繊維を多少入れる場合もあるという |
三味線づくりには、個別の技能を持った10人以上の職人が関わる。棹(さお)、胴、糸、皮、金具、糸巻き、音緒(ねお)、駒──。楽器を構成する各パーツをそれぞれの職人がつくり、組み立て専門の職人が楽器に仕上げる。芝﨑氏が担うのはその最終工程だ。
胴に皮を張り、棹に3つの糸巻きを取りつけ、胴と棹を組み合わせる。そこに絹をよってつくった3本の糸(弦)を張り、音を調整していく。こう言葉にしてしまえば、三味線はまるでプラモデルのように簡単に組み上がると誤解されてしまいそうだが、実際は、熟達した職人にのみ可能な極めて緻密な作業である。
それぞれのパーツの性格を見極め、最適なパーツを選択し、そのすべてを調和させて、演者から求められる音を実現する。最も難しいのは、胴に皮を張る作業だ。動物の皮革をなめした皮をもち米からつくった糊で胴に貼りつけ、「張り替え台」と呼ばれる台に固定し、ひもで引っ張って密着させる(写真)。皮の厚さは必ずしも均一ではないので、部分ごとにひもの張力を変えなければならない。
「三味線の音を左右するのが皮です。音の8割は皮張りで決まると言っていいでしょうね」
芝﨑氏はそう話す。三味線に求める音は顧客ごとに異なる。しかし、そのそれぞれの音のイメージをつかむのは簡単ではない。音を言葉によって過不足なく説明することは不可能だからだ。
プロの演者が顧客の場合、芝﨑氏はその人の演奏を聴きにしばしば足を運ぶ。舞台で奏でられた音をひとたび聴けば、どのような皮を選び、それをどう張ればいいかが即座に分かるという。しかし、それでも演者のイメージに合わない場合もある。

50年以上使用している張り替え台に皮を固定し、ひもで皮の張り具合を調整する。皮の厚さは均質ではないので、ひもの引っ張りの強さも部分ごとに異なる
|
「出来上がった三味線をお客様に渡して弾いてもらうでしょう。それで気に入ってもらえればいいですが、"この音じゃない"と言われてしまったら、もう一度皮をはがして、一から張り直さなければなりません。そういう厳しいお客様もいらっしゃいます」
もう一つ、三味線の音を決定するのが「さわり」と呼ばれる構造である。糸巻きが取りつけられた「天神」(ギターのヘッドに当たる部分)の根元に、糸を支える「上駒(かみごま)」と呼ばれる部品がある。棹と糸が直接触れることを防ぐパーツだが、最も太い一の糸だけをあえてその上駒から外し、棹と直接接触させているのが「さわり」である。これによって独特な響きが生じ、それが二の糸、三の糸と共鳴し、三味線の音の奥行きを生み出す。これは三味線の前身である三線ばかりでなく、世界中のどの弦楽器にも見られない独自の構造だ。棹を胴に取りつける角度などを調整し、最も響きのいい「さわり」をつくり出すのもまた、職人の高度な技である。
江戸時代末期から続く老舗三味線店

上/湿らせた皮を紙やすりで磨く。職人によっては軽石を使う。かつては職人それぞれの工夫を他人に教えなかったという
下/皮を挟むための木栓(きせん)にくさびを打ち込む。くさびの反対側に皮を挟む。くさびの打ち込み加減も職人の技の一つ |
亀屋邦楽器は江戸時代の末期から代々続く三味線店で、芝﨑氏で7代目になる。初代が東海道五十三次の第一宿である品川宿に店を出したのが始まりだという。
「三味線は花柳界のお座敷で主に使われていた楽器ですから、お座敷が多い宿場町に店を開くのは都合が良かったわけです」
芝﨑氏の父が独立して、東京・大森に店を構えたのは昭和23年(1948年)のことだ。息子は2人。芝﨑氏は弟だった。兄が18歳、芝﨑氏が14歳の時に父親が亡くなり、兄が大森の店を継ぐことになった。父と同じ三味線づくりの道に進むことを決めていた芝﨑氏は、やはり三味線職人であった叔父の家で住み込みの修業をすることになった。16歳の時だ。以後7年間修業生活を送り、さらに大森の家に戻って兄のもとで5年間働いた。28歳で結婚。それを機に独立して、世田谷の豪徳寺に自分の店を出した。
「最初の3年間は苦労しましたね。ゆかりのある土地ではありませんから、お得意のお客様がいるわけではありません。初めの頃は家にいても仕事がないので、毎日オートバイで大森の兄の店まで通って仕事をしていました」

天神。穴を空けて金具を付け、糸巻きをはめる。この糸巻きによってピッチを調整する。2本の糸の下にある金具が上駒(かみごま)
|
折からの民謡ブームもあって、その後、商売は次第に軌道に乗っていった。それから五十余年。今年(2019年)になって、隣駅の経堂に店を移した。社長の座は10年前に息子の勇生氏に譲ったが、三味線づくりのペースは今も変わらない。
「好きな旅行には前よりも行けるようにはなりましたが、それでも時間があれば仕事をしています。好きなんでしょうね、三味線づくりが」
三味線の良しあしを決めるのはお客様

左/天神の穴にはめられる太さに糸巻きを削る。以前は高級三味線では象牙が使われていたが、最近では黒檀を使ったものも多いという
右上/胴と棹のパーツをばらばらにしたところ 右下/棹は3つのパーツに分かれる。パーツの合わせが精妙なので、一見すると一体成形に見える |
職人に大切なのは、一に商売、二に技術──。そう芝﨑氏は言う。単に技術だけがあっても、仕事がなければその技術を人に見せることもできないし、腕をさらに磨くこともできない。だからまずは商売が大事なのだと。
「商いの才と、ものづくりの才。その両方がなければ職人を続けることはできないと思います」
自身は豪徳寺に店を構えてから、顧客との日々の相対の中で自然と商いを学んでいった。職人の腕の良しあしを決めるのも、出来上がった三味線の良しあしを決めるのもすべては顧客、というのが芝﨑氏の変わらぬ信念だ。
「三味線は、一丁一丁がすべて異なる楽器です。全く同じものは一つとしてありません。一人ひとりのお客様の好みに合わせて、この世に一つしかない三味線をつくっていくこと。それがあたしたちの仕事です」
店を経堂に移転した時に出した挨拶状は、実に2500枚。三味線を買った客、修理した客、常連、現在は付き合いのない客。そのすべてに案内を送ったという。いかに芝﨑氏が顧客を大切にしているかが分かる逸話だ。

上/巧みな指さばきで、糸巻きに糸を結びつけていく。糸の太さは楽器のジャンルごとに異なる
下/絹ひもで作られているのが音緒(ねお)。ここに3本の糸を結びつける。皮と糸の間にあるのが駒。固定せずに、微妙に位置を変えて音を調整する |
最近は、津軽三味線奏者の上妻宏光氏や吉田兄弟が海外で積極的に演奏活動を続けていることもあって、外国人が三味線に興味を持つようになっている。亀屋邦楽器にもしばしば外国人がやって来て、三味線を買っていくという。また、2000年代に入って小中高校の授業のカリキュラムに伝統楽器や伝統歌唱が組み込まれたことで、若者が三味線に接する機会も増えている。
顧客の層が変わり、顧客の好みが変わる。それに合わせて、ものづくりの在り方もおのずと変わらなければならない。そう芝﨑氏は言う。
「誕生してから450年の間、三味線の材質やつくり方は時代に応じて変わってきました。これからも、時代とともに変わっていくのだろうと思っています」
伝統的な三味線づくりでは、犬や猫の皮、象牙、クジラの骨など、現在では入手の難しい素材を使ってきた。最高級の三味線の棹に使われる紅木(こうき)の調達も年々困難になってきている。
素材が希少になり、調達が難しくなれば、楽器の値段も上がっていく可能性がある。現在は、1丁20万円から30万円が標準的な価格帯だというが、これを見直さなければならない時がいずれ来るかもしれない。
「だけど、あたしは値段を上げたくないんです。高くなったら、買える人が少なくなってしまうでしょう。多くの人に使ってもらって、多くの人に三味線を楽しんでほしい。それがつくり手の願いです」
伝統芸能から大衆芸能まで、様々な場面で奏でられ、独自の音で人々を魅了していた三味線。その「日本人の心の音」を後世に伝えていくためには、顧客に寄り添い、変化を受け入れなければならない──。そんな思いを胸に、今日も芝﨑氏は三味線づくりを続けている。
 |
開店してまだひと月という経堂の新店舗にてお話をうかがいました。芝﨑さんも、息子で現社長の勇生さんも、お話し好きの気さくなお人柄で、三味線づくりのイロハを一から丁寧に教えてくださいました。ご自身でつくった三味線を目の前で鳴らしてもらうと、その意外な音の大きさに驚きました。一人ひとりのお客様によって求めるものが異なるという三味線の音。それを生み出すのは、まさに熟練の技と、「お客様第一」という思いである。そんなことを強く感じさせられた意義深いインタビューでした。