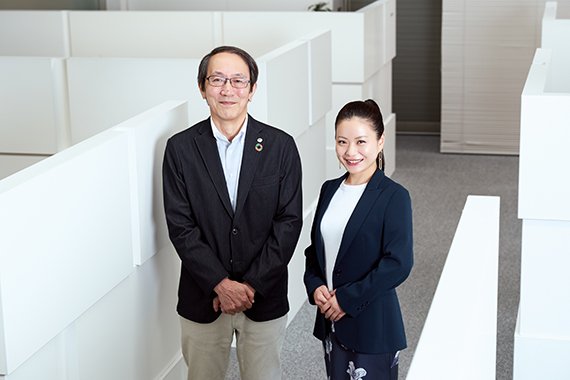AIが仕事の基礎ツールになりつつある今、人と人の結びつきが持つ意味とは何か─。AIソリューション開発を手がけるシナモンAIの平野未来社長と、日立ソリューションズの人事部門トップの半田浩晃が、「人の連鎖」が生み出す価値について語り合った。

平野 未来
株式会社シナモン
代表取締役社長 CEO
ひらの・みく
東京大学大学院修了。在学中にネイキッドテクノロジーを創業。世界経済フォーラムの「ヤング・グローバル・リーダーズ2022」に選出される。内閣官房IT総合戦略室本部員などの有識者会議のメンバーとしても知られる。

半田 浩晃
株式会社日立ソリューションズ
常務執行役員
はんだ・ひろあき
1987年に日立製作所に入社。以来、ほぼ一貫して人事部門で人財採用や育成に取り組んできた。中国法人での勤務を経て、2023年に日立ソリューションズの常務執行役員・人事総務本部長に就任。
半田:平野さんがAIの研究やビジネスに携わるようになったのは、いつ頃からなのですか。
平野:20年以上前です。「AI冬の時代」と言われていた頃から研究活動をしていました。その蓄積がシナモンAIのソリューション開発に活かされています。
半田:シナモンAIでは、どのようなソリューションを手がけていらっしゃるのでしょうか。
平野:代表的なプロダクトの一つが「Super RAG」です。これは、営業資料など社内の様々なビジネスドキュメントを取り込んで、社内専用の検索回答システムをつくることができるソリューションです。OCR(光学文字認識)の高度な技術によって、構造化されていないドキュメントを取り込むことができるのが大きな特徴です。
半田:業務が格段に効率化しそうですね。AIを仕事に有効に活かしていくには、それを使いこなせる人財が必要です。AI人財をいかに獲得・育成していくか。それが私たちの目下の課題です。2027年までに、日立グループ全体でAI人財を5万人に増やす目標を掲げています。
日立ソリューションズでは、開発業務などでのAI活用を推進しています。また、全社員を対象に現場でのAI活用アイデアを募集する社内コンテストを実施しています。予想を大きく超える1000件以上の応募が寄せられて驚きました。
平野:AI人財の育成は、多くの企業にとって必須の取り組みになっています。私たちの会社では、プロダクト開発にAIを活用することで、開発スピードがほぼ10倍になりました。現場の社員がAIを使いこなせるようになれば、仕事の生産性は大きく向上します。これからの人財育成において、AIをはじめとするテクノロジー活用を支援することは、欠かすことのできない要件になるのではないでしょうか。
半田:おっしゃる通りですね。テクノロジーを使いこなすのは、あくまでも「人」であり、会社の最大の資産は人財です。優れた人財と最先端のテクノロジーが結びつくことによって、会社の価値は間違いなく高まると思います。
同時に、一人ひとりの従業員の幸せも、会社を成長させる重要なドライバーになると私は考えています。従業員がいきいきと働ける仕組みや環境をつくり、幸せを実感しながら働けるようになることで、会社全体の業績が上がり、社会に提供できる価値も大きくなっていく─。そんな流れをつくることが理想です。
もちろん、一人ひとりが幸せになるためには、地球環境のサステナビリティ実現の取り組みも求められます。日立グループは、環境・幸福・経済成長が調和する社会を「ハーモナイズドソサエティ」と表現し、その実現に貢献することをめざしています。日立ソリューションズの人事部門の責任者として、私もその目標実現に寄与したいと考えています。
平野:AI時代だからこそ、人財の価値はいっそう高まっていると言ってもいいと思います。大切なキーワードは「意志」であると私は考えています。AIには意志や感情があるように見えることがありますが、あれは意志や感情がある「ふり」をしているにすぎません。本当に意志を持つことができるのは人間だけです。意志を持つこと、つまり、本当にやりたいこと、自分が実現したいことを明確にすることが、これからの時代にはより求められるようになると私は考えています。

半田:大変重要な視点だと思います。しかし、すべての人が明確な意志を持てるようになるのはなかなか難しいという気もします。
平野:簡単ではないですよね。例えば、「こうすべきである」という思考にとらわれていると、自分が本当に何をしたいのかが分からなくなります。そういう凝り固まった思考をできる限り取り払う支援をしていくことが、経営層や人財育成担当の重要な役割なのだと思います。やはり必要なのは、コミュニケーションです。1on1コミュニケーションなどを通じて、一人ひとりが自分の意志を醸成できるサポートをしていきたいですね。
半田:「意志」は「自律性」と言い換えることもできるかもしれません。会社から画一的に研修受講を割り当るのではなく、自発的に学習して自己研鑽したくなるような仕組みがあれば、自律性が生まれ、意志が醸成されるのではないか。そんなふうに思います。
もう一つ重要なのは、社員がワクワクできる仕事や企画など、会社が積極的に体験の機会を増やしていくことです。日立ソリューションズは、社員がシリコンバレーで起業するチャレンジを後押しするプログラムを立ち上げました。社員の果敢な挑戦を会社が支援し伴走していくプログラムです。これもまた人財育成の取り組みの一環であると私は捉えています。
平野:テクノロジーが発達して、リモートワークなどの働き方が定着したことで、一人でできる仕事が非常に増えています。効率化や生産性向上という点では望ましいことですが、一人でやれることにはおのずと限界もあります。仕事の規模が大きくなればなるほど、チームプレーが求められます。どれだけテクノロジーが進化しても、仕事の中で人と人がつながって協力し合うことは必要であると私は考えています。
半田:同感です。私たちはマテリアリティ(重要課題)の一つとして、「価値創造を連鎖させる」ことを掲げています。ここには、企業と企業の連鎖、多様なテクノロジーの連鎖に加えて、「人と人の連鎖」も含まれます。多様な人がつながることによって、新しい価値が生まれる可能性は間違いなく高まります。
5、6年ほど前から「人的資本経営」という言葉が注目されるようになりました。人財の力を引き出す、社員が幸せになることを支援することは、すべて「人的資本」の価値を高めることにつながります。同様に、人と人の連鎖を促進させることも、人的資本経営には欠かせない取り組みだと思っています。
平野:人の連鎖をつくるためにどのような施策を行われていますか。
半田:今年に入ってから、従業員体験(EX(※1))を向上させるための分かりやすいスローガンを掲げて、社内で訴求しています。挑戦する姿勢を大切にすること、働きがいを追求すること、そして、個々の社員の能力や個性の結びつき・調和を進めていくこと──。その3つがスローガンの大きな柱です。このうちの3つめの柱、すなわち、「結びつき」や「調和」が、まさに人と人の連鎖にあたると私たちは考えています。
まずはそういった活動を通じて、多くの社員に人的資本経営がめざすところを理解してもらいたいと思っています。
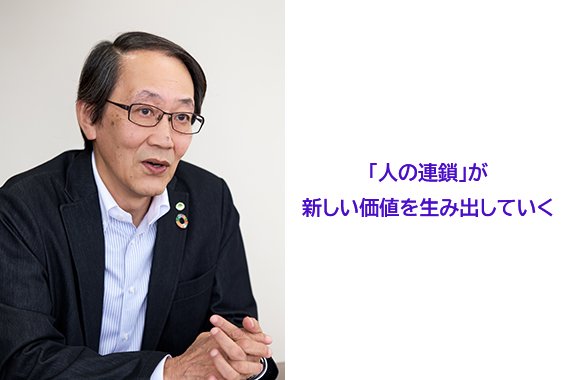
平野:人的資本経営を実現する方法は会社によって異なりますよね。自社の事業やカルチャーを踏まえた上で、人財の価値を高めていくことが求められているのだと思います。
半田:社会貢献に関する考え方もお聞かせいただけますか。
平野:私は、シナモンAIという会社が存在すること自体が社会貢献であると考えています。80年後、100年後に生きる子どもたちにより良い社会を引き継いでいくこと─。それが私の人生のミッションです。そのミッションを実現するために、私はシナモンAIを立ち上げました。この会社から様々な価値を世の中に提供していくことが、すなわち社会貢献である。それが私の考えです。
半田:素晴らしい考え方だと思います。私は人事部門のトップとして、「社員のウェルビーイングを高める」ことが社会貢献の基盤となると思っています。ウェルビーイングとは、ご存じのように、身体的・精神的・社会的に満たされた状態のことで、生きがいや人生の意義など将来にわたる幸せを含む概念です。社員一人ひとりのウェルビーイングが会社の成長につながり、社会全体の持続的な幸せの実現に寄与していく。そう私は信じています。
平野:「人」に立脚したサステナビリティということですね。働く人たち一人ひとりが、自分がやりたい仕事、生み出したい価値が何かを自覚して、意志を持って日々その達成に取り組むことが、ウェルビーイングを実現するのだと思います。そのウェルビーイングの総和が社会のサステナビリティを実現させるということなのでしょうね。
半田:そう思います。一人ひとりが輝けば、会社も、社会も輝く─。そう言ってもいいかもしれません。私と平野さんの立場は異なりますが、それぞれの立場で人財を基盤としたサステナビリティの実現をぜひめざしていきましょう。