

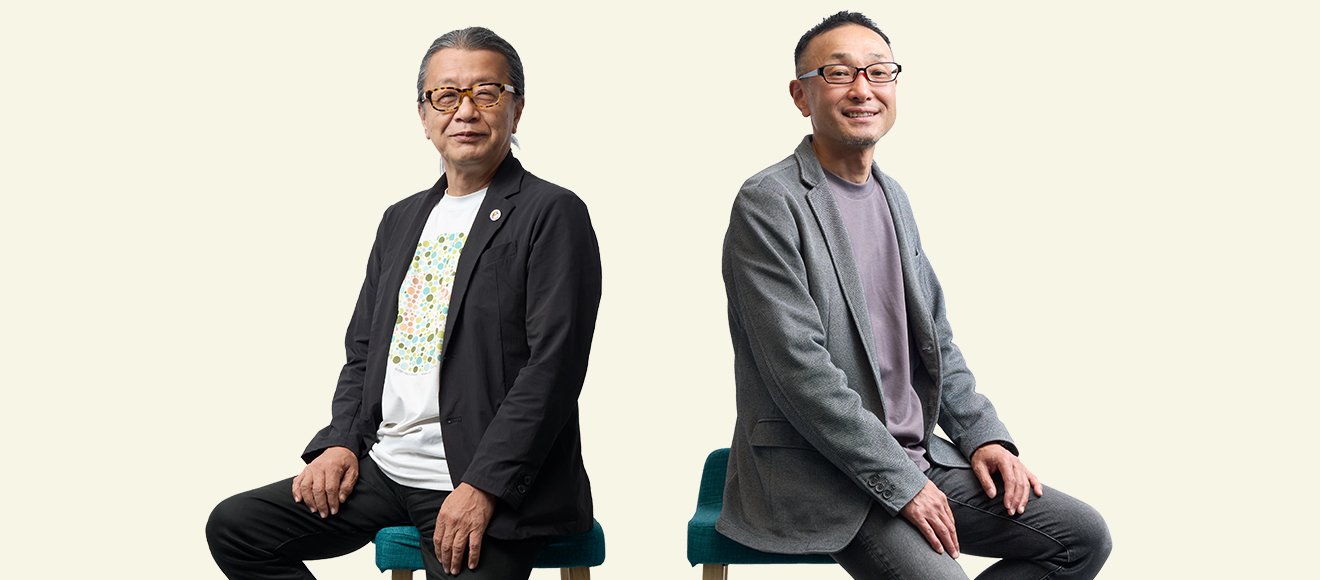
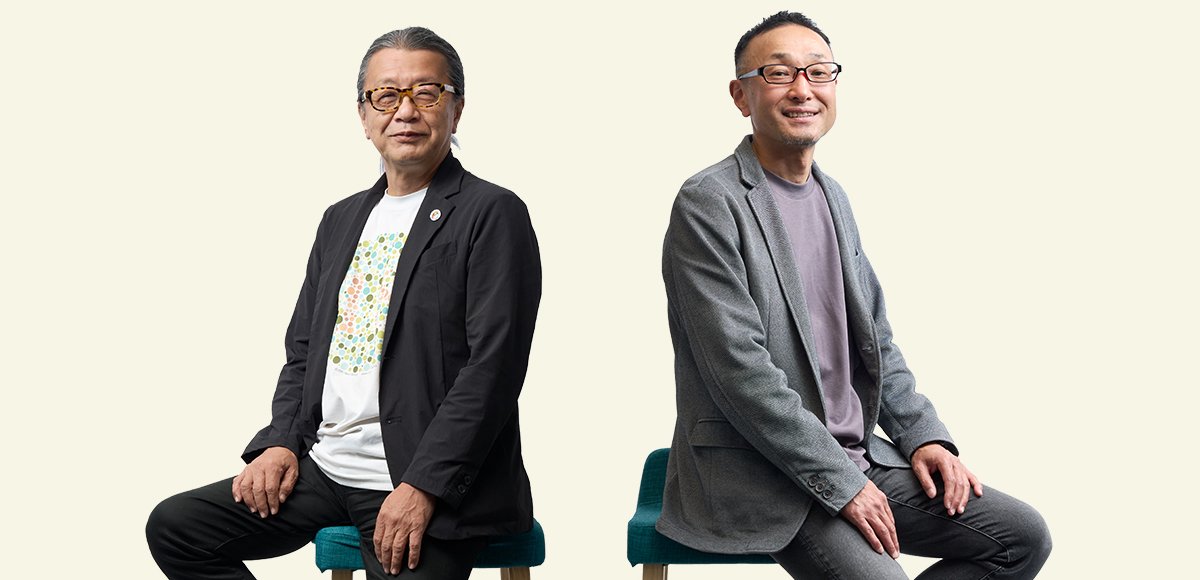
特定の色を見分けにくい、全く見えない、聞こえにくい、全く聞こえない。様々な特性の人に真に分かりやすく情報を届けるには、どうすべきか。多様な色覚に対応した色彩環境の整備を推進するカラーユニバーサルデザイン機構副理事長の伊賀公一氏と日立ソリューションズにおけるユーザビリティ向上をけん引する柳生大介が意見を交換した。

伊賀 公一
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
副理事長
先天性のP型色弱者としての自身の体験から、2004年の同法人の設立に参画。1級カラーコーディネーター資格を取得し、色覚の多様性の周知と色のバリアフリーをけん引。著書に『色弱が世界を変える』(太田出版)がある。

柳生 大介
株式会社日立ソリューションズ
技術革新本部 イノベーションデザイン技術部 主任技師
1999年入社。SEとして活動する中、ユーザビリティの重要性に気づき、2007年よりユーザーエクスペリエンスデザインに注力。HCD-Net認定人間中心専門家として、ソフトウェア開発支援の他、講演、セミナーなど社内外で啓発活動を行う。
柳生:日立ソリューションズは、ユーザーエクスペリエンス(以下、UX)デザインに取り組んでいます。ユーザーを観察しインタビューして要求を捉え、それを満たす方法を形にし、再度ユーザーや専門家に評価してもらうサイクルです。近年は情報アクセシビリティの向上にも注力しています。
伊賀:光を感じられない人には音や点字で情報を伝える、音を感じられない人には文字化するなど、情報にアクセスしやすくしようという考え方ですね。
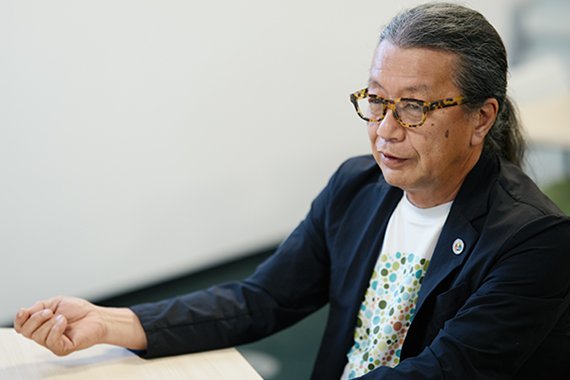
柳生:はい。当社はIT企業ですので、すべての人が簡単にウェブコンテンツを利用できるよう、ウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいます。昨年の改正障害者差別解消法の施行を前に、社員が十分に理解できるよう、一昨年から社内啓発を加速させました。
伊賀さんは、いわゆる色弱の方(以下、色弱者)に対応するユニバーサルデザインの開発と普及をけん引されていますね。
伊賀:私は生まれつき色の見え方が多くの人と異なるP型の色弱です。赤を感じる目の機能がなく、赤が暗く見えてて黒と見分けがつきにくく、さらに赤系と緑系や黄色系との区別がつかないなどの特性があります。他に緑を感じる機能がないD型や、少数ですが青を感じる機能のないT型などがあります。
柳生:日本では、男性の20人に1人がその当事者だと聞きます。
伊賀:女性は500人に1人で、男女合わせて約320万人とされています。
これだけ多いにもかかわらず、私が子どものころは大きな色覚差別があり、理科系学校に進めず、就けない職業も多くありました。日常的な困難も数え切れません。大人になってからも、この困難は続きました。
柳生:色弱者が多いのに、不便さはなぜ解消されなかったのでしょうか。

伊賀:色弱者が色について教育を通して教えられず、色をどう説明していいか分からなかったことが一因です。リンゴは黒じゃなく赤だと言われても、違いが分からない。「何色に見えるの?」と聞かれても、説明できない。
柳生:説明できないと、何が問題なのかつかめず解決策も考えられませんね。
伊賀:そうです。色の見え方が違う人同士の通訳が必要でした。
でも"熱い""冷たい"という感覚は共有できなくとも"摂氏〇度"なら共有できますね。色もマンセル値など科学的な数値が共通言語になります。そこで私は通訳になろうと考え、50歳を過ぎてから色彩学を学びました。
伊賀:そもそも色弱者自身が、分かりにくい色を使わされていると気づいていないことも、対応の遅れの大きな要因です。テレビのLEDランプは、赤が電源オフで緑がオンを表しますね。あの赤と緑の区別がつかないので、電源プラグが刺さっているかどうかを示すランプだと理解している色弱者が多かったのです。2色あると知らないから、「見分けにくい」とクレームをつけられない。
加えて、1995年頃から色を情報記号として使うことが増えました。パソコンのディスプレーがカラーになり、鉄道の路線をはじめいろいろな案内が色で示されるようになった。この時に色弱者の視点を入れられればよかったのですが、前述のように色弱者自身が不便さに気づいていないし、気づいても説明できない、さらには色覚差別もあったために言い出せなかったのです。
このような状況の中、色覚の多様性に配慮した社会へと改善していくことを目的に、仲間たちと2004年にカラーユニバーサルデザイン機構(以下、CUDO)を設立しました。

柳生:CUDOは、色覚や色覚多様性に関する情報発信の他、様々な分野にカラーユニバーサルデザイン(以下、CUD)を導入しています。
伊賀:CUDを提案し、CUD化されたものに認証マークをつけています。信号機、電光掲示板、防災マップ、トイレの男女表示など、CUDマークをつけたものは多岐にわたります。地下鉄の路線図も、路線の色を変え模様をつけてもらって、見やすくなりました。
柳生:確かに私が当社に入社した二十数年前は、社会的にも、ユーザーの多様性やユーザー視点での使いやすさに、あまり配慮されていなかったと感じます。現在は伊賀さんたち当事者のご尽力もあり、社会の意識も変わってきました。当社内でも、私たちが「ユーザーが何をしてほしいのか考えてシステムをつくろう」と啓発しており、ユーザビリティが根づきつつあります。
ただBtoBビジネスにおいては、お客様から「社内で使うものだから、そこまで配慮しなくていい」と言われることがあります。そのギャップをどう埋めるか検討しているところです。
伊賀:啓発が進むにあたり、私が懸念していることがあります。障がい者への配慮というと、アクセシビリティを第一義にすることが多い点です。
柳生:どういうことでしょう。
伊賀:その前に1つ質問ですが、最近、NHKの画面の赤い文字が、以前より橙色になっているとお気づきですか。
柳生:気づきませんでした。
伊賀:以前の濃い赤は黒と区別がつきにくかったので、色を変えてもらったのです。でも皆さんは変化に気づかないでしょう。これがユニバーサルデザインです。一般の人の見やすさを損なうことなく、色弱者の利便性が高まりました。
ところが色弱者への配慮は、色で情報を区別せずに色以外の方法で示してアクセシビリティを向上させることが、第一義に挙げられやすいのです。
柳生:デジタル庁や総務省のウェブアクセシビリティのガイドブックにも、色のみでなく文字や形でも説明することと書いてあります。
伊賀:アクセシビリティの向上は大事です。色が全く見えない人も10万人に1人はいますから。ただ、男性の約5%を占めるP型やD型の色弱者にとっては、アクセシビリティの向上だけではベストとは言えないのです。色には強い機能があって、文字や形だと近づいて読まなければ分かりませんが、色なら遠くから見ても瞬時に区別できます。色を変えてくれれば見分けがつくのに、文字や形で説明して、「色弱の人に配慮しています」というのは、極端に言えば、近視や老眼の人に、点字の利用を強制するようなものです。
柳生:色が見えるのか、全く見えないのか、0か1かではなく、特性の幅広さを理解し、ニーズに応じてユニバーサルデザインを導入したりアクセシビリティを向上させたりするという、きめ細かな配慮が求められるのですね。

柳生:やはり当事者の声を聞くことが大事だと、改めて感じました。
伊賀:対応を形にするには、ITは非常に有効だと思います。現在は、色弱の人の見えにくさを一般の人が体験できる色覚シミュレーションツールがあり、非常に重宝されています。これはITなしには生まれませんでした。
柳生:私もITには大きな可能性があると思っています。見やすい色について数値で会話でき簡単に調整できるし、文字化する、文字の大きさを変える、字幕をつけるなど、多様な情報の届け方ができます。いろいろな人にお話を伺い、実態に即した表現をITでどう実現するか探りたいと思います。
伊賀:先ほどBtoBのお話をされましたが、大企業の社内に色弱者がいないとは考えにくい。周囲の人も本人もそれと気づかないまま、色覚への対応が原因でトラブルが起こっている可能性も大いにあります。その結果、ロスや損害が出たり、本人が自信を失ったりしていることも考えられます。
柳生:もったいないことです。
伊賀:また、テレビのLEDランプの色について色弱者にアンケートをとったところ、千円高くなっても、オンとオフの見分けがつく製品を選ぶと答えています。企業は「色の見え方が違う人がいる」という視点の価値を、改めて考えてみてはいかがでしょうか。
柳生:ニーズをきちんと捉えたデザインを追求することが、企業にとっていかに重要か理解できました。ユニバーサルデザインについては規格があり、それに基づいていればいいと思っていました。でもそれで安心してはいけませんね。社内で使う資料に関しても考え直す必要があります。潜在的なニーズを正確に捉えるのは難しいことですが、どうすればいいか、自分なりに調べ、社内外に展開したいと思います。
伊賀:これまでも、企業が自社の製品やサービスにCUDを取り入れてくれたことで、この考え方が社会に浸透してきました。日立ソリューションズさんが取り組む意味は大きい。期待しています。
柳生:当社はダイバーシティを大切にする取り組みを展開しています。その一環として、アクセシビリティも当たり前のこととして捉えるべきだと、常々社内で言い続けています。今日、様々な視点を頂き、改めてその思いを強くしました。ありがとうございました。

